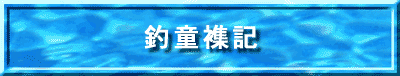
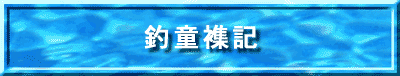
|
年齢同一性障害 |
| 年齢同一性障害 「年齢同一性障害」などという言葉はもとより存在しないのだが、自分の年齢に対する認識が実際の年齢に対する認識と一致しないということである。「性同一性障害」は、自分の肉体的な性と、それに対する違和感である。このことは当人にとって深刻で耐え難い苦痛であろう。これは見かけなど他人から見た問題ではなく、あくまで本人の心の問題であり、同じ悩みを持つ人以外には理解できないものであろう。これに対して、年齢同一性障害はそれほど深刻なものではない。私は現在72歳だが、私はこの事実がどうしても受け入れ難いのである。確かに、私は一昨年軽い脳梗塞に罹り、肉体的な老化は否むべくもないのだが、72歳という自分の年齢には違和感を覚えるのである。自分では望まないのに、年齢だけが勝手に数を増していく。「心は娘、体はおばはん」というコマーシャルがあったが、自分の気持と肉体の老化のギャップを端的に表現したもので、これは年齢同一性障害の最も典型的な症例である。 しかしながら自分の肉体的な衰え、すなわち肉体年齢を十分に自覚しながらも、なお自分の年齢を受け入れ難いという症状がある。この自分の年齢に対する違和感はいったいどこから来るのだろう。一つ考えられることは、肉体と精神の、成長と老化の曲線に相違があることに由来するのではないかと思われる。全ての人の肉体はある時点から確実に老化の下方曲線を描くのに対し、精神は個人差があるにしても、いつまでも成長し続けることが可能であるからではないだろうか。あるいは、ただ単に肉体の成熟に対し精神が未成熟であるだけのことなのかもしれない。しかしこの場合でも、肉体と精神との間にギャップが生じていると言うことに変わりはない。 一口に精神といっても、知能、判断力、気力、意欲、意志、探究心、冒険心、感性など様々である。知能の中の記憶力は老化を免れないが、判断力は年齢を重ねても老化することはなく、気力、意志、探究心、冒険心、感性などは若さを保つことができるのである。好奇心旺盛な人は若々しい。悪く言えば物見高い、野次馬根性が強い人たちである。これは、一方では向上心に繋がる。精神的な老化が進んだ人は、新しいものに興味を示さない。私の周りでも、70歳を過ぎた人で、パソコンを触る人は少ない。 私は、アウシュヴィッツ収容所での体験を記したV.E.フランクルのことを思い出した。彼は収容所にいた大勢の人たちの中で、生還した人たちに共通する精神的傾向を見出した。それは未来に希望を持っているということであった。希望を失った人たちが次々に死んでいった中で、希望を持っていた人たちは生き延びたという事実である。生きる拠りどころ、自分なりの楽しみを持つ人は、快活、行動的で若々しい。 脳梗塞に罹ったとき、私はまた釣りがしたい、渓流を歩きたいと強く望んだ。私は、リハビリのため坂道や階段のあるコースを毎日歩いた。既に500〜600kmは歩いただろうか。すべて釣りがしたいがためである。八王子の町は坂が多く、そんなに早足で歩かなくても結構足に負荷がかかるのである。また、近くに榛名神社、住吉神社などがあって、いずれも高い丘の上にありそこの階段が長いので、足腰の鍛錬になるのである。そのお陰で、私は今生徒さんと一緒に終日渓流を歩き回ることができるようになった。私は昨年内科の医師をしている二人の生徒さんと6月と7月、別々に釣りのレッスンに行った。久しぶりにお二人に会ったのだが、会った途端二人とも異口同音に「全くお変わりありませんね」と言ってくれた。 「同一性障害」は、この他のことに関しても存在するのではないだろうか。たとえば自分の理想の姿と現実の自分の姿との乖離である。この乖離に悩む人は多いことだろう。このように考えてくると、この種の乖離は多数存在していることが分かる。これらは「同一性障害症候群」とでも名づけられるかもしれない。 記憶に刻まれている昔の自分と、現在の自分のギャップも同一性障害かも知れない。人は犯してしまった過ちより、何もしなかったことへの後悔の方が大きいと言われているが、たとえそれが間違ったことであろうとも、あの時、ああすればよかった、こうすればよかったと後悔している人は多いことだろう。過ぎ去ったことは、文字通り取り返しがつかないのであるが、そのことは記憶の中では鮮明に生きている。その鮮明さが人を苦しめるのである。 これらの苦しみから逃れる方法はいろいろ考えられるが、感受性の強い芸術家はその苦しみも一層強いに違いない。詩人や小説家は、過去の出来事を克明に再現したり、その記憶を改竄したりして、自分の苦しみを昇華させているのではないだろうか。ブラームスの歌曲に「折ればよかった」というのがあるが、この後悔の気持が作詞者のL.ウーラントにこのような詩を書かせたのであろう。 ファウスト博士は自分の魂と引き換えに若さを得て、自分が過去にできなかったことを実現した。高価な宝石で純情な下町娘(マルガレーテ、愛称グレートヘン)を誘惑し妊娠させ、それを怒った娘の兄を剣で刺し殺し、挙句の果てに娘を捨て去るのである。何とやりたい放題、悪行の限りを尽くすのである。ファウスト博士はゲーテ自身であることは言うまでもないが、ゲーテ自身過去に実現できなかったことを、ファウスト博士に託して自分の後悔を解消し昇華させたのであろう。それにつけても、ファウスト博士が、悪魔との契約通りに地獄に落ちる寸前、マルガレーテによって救われるとは何と虫のいい筋立てだろう。ドン・ジョバンニが地獄に落ちたように、己の罪に対し、反省も改悛の情も薄いファウスト博士は地獄に落ちた方がよほどすっきりすると私には思えるのである。(2012/1/10) |