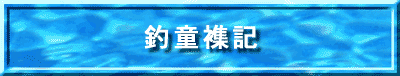
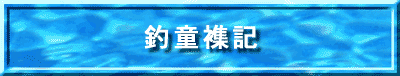
|
釣りの美学 |
|
ホイジンガは、「遊びは深いところで美的なものと繋がりを持っている」(「ホモ・ルーデンス」高橋英夫訳、中公文庫 p.28)と「遊び」と「美」の関連を指摘する。 「遊び」には、各種スポーツを始め、遊戯、歌舞音曲、狩猟、釣り、登山など身体を動かすものから、囲碁、将棋、チェス、カード、マージャンなどの頭脳的なゲーム、コレクションや模型作りなどのホビー、ルーレット、ダイス、パチンコなどの賭博まであって、その種類は多く、形態もさまざまである。いずれの「遊び」にもそれぞれの「美」が存在するに違いないが、私は「遊び」全般について幅広い知識を持っている訳ではないので、ここでは釣りに限って考察してみたい。 「美」には、所謂「美しい」という意味の「優美」の他、「崇高」、「悲壮(悲哀)」、「滑稽」、「醜」、「幽玄」、「いき(粋、意気)」など多くのカテゴリーがある。釣り人に関わりがある美のカテゴリーは、主として「いき(粋、意気)」であり、その他「悲壮(悲哀)」、「滑稽」、「醜」などが少しずつ関わっているように私は思う。 「美」のカテゴリーの対極にあるもの、それは「野暮」、「陳腐」、「低俗」、「軽薄」、「無恥」であろうか。 熟練したフライ・フィッシャーのキャスティングは惚れ惚れするほど美しい。狭いループでターン・オーバーしたラインは、揺らぎもせずに直線となって前方の水面上に伸びていく。何度キャストを繰り返してもそのフォームには狂いがない。 バランス良く捲かれたフライには、確かな「美」が存在する。人には、「黄金分割」を「美」と認識するように、アプリオリな美的尺度が備わっている。アプリオリと言えるかどうかはともかくとして、漢字を使用する人々が、内に「書」に対する絶対的な共通の美的尺度をもっているのと同じように、フライ・フィッシャーは、フライの型に対して、共通の美的尺度を持っていて、バランス良く捲かれたフライを「美しい」と感じるのである。これらは「優美」というカテゴリーに属する「美」であろう。 しかし、ホイジンガが指摘した「美」は、このような表面的なものだけでは無いように私には思われる。それはもっと内面的な、その人間の持つ「価値観」に関わるものではないだろうか。 自発的に自分に課したルールに従って、ストイックに釣りをする釣り人の姿は、「粋」であり、「悲壮」である。自分の理想とするフィッシングを追及し、その理想の実現のために釣行を重ねることは、その釣り人の美学なのである。そこには「釣れれば良い」というような低俗さは微塵も無い。 自分の利益のためとか、報酬目的で釣りをするのは「野暮」である。「遊び」はすべからく「粋」でなくてはならない。「遊び」は自腹を切らなくては「粋」ではない。スポンサー付きで釣りをするのは「野暮」である。単独では決して釣りをせず、必ず複数で釣りをし、釣行費用を少しでも安く上げようとする人がいるが、これも「粋」とは言い難い。 日常生活のしがらみを、遊びに持ち込むのは「野暮」である。釣り場へ職場の上下関係や取引関係を持ち込む人がいるが、最低の所業である。「遊び」は「日常」とは別の世界だと心得なければならない。「遊び」の世界では、「遊び」への理解、「遊び」への没入の度合い、技術力によって評価されるのであり、仮令、社会的なステータスがいかほど高くても、「遊び」の世界では通用しないのである。 最近、釣り場で同じスタイルのフライ・フィッシャーをよく見かけるが、まるでクローン人間のように良く似ていて見分けがつかない。人の真似をするのは「滑稽」である。 流行や、宣伝文句に踊らされるのは、「低俗」であり、「軽薄」である。雑誌やテレビで紹介された釣り場に殺到する釣り人の話をよく耳にするが、グルメ雑誌に紹介されたレストランやラーメン屋に押しかけるミーハー達とどこが違うのだろう?メーカーやディーラーと組んで、プロが新しいタックルの宣伝をすれば、初心者達は何の疑問も無く、まるで放流直後のニジマスのように飛びついてしまうのは、嘆かわしいことだ。 極細のロング・リーダーはハイテクの所産である。たとえば鏡のように静かな水面で、ナーバスなトラウトを狙うには、極細のロング・リーダーが必要かも知れないが、どんな釣り場でも無闇矢鱈に極細のロング・リーダーを使うのは無用であり、トラウトに対してアンフェアーでもある。 T社が製造するフライ・フックは、バーブ(返し)が極端に小さいが、これもハイテクの所産であろう。このドライ・フックはバーブが小さく、確かに鉤掛かりが良い。仮令、合わせのタイミングがずれても、魚に掠っただけで鉤掛かりしてしまう。これでは、どこに当たっても良く飛ぶ金属バットと同じである。 自分の技術を磨かずに、手っ取り早くハイテクの力を借りようとするのは、「軽薄」であり「無恥」である。(2001/3/10) |