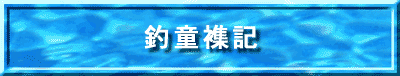
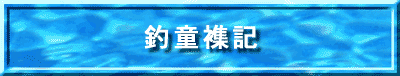
|
弘法大師空海のこと |
| 最近、誰にも束縛されることがなく、自分の時間の殆どを自分で使うことができるようになり、いろいろな本が読めるので非常に嬉しい。これほど読書に集中できるのは学生のとき以来である。尤も近頃は文学、特に長編小説の類はあまり読む気がしなくて、もっぱら哲学や宗教関係の本を読んでいる。 その人の名前が、諺や伝説にもなっているほど広く知られているのに、その人の思想や著作は殆ど知られていないという人がいるが、弘法大師空海はまさにその代表のような人であろう。弘法大師空海の業績は日本史の教科書にも載っており、各地に弘法大師にちなんだ言い伝えが残って民間信仰の対象になっているほどその名前は有名であるが、翻って、弘法大師の思想がどんなものかということに付いて、私は殆ど何も知らないのである。近頃、私は弘法大師のことを知りたいという気持が強くなってきた。 「日本の古本屋」で検索すると、弘法大師空海に関する数多くのタイトルの本が載っていたが、その中で読み易そうな気がして「空海 生涯と思想」(宮坂宥勝著、筑摩書房)を買い求めて読んでみた。この著者の解説はとても解り易く、入門者の私にとって、またとない手引書になった。 私はこの本を読んでいるうちに、 「生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに冥(くら)し。」(『秘蔵宝鑰(ひぞうほうやく)』)、 「痛狂は酔わざるを笑い、酷酔は覚者を嘲る。」(『般若心経秘鍵』)、 「凡夫の心は合蓮華の如く、仏心は満月の如し。」(『秘蔵宝鑰』)、 「虚空尽き衆生尽き涅槃尽きなば、我が願いも尽きん。」(『性霊集』巻第八)、 という不思議なリズムを持った、匂い立つような美しい言葉に出合ったのである。私が思い描いていた空海(以下<弘法大師>は省略する)のイメージとは全く違った、詩情溢れる、しかも非常に理解し易い文章であることに驚いた。私がこれまで読んだ『正法眼蔵』、『教行信証』、『歎異抄』などの仏教書とは全く類を異にしていた。私はこの文章が載っている本を是非読んでみたいと思った。 この解説書には、空海の主著は『秘密曼荼羅十住心論』と、『秘蔵宝鑰』であると書かれていた。私が稚拙な解説をするより、著者の解説をそのまま引用した方が解り易いので引用する。 「空海の密教は主著である、『秘密曼荼羅十住心論』と『秘蔵宝鑰』とにみられる十住心体系に明らかである。十住心体系は解り易くいえば、人間精神、心の発展段階を十種に分かち、低次元の世界から高次元の世界へと進展する。と同時にそれは修行の階梯および一般思想・哲学・宗教の歴史的発展の種々相を示しているものである。・・・・」(宮坂宥勝「空海 生涯と思想」13p) 空海は、第一住心は倫理・道徳以前の世界であり、第二住心は儒教その他、第三住心は道教・バラモン教・インド諸哲学などの外教であり、この中にはその当時知られていなかったユダヤ教、キリスト教、回教などもおそらく含まれるだろう。第四住心は声聞乗、第五住心は縁覚乗(以上小乗仏教)、第六住心・法相宗、第七住心・三論宗、第八住心・天台宗、第九住心・華厳宗(以上大乗仏教)、第十住心・真言密教と分類・体系化し、それぞれ詳細に解説している。この分類については空海の独創であり、真言宗以外の諸宗派から激しい異論が出たことは想像に難くない。しかしながら、この当時空海ほど世界の諸思想・宗教に通じていた人は存在せず、私はこの十住心体系を素直に受容したいと考えた。何より私がこの十住心体系に感心したのは、空海は、これらの諸宗教・思想を十段階に分類してはいるが、決して他の諸思想・宗教を排斥していないことである。この態度は一神教であるセム族の宗教(ユダヤ教、キリスト教、回教)とは明らかに異なっている。 私は早速『弘法大師空海全集』(筑摩書房)の思想篇が所収されている第一巻〜第三巻と、『性霊集』が所収されている第六巻を購入して、手始めに『秘蔵宝鑰』を読んでみた。『秘蔵宝鑰』は、『秘密曼荼羅十住心論』を要約したもので、細かく言えば多少の違いがあるようだが、空海の思想が凝縮され、全貌を俯瞰するのに適していると思われたからである。 『秘蔵宝鑰』の巻頭に美しい序文があり、すぐに「生まれ生まれて・・・・」の言葉が現われた。序文は非常に解り易く書かれており、私はすっかり空海の世界に引き込まれてしまった。「無縁に悲を起し、唯識、境を遣ればすなはち二障伏断し、四智転得す。」(絶対の慈悲の心をもって、万有はただ識のみとしてあらゆる認識の対象の実在を否定すれば、煩悩と所知との二つの障害を断ち、迷える者の心を仏の智恵にかえることができる──宮崎宥勝訳)。なんという慈愛に富んだ奥深い言葉だろう。 続いて、第一から第十までの住心についての解説がある。これは宮崎宥勝氏の適確、平易な現代語訳に負うところが多いが、この文章も極めて理解しやすいものであり、空海の思想がよく理解できる。本文については、逐一詳細を語ることは避けるが、興味のある方には是非ご一読されんことをお奨めする。 私は引き続いて『秘密曼荼羅十住心論』を読んだ。 全篇を通して、種々の経典から引用した数多くの教えが丁寧に解説してあり、仏教の真髄に触れ、知ることができるようになっている。しかしながら、全篇を読み通したが、正直なところ私には十分理解できないところが何箇所もあった。 「生死(迷い)がそのまま大いなる安らぎであるから、その上に段階などはない。煩悩がとりもなおさず菩提(さとり)であるから、煩悩を断ってさとりを得る苦労もない。」(覚心不生住心第七)とか、「もし偉大なる覚者である世尊が大智の灌頂地(かんじょうじ)にはいったならば、自らまのあたり三三昧耶(さんさんまや)の境位に住する」(秘密荘厳住心第十、大意)(いずれも宮坂宥勝訳)などの言葉であるとか、「曼荼羅」そのものの意味が、正直なところ私にはまだ十分理解できないところがある。 私は引き続き『般若心経秘鍵』と『性霊集』(『遍照発揮性霊集』)を読み終えた。『般若心経』はだいぶ以前に読んだ記憶があるが、『般若心経秘鍵』と合わせて読むと、新しい経典を読むような新鮮な驚きがあった。ついでに、『秘密曼荼羅十住心論』の文中に出てくる『法華経』を読み返してみた。『法華経』は以前読んだ時は、非常に冗長で、退屈な印象だったが、改めて読み返してみると、「正しい教えの白蓮」と称される経典だけに、以前見過ごしてしまった重要な教えが随所に現われ、私はこの経典の素晴らしさが初めて理解できたのである。 輪廻転生の考えは、古くはギリシャ時代にもあったが、仏教の根本をなす考えであり、偶々人間として生まれたものも、その行いによりいつ人間以外のものに生まれ変わるかも知れない、また、牛馬、犬猫、果ては昆虫やミミズなどに到るまで、前世は人間であったかも知れないと考えると、自ずと生きとし生けるものに対する限りない慈しみの気持が生じてくるのである。空海の重要な著作のいくつかを読み進むうちに、万物に対する慈悲と、安らぎの世界が開けてきた感じがした。空海の『秘密曼荼羅十住心論』を読んで、私はこれこそ自分の探し求めていた著書であり、思想であると思った。 聖書やコーランの「創造神」は、妬みの神、復讐の神で、自ら作った人間を、自分の意に沿わぬということで恣に滅ぼしてしまう無慈悲、冷酷な神であり、また、人間には「原罪」があって、生まれながらの罪人であるという、この宗教の根本をなす考え方には、どうにも救いが感じられないのである。 法華経に、「・・・・かの男はこれらすべての者たちに示唆を与え、示唆を与えたのちに如来の語った教えの道に入らせ、教えを理解させよう。これらの者は彼のこの教えを聴き、聴いて一瞬間・一瞬時・一寸秒の間に、すべて『教えの流れに入った者』となり、『もう一度だけこの世に還る者』・『二度とこの世に生を受けない者』となり、『二度とこの世に生を受けない者』となる果報を受けようとし、ついにはこの世の汚れをなくし、瞑想に専念し、瞑想の大名人となり、八種の開放を瞑想するアルハット(阿羅漢、仏陀)となろう。」(『法華経』岩波文庫、下巻77p、坂本幸男・岩本弘 訳・注)と書かれているが、人は修行を重ね、功徳を積めば、終には輪廻転生の輪を脱し、仏陀になることができるのである。ここには大いなる救いがあり、安らぎがある。 東寺の胎蔵界曼荼羅を見ると、私はいつか見た宇宙に浮かぶ極彩色の星雲の群れを連想する。大日如来を中心に、仏・菩薩・諸天・善神たちが居並ぶ姿は誠に神々しい限りである。おそらく輪廻転生の輪を脱したアルハットたちが、この周りに次々と参集しているに違いない。このような世界は、きっと言葉では言い尽くされることはなく、曼荼羅としてしか表現できないのではないかと、私は今考えている。(2006/8/31) |