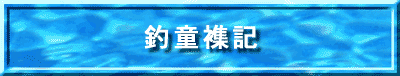
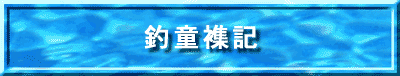
|
人は何故争うのか |
| パレスチナ、レバノンとイスラエルの紛争、アメリカとイラクの戦争、イラクのシーア派とスンニ派の抗争、世界各地で頻発するテロなど、毎日世界のどこかで紛争が起きている。考えてみると、これらはすべて、回教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒が引き起こしている紛争である。ユダヤ教、キリスト教、回教はすべてセム族の宗教であり、旧約聖書を共通の啓典としている。彼らの信仰の対象は、エホヴァ(ヤハウェ、アッラー)である。 私が初めて聖書を読んだのは、大学に入学した年だったと記憶している。それから聖書を隅から隅まで読み終えるまで三十年もかかってしまったが、自分の読みたいところ、興味のあるところは何度も読み返した。 私が聖書を読み始めてすぐに違和感を覚えた個所があった。それは「出エジプト記」第20章で、モーゼが民衆に告げた神の言葉、有名な「十戒」の中の第一戒「あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない」である。神にしてはなんという了見の狭いことを仰るものだと思った。続いて第二戒の中に、「・・・・あなたの神、主であるわたしは、ねたむ神であるから・・・・」という言葉が現われる。私はこの言葉にも、いささか抵抗を感じたものである。「ねたみ」というのは、怒りと復讐の気持を生じさせる、人間の感情の中でも決して高尚とは言えない感情だからである。しかし、当時の私は、このように考えることは誠に畏れ多いことであり、罰当たりなことであると思ったので、慌ててそんな考えを打ち消したものである。 また、「新約聖書」を読むと、<マタイによる福音書>にキリスト誕生の次第が、「母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に、聖霊によって身重になった・・・・」と説明されている。私はここでも躓いたのである。プラナリアのような下等動物や、一部の魚類は単性生殖するようだが、哺乳類である人類が単性生殖することなどありえない、と私は正直なところ思ったのである。 一方、コーランには、第64章、13節に「アッラー、そのほかに神はない。すべて信者たるものはアッラーにこそお頼り申すべきじゃ」(岩波文庫、井筒俊彦訳)と書かれている通り、回教もアッラー以外の神を認めていない。このようにセム族の神は極めて排他的であり、他の神々を信じることを一切認めないのである。 信仰の対象として共通の神を戴くユダヤ教徒、キリスト教徒、回教徒が、それぞれ相手の宗教を排斥しあい、憎みあうのは何故であろうか。私は、これら宗教同士の葛藤の歴史については殆ど無知に等しいので、このことについて云々する資格はないが、私は人は何故争うのか宗教的な理由を知りたいと思い、旧・新約聖書とコーランを読み返した。 旧・新約聖書はコーランよりずっと以前に成立した経典であり、従って直接コーランに言及することなどあり得ないのだが、コーランにはユダヤ教徒やキリスト教徒を口汚く罵った個所がほぼ全編に渡って見受けられる。尤もマホメットの態度はそのときどきによって変り、第3章、59節などに見られるように、「まことに信仰のある人はユダヤ教徒やキリスト教徒であっても回教徒と変わらず恵みを受ける」と言ったりしている他、第61章、6節では「マルヤム(マリア)の子イーサー(イエス)がこう言ったことがあったろ、『これ、イスラエルの子らよ、わしはアッラーに遣わされてお前たちのもとに来たもの。わしより前に(啓示された)律法(トーラー)を確証し、かつわしの後に一人の使徒が現われるという嬉しい音信(たより)を伝えに来たのじゃ。その(使徒)の名はアフマド』と。」(アフマドAhmadはマホメットの原名Muhammadとほぼ同義。この一節はマホメットの出現をキリストが予言していたことを示す有名な個所)(井筒俊彦訳・註)───我々が読んでいる新約聖書にこの言葉は載っていないが、マホメットは自分がこのようにキリストに予言されたことを無邪気に喜んだりしている。 ユダヤ教徒がキリスト教徒を迫害したことについては、マホメットが「かくて我々はムーサー(モーゼ)に聖典を授与し、彼のあとも続々と(他の)使徒を遣わし、(中でも)マリアムの息子イーサー(マリアの子イエス)には数々の神兆を与え、かつ聖霊によって(特に彼を)強化した。ところが、どうじゃ、お前たち(ユダヤ人たち)は自分の気にくわぬ(啓示)を携えた使徒が現われるたびに傲岸不遜の態度を示し、(それらの使徒の)あるものをば嘘つき呼ばわりし、又あるものは殺してしまいおった」(第2章、81節、井筒俊彦訳)と傍証している他、新約聖書の中には、ユダヤ教徒がキリスト教徒を迫害し、キリストを殺したことが数々描かれている。 キリストに関して「いいか、あれ(イエス)はな、ただの奴隷(人間)に過ぎんのじゃ・・・・」(第43章、59節)、「・・・・アッラーはたゞ一人の神にましますぞ。あゝ勿体無い、勿体無い、神に息子があるとは何事だ・・・・」(第4章、169節、いずれも井筒俊彦訳)などと言って、マホメットはイエスを神の子と絶対に認めようとはしない。コーランでこのように悪し様に言われたユダヤ教徒やキリスト教徒が、マホメットと回教徒を激しく憎悪したであろうことは想像に難くない。 キリスト教会が、同じキリスト教徒を「異端」と言う烙印を押して迫害し続けたことや、現在でも同じ回教徒がシーア派とスンニ派に分かれて殺しあっていることをどのように理解したらいいのだろう。要するに、全く同じ考え、同じ行為をしなければ、相手の神を自分の神と同じだと考えないのであろうか。 このように考えてくると、すべての紛争の原因がモーゼの十戒の第一戒、「あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない」と第二戒、「わたしはねたむ神である」にあるのではないかと思われてくる。ここには、自分以外の神の存在を一切認めないという極めて排他的な考えが表明されているが、このことが、宗教儀礼や伝統的慣習の少しの違いが相手の神を排斥させるという結果を招いてしまっているのではないだろうか。例えば礼拝の仕方一つとっても、キリスト教徒とユダヤ教徒では明らかに違うし、回教徒とは全く異なっているが、人は同じ拝礼をしない相手を異教徒と考え排斥するのであろう。 W.R.スミスが、その著書「セム族の宗教」の中で、「・・・・古代宗教であれ、現代宗教であれ、すべての宗教について、一方にはある種の信仰、他方にはある種の制度、儀礼的慣習、生活の規範が見られる。宗教を慣習の方面から見るよりも、むしろ信仰の方面から見ようとするのが現代の我々の傾向である。・・・・」。「・・・・結論は、古代宗教の研究に際して、神話から出発してはならず、儀典と伝統的慣習とから出発せねばならぬということである・・・・」(岩波文庫「セム族の宗教 前篇」35〜36、39ページ、永橋卓介訳)と述べているが、宗教の教義の内容は、その時々の有力な宗教指導者の考えによって容易に変化するものであり、その宗教そのものについての理解に役立つものではないという彼の考え方に私も賛同する。 同じ神を戴きながら、互いに相手の宗教を認めようとしないのは、それぞれの宗派が属する団体の、儀典と伝統的慣習に違いがあるからではないのだろうか。セム族の三兄弟とも言うべきユダヤ教、キリスト教、回教の三つの宗教が互いに憎しみ合うのは、多神教に対する憎悪以上に激しく深刻で、言ってみれば近親憎悪のようなものではないかと思われる。 私は、宗教とは一体何だろうと言うことを改めて考えてみた。私は、本来宗教と言うものは孤独なもので、個人的な心の、或いは魂の問題であると考えている。仏教的に言えば解脱、キリスト教的に言えば救済を目指すものである。或いは、生死の超越と言えるかも知れない。そこには、権威も、命令も、行動も、グループも、団体も無いのである。もっと言えば、哲学や道徳、政治や法律とも無縁のものである。 私は、学生時代に読んだシュライエルマッヘルの「宗教論」(岩波文庫、佐野勝也・石井次郎訳)を思いだして読み返してみた。これは私の宗教観を確立する基礎となった著作である。シュライエルマッヘルは、1768年、ドイツ生まれの牧師であり、カントの哲学を学び、ギリシャの古典に造詣が深かった。 シュライエルマッヘルは宗教の本質について次のように述べている。「宗教の本質は、思惟でも行為でもなく、直観と感情である。宗教は宇宙を直観せんとし、宇宙自身の表現と行為との中に在って、敬虔の念を持って宇宙に耳を傾けようとする・・・・」(岩波文庫「宗教論」49ページ、佐野勝也・石井次郎訳)。「宇宙がその豊富にして常に多産な胎から注ぎ出すあらゆる出来事は、宇宙の我々に対する行動である。かくしてすべての個物を全体の一部として、すべて制限されたるものを無限なるものの表現として受け取ること、それが宗教である・・・・」(同、54ページ)。「世界におけるすべての事件を神の行為として示すこと、それが宗教である・・・・」(同、55ページ) シュライエルマッヘルは、宗教が極めて個人的な心の問題であることについて述べている。「信仰を有ち且つ維持しようとするのは、宗教の能力の無いことを証明する。信仰を他人から要求するのは、自らこれを理解しないことを示している・・・・」。「宗教は奴隷的奉仕でもなければ捕囚でもない・・・・」(同、104ページ)。「聖典を信ずるものが宗教を有っているのではなくて、何等の聖典をも必要とせず、自らこれを造ることができる人が宗教を有っている・・・・」(同、105ページ)。 宗教は、どのような行動をも人に強いてはならないことを、シュライエルマッヘルは次のように戒める。「宗教は行動すべきだと言う此の甚だしい誤解は、同時に恐るべき悪用に外ならない・・・・」(同、65ページ)。「宗教においては、神も亦行動するものとしてしか現れず、宇宙の神的生命と行動とは何人もこれを否定しなかった。而して存在し且つ命令する神など言うものと、宗教とは、何の関係も無い・・・・」(同、111ページ)。 シュライエルマッヘルは、神と不死について次のように述べる。「・・・・私にとって神は一個の宗教的直観の方法に過ぎず、その他の直観方法は、それが他の直観方法から独立しているように神からも独立して居り、私の立場及び諸君がご存知の私の概念によれば『神なしには宗教なし』なる信仰は全然成立し得ない・・・・」(同、107ページ)。「神は宗教におけるすべてではなくして一つのものであり、宇宙はそれ以上である・・・・」。「有限なるものの真っ只中にあって無限なるものと一となり、瞬間の中にあって永遠となること、これが宗教における不死である。」 (同、113ページ)。 シュライエルマッヘルの「宗教論」を読むと、現在のセム族の三宗教が如何に眞の宗教から遠いものであるかが良く理解できるのである。(2006/11/5) |