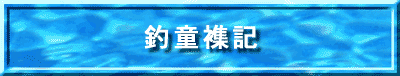
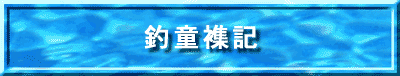
|
湯呑みのこと |
||||||
| 湯呑みのこと 最近私は湯呑みに凝っている。茶道で使う抹茶碗でなく、ただの湯呑みである。私には骨董の趣味は無い、だから古い湯呑みにはあまり興味が無い。私はお茶が好きで、毎日お茶を大量に飲む。三度の食事の後は無論のこと、朝起きて寝るまでしょっちゅうお茶を飲んでいる。お茶といってもただの煎茶である。それも高価なものではなく、あまり苦いお茶は困るが、歯茎に染みるような渋めのお茶が好きである。玉露など香りと味は良いが渋みが無いので私はあまり好まない。 私は伊藤園がペットボトル入りの冷たいお茶を売り出す十年以上も前から、お茶を冷蔵庫で冷やして飲んでいた。汲み出したお茶を麦茶用のガラスの容器に入れて冷やすのである。夏場の飲み物としてこれ以上のものはないと思っていた。最近は、無理にお茶を冷やすことはせず、4~5杯のお茶を一度に入れ、熱いお茶から自然に冷めたお茶までそれぞれの味を楽しんでいる。きちんと入れたお茶なら変色もせず、勿論味が落ちることもなく半日は十分保つのである。 以前から地方へ旅行に出かけたとき、お土産に湯呑みを求めることが多く、家に帰ってから買って来た湯呑みでお茶を飲みながら旅先の思い出を楽しんでいた。ところが、お土産の湯呑みは、その土地で作られたものが意外に少なく、デザインも似通っているのが多いので物足りなく感じるようになってきたのである。私は各地の窯の湯呑みを集めてみようと思い立った。 集める前に、少し焼物の事を知りたいと思い、カラーブックス(保育社)の「やきもの入門」を引っ張り出して読み返してみて全国にはいろいろな焼物の産地があることを再認識したのであるが、そこで私は本で読んだ焼物をインターネットで検索してみた。 「湯呑み」という言葉で検索すると膨大な数の湯呑みが見つかったが、ここに載っている湯呑みの中から適当な品を選び出すために、私は何か基準を決める必要を感じたので次のような選別基準を作った。 ①「湯呑み」は日常品であり、あまり高価なものは普通のお茶を飲むのには適さないので、価格の上限を大体2000円までとする。 ②全国の焼物の産地から、原則として一個だけ購入する。 ③デザインを重視する。 ①に付いて言えば、例えば現在珍重され、国宝や重文にも指定されている「井戸茶碗」は、元はと言えば朝鮮の日常雑器であり、朝鮮の庶民が粥か雑炊を入れたものであろうが、その作為のない素朴で、端正な姿が多くの茶人の心を捉えたものである。器の価値はその値段にあるのではないと私は考える。 以上を一応の基準として、私は湯呑みを買い始めた。 手始めに九谷焼を探した。私は以前、加賀の大聖寺川と動橋川へ釣りに行ったとき、国道脇の売店で売っていた九谷焼の蓋つきの夫婦湯呑みと大型の長湯呑みを買ったことがある。その当時の私にとって非常に高い買い物であったので逡巡していると、売り場の年配の女店員がこれでもかとばかり、小さな湯呑みを4個も5個もおまけにつけてくれた。夫婦湯呑みは極彩色の王朝絵巻風、長湯呑みは暗い赤地の上に、金の線描で仙人が佇む山水画が描かれていた。私はその赤地の湯呑みが殊の外気に入って長いこと愛用していたのだが、あるとき家人に割られてしまった。元々そそっかしい家人のことなので怒る気にもなれなかったが、それ以来あまり高い湯呑みを買うのは止めにしたのである。そんな訳で、またいつか九谷焼を買いたいと思っていたので最初に注文したのである。山水画の描かれた九谷焼はなかったので、花鳥図の描かれた大型の長湯呑みを購入した。 次に、以前何かの記事で読んだことのある小鹿田焼(おんたやき)を購入した。私は小鹿田焼の、飛び鉋の紋様が好きでどうしてもこの湯呑みでお茶を飲んでみたいものだと思っていた。小鹿田焼は、昭和初期この地を訪ねた柳宗悦をして「奇跡の窯」と驚嘆せしめ、また昭和中期英国の陶芸家バーナード・リーチによって世界に紹介された。小鹿田焼は民芸品として一つの頂点をなす存在で、お茶を飲むために作られたような器であると私は思う。それにつけても、もう少し大きな器はないものだろうか。 この他、織部焼、瀬戸焼、信楽焼、常滑焼、万古焼、備前焼、越前焼、砥部焼、有田焼、波佐見焼、唐津焼、萩焼、薩摩焼、琉球焼などの湯呑みを購入した。これらの湯呑みは、使われた土、焼き方、紋様や図柄などにそれぞれ独自の個性があり、たかが湯呑みであっても、それぞれの焼物の特徴を立派に備えている。
有田焼と瀬戸焼が全国の湯呑みの生産量の大半を占めているように私には思われるが、いろいろ湯呑みを購入しているうちに、入手し難い焼物があることに気が付いた。手ごろな湯呑みを殆んど作っていないように思われる唐津焼とか、非常に高価な作家物ばかり作っている備前焼や清水焼など、気に入った湯呑みが手ごろな価格では買えないのである。これらの産地の窯元は、何か勘違いをしているのではあるまいかと思われるほど、日常品としての湯呑みに対して理解が少ないように感じられる。 瀬戸焼、信楽焼、常滑焼、備前焼、丹波焼、越前焼は日本の六古窯と呼ばれているそうだが、これらの中で、丹波焼だけが最後まで手に入らなかった。インターネットで丹波焼を検索すると、雅峰窯という窯元のHPを見つけ、丁度手ごろな湯呑みがあったので次に注文しようと思っていると、そのHPが工事中(更新準備中)になってしまい、何ヵ月経っても更新されないので私は窯元へ直接電話した。窯元の市野秀之さんが電話に出られ、後一月待ってくれということだったが、それから暫くして納期が遅れたことに対する丁寧な詫び状と共に、湯呑みが2個送られてきた。HPに載っていたのより一回り太く、仕上がりも大変気に入ったので私は早速お礼のメールを送った。丹波、備前、越前の三つの焼物は、色合いは微妙に違うが土の味わいが似通っていて、私は何処か同じ血筋を感じたものである。 私はこれからも各地の湯呑みを愛でながら、お茶をゆっくり味わいたいと思っている。(2008/7/20) |