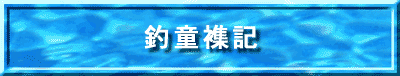
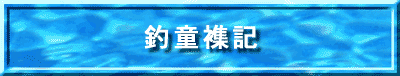
|
自己実現について |
| この歳(66歳)になって、今更こんなことを言い出すのは愚かしいことだが、私は自分が一体何者になりたかったのか、何をすれば善かったのか、最近までよく判らないでいた。 会社員になって三十数年を過ごし、そのお蔭で家族を養い、自宅を購入し、何よりも「神様はこれ以上に穏やかで、静かで、無邪気な楽しみをお造りにならなかった」とウォルトンが絶賛した釣りを続けることができ、現在年金を貰って食うに事欠くことも無いのでこのことを後悔する気持は無い。ただ、仕事をしながら、企業と、そこに働く人々の価値観と私の価値観の乖離を意識し続けてきたことは確かである。 私が、富と権力にさほど価値を認めなくなったのは、ローマ皇帝マルクス・アウレリウスの「自省録」の影響が大きい。このときの経緯については私の自己紹介で詳しく述べたので割愛するが、このとき以来金儲けや、出世に対する魅力をあまり感じなくなってしまったのである。そして私は、阿諛、追従、讒言、陰謀、裏切りなど自分を貶めるすべての行為を慎むことにした。自分の生きたいように生きるということを世間は簡単には許してくれないが、私は損を覚悟で自分の意志を貫いた。 何か人のためになることをし、その謝礼として報酬を受け取るなら、それほど違和感を持つことは無かったかも知れない。私は自分の失った可能性をいろいろと思い浮かべてみた。もしかしたら精神科医になればよかったのではないかとか、子供の頃から好きだった昆虫学者になっていればとか。或いは裁判官や検事はどうだったろう。明らかに極悪人とわかっている者の弁護はしたくないので、弁護士だけにはなりたくないが。 こんなふうに自分の過去をあれこれ振り返っているうちに、ふと学生時代卒業論文を提出した時のことを思い出した。1959年、早稲田大学第一文学部美術専修科に入学したとき、私はたいした考えも無く第二外国語にフランス語を選択した。入学後1年経って卒論に美学的なテーマを考え、ドイツ語を選ばなかったことを後悔した。当時、卒論を書くに当たって、一冊はそのテーマに関する原典を読むことが必須とされていたが、哲学方面の著作は殆どドイツ語で書かれていたからである。尤も第二外国語で学んだ程度の語学力で、カントの「純粋理性批判」や「判断力批判」が読めるとはとても思えないのだが。 私は最初、「美と祈り〜芸術の超越性と内在性について」と言うテーマで卒論を書き始めた。書いているうちにテーマが「超越性と内在性」から「美の可能性」へと変わっていった。私は、卒論を書くに当たって参考になるものはないかと、哲学・美学、文学、美術史、音楽史など数多くの書籍を渉猟した。すぐに思い出すだけでも、プロチノス、デカルト、スピノザ、ライプニッツ、ヘーゲル、シェリング、フィヒテ、ニーチェ、キルケゴール、ロック、ヒューム、バークリー、ホッブス、パスカル、ベルグソン、クローチェ、ジャン・パウル、リーグル、リップス、トルストイ、ハンス・リック、ブルクハルト、ペーター、ラスキン、ヴェルフリン、リードなどの著作がある。結局、私が卒論で実際に参考にし、引用したのは、哲学関係では、プラトン、アリストテレス、カント、ショーペンハウエル、ディルタイ、フッサール、ヤスパース、ジンメル、ヴォリンゲル、邦人では大西克礼、井島勤、阿部次郎、守屋健二、鬼頭英一、岸田劉生などの著作であり、その他ヤスパース、クレッチメルなどの精神医学関係の著作、小説ではフローベールやスタンダール、シェイクスピアなどの作品である。私は日本、西洋、東洋の各美術史を読み、画集でギリシャ・ローマ時代の彫刻から現代の抽象画家までの作品に接し、ホメロス、ギリシャ悲劇を始め西洋、東洋、日本の古典文学を読み、グレオリオ聖歌から現代音楽までのクラシック音楽を、可能な限り当時のレコードやラジオ放送、名曲喫茶などで聴いた。私はこのように、さまざまなジャンルの芸術作品に接しているうちに、芸術全般を対象としたテーマに取り組んだことを後悔した。対象があまりにも多岐に渡るので、4年間の学生生活では、とても論文として纏められそうに無かったからである。 私はどうにか自分の考えを試論として纏めることができたが、完成まで6年の歳月が必要だった。私は6年生の始めに、当時の美学担当の青柳正広教授を指導教授として「美と祈り」という卒業論文のテーマを提出した。今考えれば全く無謀で失礼な話だが、実際に卒論を提出するまで教授の指導を一度も受けなかった。私は生意気にも独力で論文を仕上げて、その成果を評価して貰おうと思ったのである。もし、私の論文が箸にも棒にもかからないものだと判定されれば、その時は素直に指導を受けて翌年再提出しようと考えていた。 いよいよ卒論を提出して、面接審査の日がやって来た。教室には、青柳教授が一人で座っておられた。長身痩躯、頬のこけた面長の、やや顔色の悪い、しかしとても温厚そうな風貌であった。私は、これまで一度も教授の指導を受けなかったことが非常に失礼に当たることと認識していたので、そのことで叱責を受けることを覚悟していた。私が席に着くと、青柳先生は柔和な笑みを浮かべながら、低い小さな声で、「知らない間に哲学者が生まれていました」と言われた。私は聞き間違いではないかと我耳を疑った。聞き返すのも変なのでそのまま黙っていた。どうやら先生にご立腹の様子は無く、逆に最大限に褒めて下さっているのだということを理解した。先生は「ヴォリンゲルに少し拘り過ぎましたね」という点と、「徽宗の『桃鳩図』のところは、もう少し膨らませても良かったですね」という二点だけを指摘された。私は最後に、指導を受けなかったことをお詫びしたが、先生はにこにこと笑っておられただけだった。面接はこれで終わった。私は、自分の努力が認められたことを素直に喜んだ。哲学者と言われたことは私の全く予想しなかったことであり、自分自身その評価に値する人間だとはとても思えなかったので、先生の優しい労いの言葉だと受け取り、そのときはあまり深く考えもしなかった。 このときのことを思い浮かべているうちに、もしかしたら私はこのとき既に自分がなるべき者になっていた(自己実現していた)のではないか、ということに思い至った。そして、私は今更自分が何者になりたかったのかとか、何をすれば善かったのかなどということを考えるのは止めることにしたのである。(2006/5/11) |