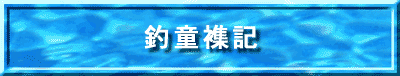
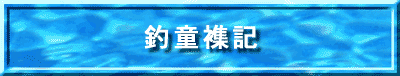
| 尊厳に対する罪 |
| すべての人に当てはまることではないと思うが、「自分の命より大切にしているもの」を持っている人たちは大勢いると私は思う。その「命より大切にしているもの」は、人によってそれぞれ違うと思うが、そういう人たちは、自分の「命より大切にしているもの」を守るためには、文字通り命を投げ出すことを厭わないのである。私は、その人の「命より大切にしているもの」を奪うことは、その人の命を奪うことより罪が重いと考えている。 「命より大切にしているもの」は、人によって異なるだろう。思想、信仰、信念、生きがい、美学、自尊心、矜持、義理、忠誠心、家族、等々、人それぞれの価値観によって「命より大切にしているもの」は、違ってくる。 「尊厳」という言葉は、「尊くして犯すべからざること」(広辞苑)の謂いであり、私は、「人間の尊厳」というのは、その人の「尊くして犯すべからざる」もの、すなわち、自分の「命より大切にしているもの」であると考える。私は、他人の「命より大切にしているもの」を奪うことは、人間の尊厳に対する明らかな冒涜であり、大きな罪であると考える。 他人の「命より大切にしているもの」を奪った人は、咎めを受けることは無いのだろうか?例えば、「命より大切にしているもの」が、その人の家族の命であればどうだろう?法治国家なら、その行為は、当然罪に問われ、刑罰が免れないであろうが、江戸時代以前のわが国では、将軍家とか、諸大名が、自分の家来やその家族を、どのように処分しようが、誰からも咎められることは無かったのである。現代を含め、世界の歴史を見渡すと、時の独裁者、権力者は、マルクス・アウレリウスなどごく一部の例外を除いて、他人の「命より大切にしているもの」を平気で奪い去るのである。 他人の「命より大切にしているもの」を奪っても、奪った人間が権力者なら、本当に誰からも咎めを受けることは無いのだろうか?私はそんなことは決してないと思う。「命より大切にしているもの」が、仮令法律の対象外の精神的なものであっても、結果は同じことである。「因果応報」という言葉があるように、人間が、人間として許される行為の限界を超えたなら、人間を超える存在が、その人間の行為を許すことは無いと考える。 最近、私は「一期一会」という言葉の由来が知りたくて、山上宗二記(やまのうえのそうじき)を読んだ。三省堂のコンサイス人名辞典(日本編)によると、山上宗二(1544〜90) という人は、安土・桃山時代の茶人・富商で、堺の山上に住み、山上を姓にしたという。千利休の二十年来の弟子で、理論・実技共に優れ、豊臣秀吉に召されて、茶頭(さどう)となったが、自負心が強く直言家であったので秀吉に嫌われ、1583年から諸国を放浪した後、1590年小田原の陣で秀吉と対面し、利休の仲介で許されながら、早雲寺での茶会で秀吉を立腹させ、耳・鼻をそがれ、惨刑に処されたと伝えられる、とある。 山上宗二という人は、たとえ相手が天下人であっても、茶道においては自分の方が上だという矜持があり、茶道に対する自分の信念(美学)を、秀吉に押し付けたものと私は理解している。茶道というのは「遊び」であり、遊びの中に身分の上下を持ち込んではならない、という遊びの精神が理解できない無粋で下司な秀吉には、権力を恐れぬ宗二の態度が我慢できなかったものと思われる。 山上宗二が殺された翌年の1591年、師の千利休も同様の理由によるものであろうが、秀吉の命によって自害させられたという事実を知って、私は暗澹とした気持になった。出世のためには、主人の草履でも懐に入れて暖めたと伝えられる、言ってみれば、出世のためにはどんな苦労も厭わず、恥を恥とも思わない秀吉にとって、自分の信念のためには命をも投げ出すという利休や宗二の気持は到底理解できず、むしろ不気味さや、恐怖すら覚えたに違いない。秀吉は、ただ人を殺めたのではなく、その人間の信念や、美学を抹殺するために人を殺したのである。これは、明らかに「人間の尊厳」に対する冒涜である。私は、この行為は人間が超えてはならない、神の怒りに触れる行為だと感じた。そのとき私は初めて、何故、豊臣家があれだけ早く滅亡したのかという理由が理解できたような気がしたのである。 織田信長の場合は、彼の暴虐の数々を見ると、彼の破滅に至る因果関係は、秀吉の場合より、もっと明白である。比叡山の焼き討ち、一向一揆の抹殺、明智光秀の母親殺しなど、信長の「人間の尊厳」に対する陵辱を見ると、彼の悲惨な末期は当然の帰結のように私には思われる。 卑近な事例で、秀吉や信長と比較するのは気が引けるが、私が、子供の頃に出会った事件に付いて触れてみたい。1954年(昭和29年)12月22日、当時私は中学2年生だったが、街頭テレビで放映されていた「力道山対木村政彦」のプロレスの試合を見ていた。当時の力道山の人気は凄まじく、後の美空ひばりや、石原裕次郎などのスターですら足元にも及ばぬ国民的英雄であった。一方の木村政彦は、「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」と称えられる不世出の柔道家であった。両雄並び立たずという言葉があるが、両者の雌雄を決すべく、蔵前国技館で日本重量級選手権が開催されたのである。結果は、木村政彦が喉元に力道山の空手チョップを打ち込まれ、立ち直る暇もなく、テンカウントされ惨敗したと私は記憶している。見ていて、私は喉元への空手チョップは反則ではないかと思ったものである。ひどく後味の悪い、嫌な感じがした試合であった。 私はこのとき、力道山が木村のプロレス生命を奪ったばかりでなく、木村の武道家としての誇りまでも抹殺してしまったのを目の当たりにした。力道山は、木村政彦という人間の尊厳を冒涜したのである。そのとき、ふと、この男(力道山)は、碌な死に方をしないだろうと不吉な予感がしたのを、私は今でもはっきりと思い出すことができる。 力道山の、国民的英雄という虚像は年を追うごとに崩れ、小心で凶暴な性格が災いして、毎年のように暴力沙汰を起こして新聞紙上を賑わせていたが、1963年(昭和38年)の12月8日、赤坂のクラブで若い暴力団員にナイフで腹を刺され、その1週間後の12月15日に非業の死を遂げたのである。(2003/10/15) |