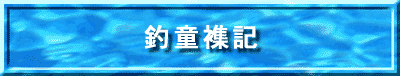
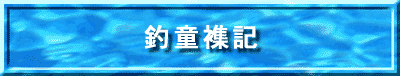
|
坂口紀三和さんのこと |
| 坂口紀三和さんのこと 自分の何気ない言動が人を傷つけたり、人の恨みを買ったりすることはよくあることだが、その反対の話はあまり聞かない。だが、自分では深く考えずにしたことが、人に強い恩義を感じさせたりすることも偶にはあるようである。 坂口紀三和(きみかず)さんの名前は一般には知られてはいないかも知れないが、ポピュラー音楽やジャズ、映画のファンならご存知の方も多いことだろう。 私が坂口さんに初めて出会ったのは、私がビクター・レコードでジャケット編修(制作)の仕事に関わって何年か過ぎた頃のことである。当時私は邦楽部というところに所属していた。邦楽部は、国内で制作するすべてのジャンルを担当していた。私は流行歌や国内制作のポピュラー音楽などのジャケット編修を担当していて、アーチストの撮影やデザイン、LPの解説 (ライナーノート)などを発注し、印刷、加工の仕上がりまでを見ていた。 仕事柄いろんな方と知り合いになった。ある日坂口和澄(わずみ)さんという方が編集室を訪ねて見えた。話を伺うと、長年Kレコードでデザインの仕事をして来たが、退社してフリーのデザイナーになったとのことである。一口に言えば売り込みであった。私は坂口さんのKレコード時代の作品を見せて貰ったが、レタリング(書き文字)が個性的で魅力があり、作品によっては上手くマッチすると思われた。そのときは生憎適当な内容の作品が無かったが、後日坂口さんに合ったレコードがあればデザインをお願いするということで別れた。 その後坂口和澄さんには時々ジャケットのデザインをお願いしたりして、親しく話すようになった。坂口さんは下駄のように四角張った顔で磊落な感じで、お互い関西系ということですぐに親しくなった。和澄という名前から私は彼の出身地が和歌山と見当をつけたが、実際はご両親が和歌山出身で和澄さんが生まれたのは東京だということだ。私は大阪で生まれ小学3年までを関西で過ごしたのである。暫く付き合っているうちに、和澄さんの弟の紀三和さんが早稲田を卒業したが、就職もしないでぶらぶらしているので困っている。ついてはポピュラー音楽に詳しいので、もし良かったらレコードの解説を書かせてやって貰えないかと言われた。和澄さんは弟さんを愚弟と呼んでいたが、私はその言葉の中に弟への強い愛情を感じた。私は近いうちに弟さんに会ってみることにした。 数日経って坂口紀三和さんが来社した。学科は違うが文学部の後輩である。1946年和歌山の生まれで、私とは6つ違いである。お兄さんと違って、華奢で繊細、体はあまり丈夫そうでなかった。見るからに生真面目な学者タイプで、風貌はどこか詩人の藤浦洸さん(「別れのブルース」「悲しき口笛」「東京キッド」などの作詞者)に似ていた。私はタイトルは忘れたが、ジャズのレコードの解説をお願いしたと記憶している。その後幾つかポピュラー関係の解説をお願いしたが、邦楽部には坂口さん向きの企画が少ないため、洋楽部の編集担当を紹介したりした。紀三和さんは子供のように純粋無垢、その上温厚な性格で、怒った顔など一度も見たことが無かった。また、博覧強記の上に聞き上手であり、私は彼とクラシックや哲学、絵画などについて話をするのが楽しみであった。その後彼は、レコード各社の解説ばかりでなく、「スイング・ジャーナル」や「キネマ旬報」など音楽雑誌や映画雑誌にも広く執筆するなど活躍の場を広げていった。 私はその後ジャケットの制作現場を離れて、音楽テープの営業や制作をしたりしていたが、紀三和さんは、私が初めて原稿を依頼したときからずっとお中元やお歳暮を贈ってくれていた。特別高価なものではないが、心のこもった、紀三和さんらしい気の利いた品である。私はジャケットの編集から離れたので、盆暮れの付け届けは止めにして欲しいと紀三和さんに頼んだ。彼は「私が今こうやって食べていけるようになったのは、柳原さんが最初に仕事をさせて下さったお陰ですから」と、私の申し入れを断った。彼が音楽や映画の解説者として活躍しているのは彼の不断の精進と研鑚の賜物からであり、私としては特に恩に着て貰うほどのことはしていなかったので非常に心苦しかった。 10年ほど過ぎて、私は今度はビデオ関連のジャケットを編修することになった。前任者が都合で異動したため、私がピンチヒッターで呼ばれたのである。そこで再び坂口さんと仕事をするようになった。彼と話すのは私の大きな楽しみであった。彼は何か解らないことがあるとすぐに調べてくれ、仕事のことで話すことはもうあまり無かったが、例えばキャスリーン・フェリアの「亡き子を偲ぶ歌」のことや、ヤスパースの「哲学三部作」のことなど、むしろ仕事以外のことで話が盛り上がった。彼は私に再三インターネットを始めるように勧めてくれた。当時私はITについては無知であり無関心だった。私はこの件についてだけは彼の話を聞き流していた。 ビデオ・ディスク(VHD)の事業が頓挫し、私は自ら希望して人事部の研修担当になり、八王子に異動した。彼は電話をくれて、都内に出て来られたら是非会いたいと度々言ってくれたが、都心に出るのはいささか億劫だったので、その後彼と会う機会はあまり無かった。私は定年の1年前に早期退職し、HPを立ち上げてフライ・フィッシング教室を開いた。彼にメールすると非常に喜んでくれて、「こうやってメールのやり取りができるのは夢みたいです」と言ってくれた。また、私のHPの自己紹介を読んでくれて、「巧まざるユーモアに溢れていて非常に面白い」と褒めてくれた。 私が退職してからも、坂口さんから盆暮れの贈り物が届いていたので、再三止めてくれるようにお願いしたが、頑として聞き入れてくれなかった。私は彼の恩義の厚さに感心した。義理堅さなどといったありふれた言葉ではとても言い尽くせない、凛としたものが感じられ、私はそれからは彼の厚意を有り難く受けることにした。 あるとき人伝に、坂口さんが入院していると聞いて、私は千疋屋から果物をお見舞いに送ったことがあったが、彼から「普段口に出来ないようなものを頂いて」と、恐縮した礼状が届いた。その後時々メールでやり取りをしていたので、私は彼の病状が回復したものとばかり思っていた。 2006年の年明けに、突然坂口さんの奥さんから、欠礼の葉書が届いた。読んでみると、暮れの12月に紀三和さんが亡くなられたと簡単に書かれていた。私はとてつもなく大きなものを喪失したと感じた。後悔先に立たずと言うが、私は何故もっと頻繁に彼と会っていろいろ話をしなかったのだろうと悔やんだ。 後でお兄さんが、紀三和さんの最期の様子を詳しく語ってくれた。それによると、もともと病弱な体質であったが、医者嫌いでよくよく悪くならないと病院に行かなかったそうだが、あるとき、虫歯の治療をしていて、吐き気を覚えて治療を続けられず、そうこうする内に虫歯の菌が心臓の弁膜を冒し、日本医大に入院して心臓のほうは完治したのだが、精密検査で胃癌が見つかったというのである。胃癌が見つかった時には、あちこち転移していて既に手遅れであったらしい。亡くなったのは2005年12月20日、享年59歳という若さであった。 晩年、不自由な体を奥さんに支えられながら、京都精華大学へ客員として、月に1回のペースで日本ポピュラー音楽史の講義に通ったそうである。その途次生まれ故郷の和歌山へ行きたがったが体がままにならず断念したという。私はその話を聞いて涙が出そうになった。 人情紙の如く薄い現代にあって、彼ほど義理に厚い人を私は知らない。若いころ受けたささやかな恩義を、死ぬまで忘れずにいてくれたのである。論語の世界でも彼ほどの人物は登場しない。私は彼の厚意に報いるため、一人でも多くの人に彼のことを知って貰おうと思い、彼の憶い出をHPに書こうと思ったが、「恩を早く返そうとするのは、忘恩の証」という言葉を思い出してすぐには書かなかった。今回、坂口さんが亡くなって5年が経つのを機に書いてみようと思った次第である。(2010/1/15) |