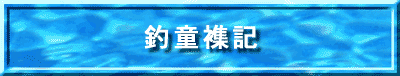
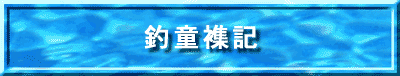
| 八王子山岳展望〜寝顔山と白馬の雪形 | |
| 奥多摩の寝顔山 よく見かける面白い形をした山があるのだが、その山の名前が分からない。それが何と言う山の名前か知りたいと思っても、登山愛好家でもなければ、その山の名前を知る手がかりやチャンスはなかなか無いのである。 私が住んでいる八王子の自宅の、すぐ裏手に小比企丘陵という丘があり、20〜30mほどの高さなので、私の手ごろな散歩コースになっている。東は、国道16号線の片倉付近から始まり、西は大船町まで、或いは相模原市との境界である七国峠辺りまで入るかも知れないが、七国峠辺りまで入れても東西の全長が4〜5kmほどの小さな丘陵である。丘の上は開けていて、畑や雑木林がある。十年ほど前から八王子南ニュータウンの造成が始まり、最近ではみなみ野という新しい町ができて丘の縁(へり)近くまで迫り、雑木林や畑はすっかり小さくなってしまった。 私が八王子に越して来た二十数年前、この丘陵一帯は雑木林に覆われ、軽トラックが1台通れるだけの道幅しかない農道(昔の地図には都道と載っている)を上っていくと、七国峠へのハイキングコースになっていた。その頃すでに、このハイキングコースは廃れてしまっており、道標は朽ち果て、訪れる人も殆ど無かったが、それだけに豊かな自然が残っていて、蛍は勿論、雉や狐などの姿を見ることが出来た。七国の名前は、みなみ野に出来た新しい町の名前として残り、往時を偲ぶよすがとなっているが、この町の住人はこの名前の由来を恐らく知らないだろう。 散歩の帰り道、なだらかな坂(幻の都道)を下る途中、私の視線の真正面(北西方向)に、仰向けに寝ている可愛い童女の横顔のような形の山が見える。下脹れの、どこか気品のある容貌で、菩薩の寝姿のように見えないこともない。私はこの山を、『寝顔山』とか『菩薩の寝姿山』と名づけ、四季折々、また時間によって変化する姿を楽しみに眺めている。 この山の形はとても個性的なので、どこから見てもはっきりと『寝顔山』だということが分かる。この山は、小比企丘陵からだけでなく、八王子市内では御殿峠や石川町、あきる野市の小峰峠の下、日の出町の平井付近などあちこちで見ることが出来る。あるとき、私は秋川に釣りに行こうと美山町の山入川沿いを車で走っていると、目の前にあの特徴のある山が顔を出しているのが見えた。私は、道端に車を止め、近くにあった中古車売り場の若い店員さんを掴まえて山の名前を聞いてみた。「さあー」と、彼は怪訝な顔をしていたが、勿論山の名前など知らなかった。富士山とか、自宅の裏山の名前は知っていても、遠くにチラッと見える山の名前など、大抵の人は知らないのである。 私は、多摩全図を買ってきて、目撃した5箇所の地点から『寝顔山』の方角へ線を引いてみた。目撃地点と角度が不正確な所為か、奥多摩の御岳から大岳山辺りの範囲である事は分かったが、御岳も大岳山も、麓の渓流で釣りをしたことはあるが、どちらの山も登ったことが無いので、結局山の名前は分からず仕舞いだった。 私がこの『寝顔山』を始めて見たのは何年前だったか確かな記憶は無いが、恐らく十年を下回ることは無いだろう。十年以上も、私はこの山の名前を知らずに過ごしてきたのである。名前を知らなくても不都合なことは全く無いのだが、それにしても、すぐ目の前にある山の名前が分からないのは、ひどくもどかしいもので、正直なところ、口惜しくて仕方がないのである。 最近、ふと思いついて、インターネットで奥多摩の山々の名前を入力して検索してみた。登山の記事には、頂上から撮影したパノラマ写真などが載っていることが多いので、もしかしたら『寝顔山』の写真が写っているかも知れないと思ったからである。御岳や戸倉三山を手始めとして、いろいろな山のことが書かれたホームページを覗いてみた。 遂に見つけた!「馬頭刈山」(まずかりやま)(884m)という項目でホームページを開いてみると、よく見慣れたあの『寝顔山』の鼻と顎が写っているではないか!キャプションには「馬頭刈山山頂からの大岳山」と書いてある。これが大岳山だったのかと、私は初めて『寝顔山』の本当の名前を知ることが出来たのである。 大岳山の名前は非常にポピュラーであり、私もよく知っているが、それがどんな姿をしているのかは全く知らなかった。私がよく釣りに行く秋川の支流に、毛鉤釣り場で有名な養沢川というのがあって、上流で御岳沢と大岳沢の二本に枝分かれする。私は大岳沢でも釣ったことがあるが、養沢川や大岳沢からは、大岳山は近過ぎて視界を遮るものが多い所為か、その姿を見たことが一度も無かったのである。 |
|
|
|
私はこの大発見(?)に興奮した。十数年もの間知りたくて仕方なかったことが、やっと分かったからである。私はだれかれ構わず吹聴したくなり、まず女房に話してみた。すると、「そう」と、あまり興味の無さそうな返事が返ってきた。私はこの発見が、私以外の人間にとっては、それほど重大なことではないらしいと気づいたのである。 丹沢の白馬の雪形 八王子に大雪が降ると、自宅二階にある私の書斎の窓から、近所の家の屋根越しに見える山の中腹に、白馬の雪形が現われる。どういう加減で出来るのか分からないが、今まさに左向きに跳ね上がろうとしている見事な白馬の雪形である。八王子の西南の方角にあるので、丹沢山塊だと思うのだが、その山の名前がこれまた分からないのである。 最近、近所の家の庭木が伸びて雪形が見え難くなったが、自宅の裏手を流れる浅川支流・湯殿川に掛かる大橋(名前ほど大きくない)の上から、川の上流方向真正面に白馬の雪形がくっきりとよく見えるので、雪の降った朝は、その橋まで雪形を見に行き、デジカメで写真を撮ったりしている。 |
|
|
|
私がこの雪形に気づいたのは、まだ私が会社勤めをしていた頃だから、今からもう5〜6年前のことになる。最初に見たのは、雪が降った翌日の午前中だったから、恐らく土日の休みの日だったと思う。八王子の富士森公園から山田川に向かう坂道を車で下りながら、ふと目を上げると、正面に見える山の中腹に、はっきりと白馬の雪形が現われていたのである。帰宅して、私は二階の窓を開けて丹沢の山を見てみた。すると、近所の家の屋根の上に、はっきりと白馬の雪形が見えたのである。丹沢は、大岳山(寝顔山)よりずっと遠いので、午後になると空がかすんで見え難くなる。また、真冬の空が澄み切った日でないと、雪形がぼやけて判別できなくなってしまうので、大岳山より見える確率が低くなり、八王子辺りでは、この雪形に気がつく人は少ないのではないかと思われる。 2001年3月、私は伊豆に初釣りに出かけた。厚木ICから東名高速に乗ってしばらく走っていると、防音壁が途切れてぱっと視界が開け、右手のすぐ間近に、あの見覚えのある白馬の雪形が大きな姿を現したのである。(このときのことは、『最新フィッシング・レポート(6)』に書いた)こんなに間近に見える、この珍しい雪形のことを誰も騒がないのは、私には不思議に思われた。私は、この山が丹沢の大山(1252)に違いないと思ったが、確認できないでいた。 つい最近、『寝顔山』が大岳山だと判明した後、もしやと思って、またインターネットで丹沢・大山を検索してみた。300項目ほど検索してみたが、雪形のことも、この山の名前も分からなかった。 万策尽きた私は、インターネットで見つけた厚木市観光協会と、<景図工房>というところに、雪形の写真を添付して山の名前を問い合わせてみた。 その夜遅く、<景図工房>の田部賢一さんから雪形の山が同定できたという返事が来た。それによると、この山は大山ではなく、丹沢の蛭ヶ岳の東にある、通称『鬼ケ岩ノ頭』(1608)と呼ばれる山であるということだった。 <景図工房>というところは、鳥瞰図、展望図、風景写真の作成・販売を仕事にしているところで、山の写真は、それを撮った位置と方角さえ判れば、それがどこの山か、正確に短時間で同定(特定)し、それをCGで表現してしまうという、私のような素人から見れば、魔法か神業のような技術を持ったところである。 翌朝、田部さんから、白馬の雪形を<景図工房>のホームページの〔GALLERY2〕に、掲載したという連絡が来た。 http://www.kei-zu.com/main/hachiouji/hachiouji.html 誠に見事な出来栄えで、周辺の山々の名前もすべて同定してあり、非常にわかりやすく出来ている。私は、長年の疑問が解けたことに対してお礼のメールを書き、八王子から見える『寝顔山』(大岳山)の写真をまた送った。田部さんは、この『寝顔山』という表現が気に入ったらしく、一緒に写っている奥多摩の山々を同定して、また同じホームページにupしてくれたのである。 二日後、厚木市観光協会から、雪形が丹沢最高峰・蛭が岳近くの鬼ヶ岩(1608)の、津久井側に下る尾根の上に現われたものであるというメールが来て、参考として雪形の記事が載っている、2001年1月18日付の神奈川新聞のコピーを郵送すると書いてあった。翌日、新聞記事のコピーが届いた。そのコピーには、『丹沢に白馬』という見出しで、「鬼ヶ岩の津久井側尾根に現われた大きな白馬の雪形」というキャプションの付いた大きな写真とともに、詳しい解説が載っていた。記事の中で、地元津久井町鳥屋のNさんの、「昭和四十年代に現地の木を伐採した」という話が紹介され、伐採跡に積もった雪と、周囲の林とのコントラストで、白馬の雪形が現われるようになったらしい、と書かれていた。 私は、この白馬の雪形が地元では早くから知られていたことを知って納得した。伐採跡に積もった雪が雪形の起源らしいということも判り、すべての疑問が氷解したのである。しかし、将来、伐採跡に再び樹木が生い茂ると、恐らく雪形も見えなくなるだろうということが想像され、今のうちにこの雪形を大いに観賞しておきたいと思ったものである。私は、厚木市観光協会の担当者に、感謝を込めてお礼のメールを送った。 私は改めて、情報収集の手段としてのインターネットの威力に脱帽した。 (2004/2/26) |