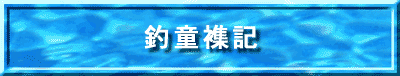
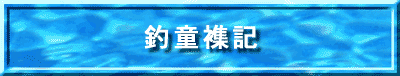
|
長年の探しもの |
| 長年の探しもの パウル・バドゥーラ=スコダの「ショパン:ピアノ協奏曲第1番」 長年探し求めていたものに巡り合えた時の喜びは何ものにも替え難いものがある。 誰にももう一度聴いてみたいと思う曲が1曲や2曲あるに違いない。人は時とともに変ってしまうが、芸術作品は時間と空間の影響を受けることはない。 昭和30年代、私が学生だった頃のことである。当時私は都下の小金井市に住んでいたが、学校に行くつもりで家を出るのだが、途中吉祥寺とか新宿で下車してしまい、なかなか学校のある高田馬場まで行き着けなかった。小遣いが潤沢にある方ではなかったし、映画や賭け事などに興味の無い学生が何故吉祥寺や新宿で下車したのかと言うと、今は殆んど見かけなくなったが、名曲喫茶でレコードを聴いていたのである。当時レコードは非常に高価で、貧乏な学生にはおいそれとは買えなかった。ちなみに、輸入レコードは1枚2,300円ほどしていた。今のCDとそれほど値段が違わないが、現在の物価が当時の十数倍になっていることを考えると当時のレコードが如何に高価だったかが分る。私は世の中に存在するクラシックの曲を、でき得る限り聴きたいと思っていた。 その名曲喫茶店の名前は吉祥寺「田園」。当時「田園」と言う名曲喫茶はあちこちにあり、その他荻窪には「グノー」、新宿には「ランブル」と言うように有名な名曲喫茶が数多くあった。いずれも高性能のオーディオ機器を備え、スピーカーもJBLだとかアルテックなど一般の人間が購入できるものではなく、当時としては最高のレベルの音で音楽を聴くことができた。演奏する曲目のプログラムの一部を自前で組むところもあれば、曲目をすべて客のリクエストによるなど店によって様々だったが、私はできるだけ多くの曲が聴ければそれでよかった。「田園」には週に3日は通ったと思うが、そこで1日に1回はレコードがかかったのが、パウル・バドゥーラ=スコダが弾いたショパンの「ピアノ協奏曲第1番」だった。演奏の前にアルトゥーロ・ロジンスキー指揮、ウイーン国立歌劇場管弦楽団の名前がアナウンスされた。私は何時だったか、レコード・プレーヤーの前に置かれたジャケットを見に行ったことがある。ウエストミンスター・レーベルで、上部3分の2がマゼンタ(印刷インキの赤)、下部の3分の1ほどが青の地色の上に、ショパンのバストアップのデッサンが黒で印刷されていた。当時、このレコードはかなり人気があったようで、半年ほどこの曲はリクエストされ続け、私も耳に胼胝ができるほど聴いた。私はすっかりこの演奏が気に入ってしまった。 ショパン・コンクールは、第1回が1927年と歴史は古いが、1955年までは優勝者がポーランドとソ連のピアニスト達によって占められていたためか、世界的にはそれほど注目されていなかったが、1960年にマウリツィオ・ポリーニ(イタリア)、次の1965年にマルタ・アルゲリッチ(アルゼンチン)が優賞し、それぞれがビッグネームとなったことで俄然有名になった。その課題曲であるピアノ協奏曲も一躍人気曲になった。 私はショパンの「ピアノ協奏曲第1番」を初めてこの喫茶店で聴いたのである。1959年か1960年のことだったと思うが、この頃この曲はそれほどメジャーな曲ではなかったと思う。私は初めてこの曲を聴いた時、何と型破りで初々しい曲だろうと感心した。それまで聴いてきたベートーヴェンなどの端正な曲とは全く違う、感性が前面に出た甘美で華奢な感じのする音楽だった。私は繰り返し何度も聴くうちに、バドゥーラ=スコダの演奏を全身に刷り込まれてしまった。とにかく彼の演奏が私にとってこの曲のスタンダードとなってしまい、後年他のどの演奏者の演奏を聴いても、しっくりこなくなったのである。 何年か経って、このレコードは廃盤になってしまい、その後他の演奏者のレコードは何枚も発売されたが、ウエストミンスター・レーベルが消滅してしまったこともあって、バドゥーラ=スコダのこのレコードが復刻されることは無かった。私はこのレコードを探し求めたが、現在のようにインターネットで検索する手段も無く、半ば諦めてしまっていたのである。 それから30年近く経って、そのころ私はビデオ・ディスク関連の仕事をしていたが、あるとき、ワーナー・パイオニアからこのレコードが完全復刻されると言う話を聞いた。1987年頃だったと思うが、私はワーナー・パイオニアの友人に頼んでこのレコードを送ってもらった。CD全盛の世の中にあって、ジャケットにオリジナルのデザインを使い、レコードとして完全復刻されたのである。家に帰って震える手でレコード・プレーヤー(デンオン、DP3000)にレコードを置き、早速聴いた。スピーカー(タンノイ、エディンバラ)から出てくる音は、まさしくあの懐かしいバドゥーラ=スコダのショパンであった。それと同時に名曲喫茶「田園」二階正面の、壁いっぱいに設置された巨大なスピーカー群や、暗い店内の光景が甦ってきた。 つい最近、私はMusic & ArtsレーベルからCD化されたこの曲を入手した。バドゥーラ=スコダの弾くショパンの「ピアノ協奏曲第1番」が一層手軽に聴けるようになって幸せに感じている。 ラッスス(オルランド・ディ・ラッソ)の「マタイ受難曲」 この曲を初めて聴いたのは、新宿の風月堂だった。1961年か1962年、まだ私が学生の頃のことである。私は古い音楽に興味があって、バッハの「マタイ受難曲」などを聴いていたが、もっと時代を遡ってみたくなって、グレゴリオ聖歌などを聞いたが、グレゴリオ聖歌とバッハの間に空白があることに気が付いた。私は西洋音楽史の本を読んで、ラッススの名前を知り、彼の受難曲を是非聴きたいものだと思った。 新宿の風月堂は新宿駅の北側にあり、二階の天井まで吹き抜けとなっていて、北側と東側の壁に狭いバルコニー式の二階席があって、二階席から一階が見渡せるユニークな建物であった。風月堂は膨大なレコードのコレクションを持っていることで有名であったが、同時に芳しからぬ噂も流れていた。それは、海外のヒッピー達の間で、風月堂に行けば簡単にガールハントできるということで有名になっているという噂だった。実際風月堂に行ってみると、怪しげな外人が多く噂はどうやら本当らしかった。私はそんなことにはお構いなく、レコードのコレクション目当てに出かけ、もしかしたらと思いラッススの「マタイ受難曲」をリクエストしてみたのである。 スピーカーから流れてきたのは、この世のものとは思えないほど清らかで素朴な歌声だった。グレゴリオ聖歌のメロディーをそのまま膨らませたような感じで、切実で敬虔な祈りをこの曲の中に強く感じた。店内のいささかいかがわしい雰囲気には全くそぐわない音楽で、店内にこの曲を真剣に聴いている人が果たして何人いるのかという気がした。私はその後風月堂には行くことはなかったが、暫く経って風月堂は廃業してしまった。聞くところによると、1960年代の後半、風月堂を舞台にいろいろな問題が起き経営者が店を閉じてしまったそうである。店には全く責任は無いのに、気の毒なことであった。 その後、私はこの曲が聴きたくて仕方がなかったが、それから10年ほど経って、NHKFMの早朝番組「バロック音楽の楽しみ」で抜粋だったが一度だけ放送されたのを、エアー・チェック(お分りにならない方も多いと思うが、FM放送をカセット・テープに録音すること)しながら聴いたことがある。 時折、カセットに録音したものを引っ張り出して聞いていたが、抜粋であるうえ音質的に満足できるものではなく、そのうちにテープがカセットの中で引っかかって動かなくなった。それ以来、ラッススの「マタイ受難曲」は、私にとって幻の音楽となってしまった。 ところが、つい最近ネットの検索に引っかかったのである。私は、探している曲とか、本の名前を駄目元で時折ネットに打ち込んでいるのだが、3ヵ月ほど前、HMVでラッススの名前でCDを検索したら、harmonia mundiレーベルの「マタイ受難曲」が見つかったのである。演奏者も録音も以前のものとは違うが、紛れもなくラッススの「マタイ受難曲」そのものである。 私は、当時の風月堂のことを思い出しながらラッススの「マタイ受難曲」を聞いている。(2008/9/25) |