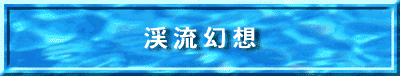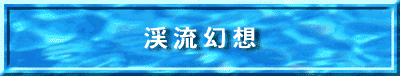|
柳原 釣童
不思議な話
昨年の2月下旬、突然、高校時代からの友人であるMから、添付文書つきのメールが送られてきた。メールを読むと自伝を出したいので文章を読んで欲しいと書いてあった。どうやら読んで添削して欲しい、と云うことらしい。後で聞いた話だが、パソコンを最新型に買い換えたら、あまりに使い勝手がいいので、少年時代から記憶していることを次から次へと打ち込んだと云うことだ。書いているうちに、ある出版社の原稿募集の広告が目にとまり、その中に優秀作品は出版社の責任で出版すると書いてあり、Mは、あわよくば出版社の費用負担で「自伝」を出版しようと目論んだようだ。
添付文書を開こうとしたが、これが文字化けしたりしてうまくいかない。しかたがないので、テキスト文書で開き、それをワードにコピーした。400字詰め100枚もある長大な文章で、些かうんざりしたが、幼少期の、家族で満州から引き上げてくる話は迫力があり面白かったのでつい引き込まれて読んでしまった。中でも、彼の父親が出征中で、身重の母親が一人で幼い4人の子供を連れて、危険な目に遭いながらも気丈に振舞い、困難を乗り越えて帰国する件(くだり)は感銘を受けた。私はMの母親をよく知っているが、あの温厚なお母さんが当時の凄惨な修羅場を潜り抜けてきたことなど想像すらできない。まさに「母は強し」である。
Mは「自伝」を書き上げて出版社に投稿したが、残念ながら採用にはいたらなかった。その代わり、出版社から自費出版を持ちかけられた。書店への配本から、宣伝まで面倒を見るということだったので、彼はその話に乗って自費出版に踏み切ったのである。
7月に入って、出来上がった「自伝」が私の手元に送られてきた。彼の小学校から大学までの生活が描かれている前半には、当然私との交友の経緯も描かれている。読書の習慣のないMに、岩波文庫の青帯を何冊も強引に読ませた私の押し付けがましさなどが克明に描かれていて、今考えるとお節介の極みである。彼の自伝を改めて読み直しているうちに、当時の記憶が鮮明に甦ってきた。私自身は父親の勤めの関係で小、中学校を通じて6回転校しており、その経験から瞬時に相手を敵か見方か見分けることができるようになっていた。Mはその点申し分のない相手で、善良で、間違っても人の足を引っ張ったりするようなことはなかった。
同じクラスであり、互いの家が近かったこともあって、学校から帰ってからも、われわれは毎日のように会っていた。高校で、殆ど二人だけの陸上部を創って日暮れまでグラウンドを駆け回ったり、生物部を創り、生物教室を借りて一晩中電灯を点けっ放しにして、昆虫の夜間採集をしたことなどが思い出された。当時、学校は畑と林に囲まれていて、蛾や甲虫類がたくさん採れた。また、もう一人の友人であるKと、Mの家に押しかけ、休日前など泊りがけで花札(もちろん何も賭けてはいない)で遊んだりしたものである。
出来上がった彼の「自伝」を手にして、本になるのもいいものだな、と思った。いつかは本になればとHPに書き始めた短編小説が、既にかなりの分量になっている。最近では本にしようという気持ちは失せてしまっていたが、今回のことで改めて本にしたいと意欲が湧いたのである。
私は心当たりのある出版社や、出版プロダクションに電話してみたが、10年前ならともかく、今では当時の知り合いたちは皆現役を引退してしまっており、連絡先が判らなくなったり、中には既に鬼籍に入ってしまった人もいた。自分の周りから、友人、知人たちが一人、またひとりと、落葉が散るように去っていく悲哀は、今まで味わったことのないものである。私は長い年月が過ぎ去ったことを実感し、住み慣れた土地が砂漠に変わっていくように感じられた。
出版ルートを持っていた昔馴染みの印刷会社にも電話してみたが、今はもう出版はやっていないということだった。最後に、私がレコード会社に勤めていたころの古い知り合いの柿沼さんに電話した。柿沼さんは大手出版社S社の芸能関係月刊誌の副編集長時代に独立して、相棒の三上さんと、ジャガー企画という芸能関係主体の編集プロダクションを立ち上げ、ジャガー出版という出版社も経営していた。
柿沼さんは、私がレコード会社でジャケット制作を担当していた頃随分とお世話になった。柿沼さんには出版社時代からの人脈があり、とにかく顔が広く、大抵の頼み事は引き受けてくれた。有名写真家競作でジャケット写真を撮ってもらうという企画では、破格の低価格で撮影を依頼してくれたりしたこともあった。豪放磊落な人柄で、恰幅がよく、度の強い眼鏡を掛け、やや薄くなった髪をオール・バックにし、色黒の将棋の駒を逆さにしたような顔立ちで、とにかく頼り甲斐のある人だった。いつもニコニコしていて、気風がよくメリハリのある喋り方は、東京の下町出身、いわゆる江戸っ子そのものの感じだった。
私は古い名刺ホルダーから、柿沼さんの名刺を引っ張り出し、そこに書いてあった彼の自宅に電話を掛けた。柿沼さんはすぐに電話に出た。
「やあ、しばらく」と、いつものやや皺枯れた懐かしい柿沼さんの声が電話口から聞こえてきた。それにしてもいつもの柿沼さんとは様子が違い、話し振りに元気がないのが気になった。
「お変わりありませんか?」と、私は尋ねた。
「実は去年、三上が亡くなって会社を閉めちゃったんですよ」と、彼は声を落としてそう言った。三上さんの病名はスキルス性の胃癌で、あっという間に亡くなったそうだ。長年二人三脚で仕事を続けてきた相棒を失い、気落ちしている様子が手に取るように伝わってきた。私は、三上さんのお悔やみを言い、あまり気を落とされないようにと付け加えた。それから、実はこう云う訳でと電話を掛けた経緯を話し、残念ですが諦めます、と言った。それから暫く、当時の関係者のことや世間話などをして、本が出来上がったら送りますと言って電話を切った。
8月になった。私は出版の当てがすべて外れて、Mに相談した。もちろん自費出版で、幾許かの予算を提示して、HPで発表したものを本にしてくれる出版社があるかどうか訊いてみた。Mは「当たってみるから、少々時間をくれ」、と言った。
一週間ほど経ってMから連絡があり、Kという料理専門の雑誌社のH専務が興味を示してくれ、その予算で大丈夫だと言うことだった。Mは連絡先を教えてくれて、連絡してみたらどうだ、と言った。Mに話を聞くと、彼の娘婿のHさんが大手印刷会社に勤めており、出版社にいろいろ当たってくれたということだ。
8月下旬、私はK社のH専務に電話してアポをとった。その頃連日の猛暑で、若い頃は夏の暑さはむしろ好きな方だったが、最近は、ことに一昨年軽い脳梗塞を患ってからは、暑いのが苦手になったが、そうも言っていられなかった。8月30日、私は京王沿線にあるH社に打ち合わせに行った。その際、過去に釣り雑誌に掲載された記事や写真を持参した。編集担当のKさん、Aさんが同席した。どの程度のページ数にするか、HPの中からどの短編を入れるかなどを打ち合わせた。HPに乗せたものをそのまま印刷するということで、編集の手間が省けるので、かなり経費の節減になる筈である。9月に入って、デザイナーのGさんが同席し、具体的な装丁のイメージについて話し合った。
その後、正式な契約を交わし、出版の話は順調に進み、11月30日に短編集「渓流幻想」が発売された。K社は、この手の自費出版はあまり経験が無いようで、逆にそれが幸いし、謂わば「ノリ」で仕事をして貰ったようなもので、低予算にも拘らず装丁を含め、私の期待以上のものに仕上がり、周囲からの評判も良かった。私は、お世話になった人や、友人、知人、フィッシング教室の生徒さんたちに出来上がった本を贈った。
今年に入って、遅くなったが、柿沼さんに本を贈る約束をしたのを思い出し、住所を確かめようと柿沼さんに電話した。ところが、電話には誰も出ない。呼び出し音を10回数えたところで電話を切った。平日の午後3時を回ったところなので、もしかしたら何処かへ出かけているのかと思った。それから、時間を変えて2、3日おきに電話を掛けてみた。電話はなかなか通じなかった。この前はすぐ通じたのに変だな、と思いながらその後も電話を掛け続けた。
半月ほど過ぎて、半ば諦めかけたとき、電話が通じ、「はい、柿沼です」と、若い女性の声が電話口から聞こえてきた。
「昔、V社でお世話になりました柳原と申しますが、柿沼淳一郎さんはご在宅でしょうか」。───少し間があって、
「あのー、父は十年ほど前に亡くなりましたが・・・・・・」
私は絶句して、なかなか次の言葉が出なかった。
「この前、三上さんが亡くなられたことはお聞きしたのですが・・・・・・」
「三上さんが亡くなられた1年後に父は亡くなりました。」
つい半年前に電話して話をしたことなど、とても口に出せななった。私は本が出来たので送ろうとしたことを伝えて、失礼を詫びて早々に電話を切り上げようとした。
「どうぞお体を大切にされて、長生きなさって下さい」と、娘さんはそういって電話を切った。
この前の電話は一体何だったんだろう!あの声は確かに柿沼さんだった。私は十年前に電話したことなど無かった。私は慄然として、座っていた椅子から暫く立ち上がれなかった。(2013/8/15)
©2016(無断で転載することを禁じます)
|