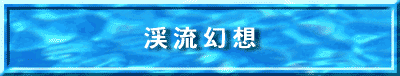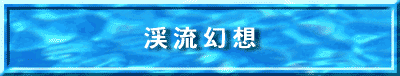|
柳原 釣童
一人山奥の渓流で釣りをしていると、時には不思議な出来事に出会うことがある。
今から三十年も前のことである。当時私はフライ・フィッシングを初めてまだ日が浅く、それまで持ち慣れた餌釣りの竿をフライ・ロッドに持ち替え、山奥深く分け入ってはヤマメやイワナを狙っていた。餌釣りで渓流釣りを始めた私は、落差のある障害物の多い渓流でフライ・ロッドを振ることに違和感はなく、ブッシュにフライを取られるのは、自分のキャスティング技術が未熟な所為だと思っていた。私は、自分がフライ・フィッシングに興味を持つようになった経緯を、ある雑誌に次のように書いた。
「私が初めてヤマメを釣ったのは確か大学に入学した年だから、今からもう40年以上も昔のことになる。釣った渓は奥多摩の日原川支流・小川谷だった。高校生の頃から多摩川や秋川で清流釣りをして、ヤマベ(オイカワ)やハヤ(ウグイ)を釣っていたので、初めて渓流に入っても、たった2尾とは言えヤマメを釣ることが出来たのだろう。
当時はまだフライ・フィッシングなどと言う釣りは世間一般には知られておらず、勿論私もその日は餌釣りをしていた。2枚の小さな、白い鳥の羽根の根元を結んで、双葉が開いたような形にした目印を、道糸の途中にゴム管で取り付け、魚の当たりを取っていた。
夕方になり辺りが暗くなってきた。切り立った両岸が狭まり、川幅一杯に流れる渓を、私は川通しで遡っていた。私は小さな淵の淵尻に立ち、淵の中央付近に投げ込んだ餌をゆっくりと下流(手前)に流していた。小さな目印が、白い蝶々のように、暗い水面上を僅かに上下しながら舞っていた。そのとき、突然水面がはじけて、白い魚体が目印めがけて真っ直ぐに飛び上がったのである。
予想もしなかった展開に、私は我を忘れてその光景を眺めていた。ヤマメはその後何回もその目印に飛びついてきた。その時、私はヤマメが夕方になると、翔んでいる昆虫を狙うものだということを初めて知って、目印に鉤をつけたらヤマメが釣れるのではないかと思ったのが、擬餌鉤について興味を持ったきっかけだった。」
私は、目印に鉤をつけて何回かトライしてみたが、餌釣りの竿で、0.6号ほどの細い道糸の先に、羽根の目印を結んで投げようとしても上手く投げられず、また、目印を水面上に、虫が翔ぶようにキープすることが難しく、この試みは失敗に終わった。
ある年の八月の末、私は関東有数の大河であるT川の源流に出かけた。I川はT川の源流の一つで、中流は非常な険谷として知られ、ザイルワークのできる複数のパーティーしか入渓できないといわれている。I川は中流を過ぎてI集落に近づくと、それまでの険しさが嘘のように穏やかな流れに変わり、何本かの支流に枝分かれする。I集落一帯は、狭いながらもなだらかな地形でI高原と呼ばれ、白樺、ブナ、ミズナラ、モミなどが生い茂り、どこか軽井沢の森を連想させた。
その日は風もなく、非常に暑かった。私は、I集落に通じる山道がI川の険谷部を通過して、カーブしながら急激に高度を上げてI集落に近づく、そのカーブの手前にある駐車スペースに車を停め、釣りの支度をした。I川の両岸は鬱蒼とした喬木に覆われ、午前十時だと言うのに日差しは地上に届かず、辺りは薄暗かった。道路脇の、熊笹が生い茂るじめじめした急な斜面を、釣り人のものと思われる踏み跡を辿って岸辺に降りて行った。
実は、私はI川に入渓するのは、このときが初めてだった。この辺りは、I川が数本の支流に枝分かれする少し下流で、落差はないが水量が多かった。両岸が切り立った河原のない谷底を、I川は10mほどの川幅いっぱいに流れていた。私は密生した笹を掻き分け、川岸にしゃがんで片足を流れの中に入れてみた。流れは意外に深く、膝近くまで水に浸かった。ウェスト・ハイのウエーダーを履いているので、足が濡れる心配はなかったが、途中に通らずでもあれば引き返さなくてはならず、果たして川通しで上流まで遡行できるか少々不安になった。
入渓してすぐに、I川は右にカーブした。私は左岸の岸壁に沿う流れの岸際ぎりぎりに、エルクヘアー・カディス#14をキャストし、1mほど流してみた。カーブが膨らんだ地点をフライがまさに通過しようとした瞬間、暗い水面に波紋が起きた。すかさず合わせると、24cmほどの幅広のヤマメが釣れた。それから50mほど遡っている間に、20cmクラスのヤマメが2尾ヒットし、I川が二本に枝分かれする手前で、今度は27cmのイワナが釣れた。この辺りはヤマメとイワナが混棲しているようだ。
川幅は今までの倍ほどに広がり、見上げると木々の間に青空が見えた。I川が左右に枝分かれする分岐点に着いた。私は事前に地図で調べていたので、大体この辺りの地理の見当がついた。右股のN川を進むと、先ほどの山道に近づき、なおも進むとNという小さな集落に出る。左股は、I川の本流で、2kmほど進むとI集落に達している。出合いこそ右股より川幅が狭く冴えない渓相の左股だが、水量は3:2の割合で右股より多い。私は躊躇うことなく左股を選んだ。
10分ほど遡行すると、I川は川幅が広がり、ゆったりと蛇行を繰り返すようになった。びっしりと熊笹に覆われた川岸は、遡行するに連れて、水面から高く離れたり、水面に近づいたりした。所々に河原も現われ、幾らか遡行が楽になった。I川を取り囲むように大きなブナや、ミズナラ、モミなどの森が広がっている。樹々は、間伐されたことない杉林のように密生してはいないが、それでも、大小さまざまな木の幹が重なり合って、森の奥まで見通すことはできなかった。ところどころ、木の葉の隙間から木洩れ日が差し込み、下草の笹が、スポットライトを浴びたように明るく浮かび上がって見えていた。聞こえてくるのは渓のせせらぎと、カッコウやオオルリなど野鳥の囀りだけである。前の年に釣りに行った、奥日光の湯川の風景にそっくりだと思った。
この辺りは、イワナの生息圏のようで、岸際から張り出した笹藪の下や、倒木周り、底石のある瀬などで、型は不揃いだが、ぽつぽつとイワナがヒットした。川底の砂は白く、釣れるイワナの体色も白っぽかった。私は、適当な河原を見つけ、倒木に腰掛けて昼食を摂った。
左股に入って2時間も経っただろうか、かなり深い淵に前進を阻まれた。河原はなく、完全に通らずになっていた。右岸はかなり高く、とても上がれそうになかったので、私は左岸の低い崖を上がり、通らずを巻くことにした。
左岸の岸際にはネコヤナギや、茨などの低木がびっしりと生い茂り、岸沿いを進むことはできなかった。足元に目をやると、熊笹の間に細い獣道のような微かな踏み跡があり、上流に向かっていた。私はその踏み跡を辿れば上流に出られそうな気がして、その踏み跡を辿った。その踏み跡は、緩い傾斜の熊笹の丘を登ったり下ったり、また、右に行ったり左に行ったりしながら延々と続いた。辺りは同じような景色が続き、私は完全に方向を見失ってしまった。
20分も歩いただろうか、かすかに水の音が聞こえ、ようやくI川の上流に出ることができた。私は釣りを再開したが、先ほどまでと打って変わって、魚の当たりは遠かった。上流は魚影が薄いのかなと思いながら遡行を続けた。時折、ナーバスな魚信があったが、食いが浅くほとんど鉤掛りしなかった。
1時間ほど過ぎて、また通らずに行き当たった。私は、再度左岸に上って、通らずを巻こうとした。僅かな昼食の休憩を除けば、ほとんど4時間歩きっぱなしで、それも、流れの中を歩くことが多くかなり疲れていたのか、川岸に上がるとき足が滑り、右手で掴んでいた猫柳の枝を折ってしまった。
先ほどと同じように熊笹の叢の中に踏み跡があり、私は、またその踏み跡を辿って歩いた。初めての渓で、どこを歩いているのか、また分からなくなったが、幸いI川の上流に出ることができた。私は頭の中で地図を思い浮かべ、あと30分も遡行すれば、I集落に出られる筈だと思った。魚影は益々薄くなり、私は早くI集落に出て、集落の上流を釣って見たいと思った。
30分経っても40分経っても、I集落は見えなかった。1時間ほど過ぎて、また通らずに突き当たった。似たような淵があるものだと思い、幾らか怪訝な感じがした。私は辺りを見回し、巻き道を探した。左岸が上がれそうだったので近づいて、ネコヤナギの枝を掴んで上がろうとした。そのとき、私は、低い崖に滑った足跡と、ネコヤナギの折れた枝を見つけた。
それは、先ほど、私が岸に上がろうとして滑った足跡と、私が折った枝に違いなかった。私は、あまりの不思議さに、ギョッとした。私は、三度も同じ場所を、ぐるぐる廻っていたことになる!私は言い知れぬ恐怖で背筋が寒くなった。
私は、左岸に上がることを止め、そのまま流れ引き返した。2時間近く川を下って、N川と、I川の分岐点に着いた。私はN川を遡って、漸くN集落に着くことができた。
辺りはとっぷりと日が暮れ、人家の明かりが、このときほど嬉しく感じられたことはなかった。(2003/9/10)
©2004(無断で転載することを禁じます)
|