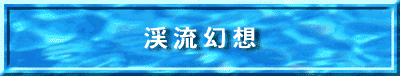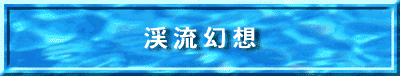|
柳原 釣童
画家とその弟
(これは、私の学生の時に書いた作品である。拙い作ではあるが、このままごみ箱に入れるのも忍びなく、学生時代を過ごした一つの証として、多少手を加えて発表するものである)
(一)
昭和三十年代初頭、低い丘陵が続く武蔵野台地がまだ雑木林や畑で覆われていた頃のことである。
出しぬけにバタバタと乱暴な足音が聞こえたかと思うと、ばたんとドアを開けて学生服を着た若い男が勢いよく部屋に入ってきた。「兄さん!」と叫んで、その男はそのままずかずかと壁際に置かれたベッドに腰をおろして鞄を置き、学生服を傍らに脱ぎ捨てた。額にはびっしょりと汗を掻き、ワイシャツの胸の辺りが汗で濡れていた。6月半ばの梅雨の晴れ間で、非常に暑い日だった上に、駅からかなりの距離を歩いて来た所為で大汗を掻いたのだろう。
板敷きのむさくるしい、十畳一間の南北に長い部屋には、傷だらけのテーブルと椅子、本箱、小さな箪笥、ベッドなどが雑然と置かれ、埃だらけの床は絵の具や油で汚れ、丸められたキャンバスや紙屑が散乱していた。部屋の入口側の片隅に薬缶の載った石油コンロがあり、ベッドの上の棚には、半分ほど残ったウイスキーの壜と縁の欠けた湯呑やコップが置かれていた。南に向いたこの部屋の奥にカーテンの閉まった半間ほどの窓があり、窓の横に自画像を描く為かこの部屋には不釣合いに大きな姿見が掛けられている。流し場や便所は廊下の奥に共同のものが設けられていた。この木造の細長い建物は、戦後引揚者用として使われたもので平屋で10室ほどある。その後全ての住人が立ち退いて廃屋同然になり、そのうち取り壊される予定であったが、画家はこの建物の持ち主を見つけて取り壊すまでと言う約束で借りているのである。
「おお、来たか、珍しいじゃないか」、暗い部屋の奥で、兄と呼ばれたランニング姿の男が左手にパレットを持ち、絵筆を握った右手をゆっくりと動かしながら、画架に立てかけた大きなキャンバスに向かったまま、振り返りもせずに答えた。
「廊下をガタガタ言わせていたので、きっとお前だろうと思っていたよ、いつもお前は元気でいいな」と、振り返って弟をちらりと見やり、弟の溌剌とした顔を確かめ、また画布を覗き込むように描き始めた。
「ガタガタは酷いな、でも兄さんも元気なんでしょう?」。弟はいくらか気勢をそがれながら尋ねた。
「見ての通りさ。だが、思うように描けないもんだな。でも、まあ飽きもせずにやっているよ」と、やや自嘲気味に答えた。やがて筆を置いて、首に巻いた手ぬぐいで顔の汗を拭き序に手に付いた絵の具をごしごし擦りながらゆっくりと弟に近寄り、屈んで弟の顔をじっと覗き込むように見た。見上げている弟の方は、歳は二十歳くらいで、まだ頬の肉が削げない子供っぽい容貌で、背格好も小柄でとても大学3年生には見えなかった。弟を見下ろしている兄の方は180cmを優に超える大男だった。歳は弟より一回りも上だろうか。髪の毛は伸び放題で暫く剃刀を当てていないらしく無精髯が伸びていた。表情は全体的に生気がなく、憔悴しきった印象で、時折放心したように視点が定まらなくなった。弟は兄の顔を見上げ思わずぎょっとして危うく声を立てそうになった。頬はげっそりこけて眼ばかりが異様に光り、鬼気迫る感じだった。何と言う窶れ様だろう、昔の快活なあの兄の姿は何処にもない。何かに取り付かれたような目つきで、酷く苦しんでいるんだな、可哀想な兄さん、と彼は心の中で呟いた。
「何だい?妙な顔して。俺の顔にまだ何か付いているかい?」
画家は弟の気持が分かっているくせに、妙に意地の悪い口の利き方で弟に尋ねた。画家の表情に一瞬暗い笑いが浮かんだが、すぐに真顔に戻って、探るようにじっと弟の顔をみた
「い、いいえ、でも何でそんなに怒ったような顔をして僕を見るんです?」と、慌てて答え、そしていくらか不安そうに兄を見上げた。
「別に怒ってやしないさ、だがな、何故か近頃イライラしてな・・・・、あまり眠れん所為だろう。ま、そうびくびくするな」と言って、急に大きな声で笑い出した。弟は兄の笑い顔を見てホッとして微笑んだ。
「どうだ、酒でも飲むか?ちょうど美味いのがあるぞ」と、画家はことさら陽気そうに言い、ベッドの上の棚に手を伸ばしかけた。
「昼間からとても飲めませんよ」、弟は慌てて遮った。
「そうか」、兄は苦笑しながら伸ばしかけた手を引っ込め、弟の横に腰掛けて母親のことなど家の様子を訊ねた。弟は傍らの鞄の中から、一通の封筒を取り出し黙って兄に差し出した。それは母親から兄に宛てた手紙で、簡単なメモのような手紙の他、乏しい家計を遣り繰りして溜めた小遣いが入っていた。
「いつも済まんな。お袋に宜しく言っといてくれ」
弟は、兄と話しているうちに、堪らないほど侘びしい気持ちになっていた。つい数年前まで陽気で、時には気障とも感じられほど颯爽としていたあの兄の面影は、いまやすっかり影を潜めてしまっていた。美大に入学した頃の兄は、クラスでも飛びぬけた才能を発揮して、将来を嘱望されていた。あの頃の自信たっぷりで、唯我独尊風の得意そうな兄の姿はもう何処にもない。
弟は、昔田舎に住んでいた頃のことを思い出していた。弟は小さい頃から兄が大好きであったし、歳の離れた兄に畏敬の念を抱いていた。幼かった自分をよく近くの川へ魚釣りや泳ぎに連れて行ってくれたあの兄と、今の兄が果たして同一人物であるかすら疑わしく思えるのである。ここ数年の間にどうした訳か、急に自分の才能に自信を無くして、焦燥と絶望のうちにすっかり精神的にも肉体的にも参ってしまっているように見える。
お前このごろ勉強しているか?怠けちゃ駄目だぞ・・・・。歩みを止めるともう駄目だ、自分と一緒に歩いてきた才能が離れて行ってしまい置いてけぼりを食っちまう、そうなるともう追いつけない。逃げられてしまうんだ」、画家はうめくように呟いた。それは、まるで自分を責めているように聞こえた。弟は黙っていた。彼は兄の苦悶を察知していた、そして才能に絶望した者を慰める言葉のないこともよく解っていた。───兄さんの苦しみは、たとえ兄弟だって慰められないのです。と、心の中で呟きながら、兄と二人きりでいるのが耐えられないほど辛くなってきた。
「新しい詩が出来たか?あったら朗読してくれないか」、兄は弟に訊ねた。弟は文学部に在籍していて詩を書いていた。
「ええ、少し古い作品ですけど」と、この苦しい雰囲気から何とか逃れたいと思っていた弟は、鞄の中から詩作ノートを取り出して読み上げ始めた。
兄は黙って聞いていたが、
「寂しい絵だ、しかし美しい絵だ。いい詩ができたな。特に<・・・・悲しい時に 太陽は要らない・・・・>と言うフレーズはいいね」と、作品を褒めた。
「どうも有り難う、兄さん」、弟は心から嬉しそうに言った。「そうだ、窓を開けましょう」。弟は明るい声で立ち上がって、カーテンと窓を開け放ち、画架の前を横切ってベッドに戻ろうとすると、突然、
「お前、この画をどう思う?」。画家が弟に声をかけた。振り向くと兄が冷たい眼で、弟の顔を見据えていた。
弟はぎくりと歩みを止め、表情を強張らせ口篭った。冷水を浴びたようにスーと血の気が引いた。
「ええ、でも僕には画のことがあまり解らないので・・・・」。
弟は、兄のこの質問を恐れていた。何も喋りたくはなかった。仮令嘘をついても兄にはすぐ分かってしまうだろうし、本当のことは尚更言い難かった。画の出来は、贔屓目に見ても褒められるものではなかった。しかし、そのことは決して口に出せなかった。イライラして尖っている兄の神経を逆撫でしたくない。
「お前に画が解らないなんてことあるもんか!そりゃこの画の出来はよくない。それくらい自分でもよく分かっている。そればかりではない、最近の作でましなものは一つもない。だがそんなことはどうでもいい」。兄は次第に昂ぶる気持を抑えきれなくなった。
「妙な遠慮は止せ、この画をどう思っているのかはっきり言え!」。画家の目は血走り、顔面は蒼白になり、ゆがんだ頬の筋肉が痙攣した。
弟も真っ青になって画架を前に、終に来るべき時が来たと思い立ち竦んでいたが、思い切って口を開いた。
「正直に言いますが、昔兄さんが学生時代に展覧会に入選した絵を見せてくれましたね。そのときの画と比べて、迫力がないと思います。」
画家は激怒の発作を危うく抑えて、ベッドに腰を落とし、髪を掻き毟りながら、低いうめくような声で語り始めた。
「俺はな、お前が俺の画を見ないようにしているのが分かっていた。わざと画から目を逸らしているのを何度も見てきた。俺に画のことを何か聞かれやしないかとびくびくしているのもよく分かっていた」。画家はここで次の言葉を口にするのを瞬時躊躇った。
画家は再び喋り始めた。
「俺には画家としての才能が全くないのだ。今じゃ全てを失ってしまった」。画家はいくらか落ち着きを取り戻した。
「画と言うものはな、自然、いや世界と言っても良い、その真実をキャンバスに写し取るものなのだ。これは、広漠とした自然の多様性の一面を如何に捉えるかと言うことだ。自然はな、人間のどんな繊細で微妙な感性にも応じられる底知れない深さと奥行きと広がりを持っている。自然を捉えると言うことは、一口で言えばその人独自の様式に従って自然を統一することなのだ。」と、ここで画家は一息ついた。そして、猶一層苦しそうに語り始めた。
「様式、これが全てだと俺は思っていた。ゴッホのうねるようなタッチと強烈な色彩、ルノワールの肉感的な量感、マチス、ルオー、シャガール、全てその画家独自の様式、表現技法を持っている・・・・。俺は自分独自の表現技法を持とうと必死になった。原始美術、精神病者の画やアウトサイダー・アート、何でも良いからヒントを得ようと手当たり次第試してみた。その挙げ句、俺の画はただ目新しいだけ、奇を衒っただけの無意味なものになってしまった。デッサンさえも疎かにしてしまった。・・・・・俺は様式に拘り過ぎた。様式なんてものは、所詮その画家の持って生まれた感性から生まれるもので、真似することも、無理やり作り上げることも到底出来ないものなのだ。俺は独自の道を歩いているつもりだった。全くいい気なものだ。それは只道を踏み外していただけだ。」
「そんなとき俺は、ミレーやフェルメールの画を見たんだ。この画家たちは、特別に変わった表現方法をとっているわけではない。ミケランジェロや、ダヴィンチだってそうだ。ごく正統的な技法で、奇を衒ったところなど何処にも見られない。表現方法ではなく、その中身が大切なんだ。如何に対象に命を吹き込めるかが全てなんだ、と俺は気がついた」。
暫く沈黙の時間があった。画家は再び語り始めた。
「俺は振り出しに戻って、また一からやり直そうとした。だが駄目だ・・・・。何もかも狂っちまった。もう引き返せないんだ」
画家は再び気持を昂ぶらせ、
「お前は、こんな俺を馬鹿にしているんだろう!俺を一人にしてくれ、帰ってくれ!」と、叫んだ。弟は悄然と部屋から出て行った。
(二)
数時間が過ぎた。日は沈み、灯のない室内は深い闇に包まれていた。なだらかな低い丘の上に立っているこの建物の周辺には、野菜畑が広がるばかりで人家は1軒もない。辺りは静まり返り、半月の月明かりが雲間から洩れてくるばかりである。画家はベッドに寝転がったまま、ぼんやりと天井を見上げていた。画家は暗澹たる絶望に襲われていた。何の咎もない弟に、やり場のない怒りをぶつけてしまったことが悔やまれた。「何故、俺は画家になんかなったのだろう」、画家は長い絶望的な努力の日々を思い起こしていた。
「一枚でよかった、たった一枚でも良い、満足のいく画が描きたかった」と、画家は呟いた。
憶い出は遠い昔に遡っていった。悔恨はほのかに甘い郷愁に変わり、気分はそれほど暗澹たるものではなくなっていた。追憶がもたらす淡い安らぎであろう。
あるとき、幼い弟を連れて山に登った。大きな樹が何本も生えているところで、その中の一本に姿を隠すと、弟は泣きべそをかいたものだ。あの心細そうな弟の顔を思い出した。「ばあっ」と言って顔を出すと弟は一気にわっと泣き出し、宥めるのに苦労したものだ。「俺はあんな可愛い弟になんて酷いことを言ってしまったのだろう」、画家は激しい後悔の念に苛まれた。
憶い出は現在の自分に近づくに連れて苦いものに変わっていった。彼はサラリーマンの家に弟より10年以上早く生まれた。父親の転勤で、西日本の各地を転々と移り住んだ。父親は、長男を教師か、公務員にしたかった。長男が画家になりたいと言った時、猛烈に反対した。せめて高校の美術の教師になってくれればと考えたが、彼に全くその気がないことを知って、もう何も言わなくなり、家を飛び出した彼を一切相手にしなくなった。
それ以来、母は父に気兼ねして、大っぴらに兄に会ったことは一度もなかったが、定期的に細々した日用品だとか、小遣いなどを弟に託して兄に届けさせていた。そんな訳で画家は家族とは殆んど交渉がなかったが、唯一弟だけが足繁く兄を訪ねてきていたのである。弟は兄を愛し、尊敬し、理解していた。
月の光が室内に射し込んできた。室内は月光に淡く照らし出された。
画学生の頃から既に8年余りもこの不潔な長屋に住んでいた。彼は実家からの仕送りも受けずいろんな雑役をしながら生活してきた。農家の収穫を手伝うのにもなれた。生活は苦しかった。しかし生活苦は彼にとってさほど苦痛ではなかった。彼を苦しめたのは自己嫌悪、焦燥、絶望と言った精神的なものであった。
一体俺は何のために画を描くのか?どれだけ頑張って、齷齪してみたところで、ましな画は描けそうにない。いっそ、筆を折るか?それは出来ない。画を描くこと以外考えたこともなかったし、今更他の道を選べといわれても、それは到底無理だ。なら、どうする?
この問題に彼は触れないように、考えないようにしてきた。だが、今日ばかりは、この問題から到底逃れられそうもないことを、ひしひしと感じていた。
「そうだ、俺は何のために生きているのだ。俺は何故生き続けねばならないのだ。今の俺にとって、生き続けるより寄り死ぬほうがよほど楽だ」。
画家はベッドから起き上がり、腕を伸ばして電灯をつけた。赤っぽい侘びしい光が室内を照らし、画家の影を壁に映した。青ざめた画家の表情には、もう何処にも苦悶の跡は残っていなかった。
画家は再びベッドに腰をおろし、棚においてあるウイスキーの壜を取り出した。棚の奥から取り出した小壜を手に持ち、じっとそれを凝視していた。小壜には農薬が入っていた。農薬は画家が農家で畑仕事の手伝いをしたとき、こっそり小壜に移して替えて持ち帰ったものである。彼は、小壜の農薬をウイスキーの壜に1ccほど入れ、絵筆の柄でかき混ぜた。彼はウイスキーの壜と農薬入りの小壜を元の棚に戻した。
画家は、今取り掛かっている自画像に最後の挑戦をし、どうしても満足なものが描けなければ、そのときは、農薬入りのウイスキーを飲もうと心に決めたのである。たった1枚でも良い、自分の満足する画を書きたい。それだけが画家の最期の望みだった。
画家は画筆を手に持って画架の前に立ち、机の上においてあったパレットの絵の具を混ぜ合わせ、描きかけていた自画像の上に勢いよく絵の具を塗り重ね始めた。「せめてこの画だけでも」。
画家は熱中した。久しく感じなかったあの感覚が甦ってきた。天啓と言おうか、閃きと言おうか、あの身震いするようなインスピレーションが帰ってきたのだと、画家は感じた。久しぶりに、何もかも忘れて画を描くのに何時間も没頭した。
自画像は、アントナン・アルトーのものをもっと醜悪にした感じで、それは懊悩、絶望、憤怒、悔恨、その他ありとあらゆる感情が凝縮された作であった。その画には確かに生命が吹き込まれていた。「これが俺が求めていたものだ」。画家はなおも熱中して描き続けた。
深夜、画家の部屋の前に佇む弟の姿があった。弟は兄と別れた後、兄がもしかすると自殺するのではないかと心配になった。家に帰る途中、どうしても兄のことが気になって引き返してきたのである。弟は部屋からもれてくる明かりを見て、兄がまだ起きていると思い、何故かホッとした。おずおずと部屋の中に入ったが画家は全く気づかなかった。
弟は画家の背後からそっと近づき、描きかけの画を覗き込んだ。その瞬間、弟は胸に突き刺さるような衝撃を受けた。その画の持つ異常なまでの凄惨さに打ちのめされた。
「凄いね、兄さん!」と、弟は、思わず大声を上げてしまった。
画に没頭していた画家は不意を突かれて、ぎくりと肩を震わせた。
「何だ、お前か。来てたのか」と、振り返った画家は呟いた。
「凄いね、傑作だね!」、弟は、久しぶりに見る兄の新鮮で、鬼気迫るような出来栄えの画に見入っていた。
「お世辞は止せ」、画家はそれでも内心嬉しかった。弟がお世辞など言えない性格だと言うことをよく知っていたからだ。
「お世辞じゃないよ・・・・」、弟が続けて何か言いかけようとするのを制して、
「もう少しで終わるから、少し座って静かにしていてくれ」と言って、画家は最後の仕上げに取り掛かった。何もかも忘れて、仕上げに没頭した。
……………………………………
「うう・・・・・苦しい、・・・・・兄さん助けて、……」。
低い呻き声が聞こえて来た。その声は、夢の中で呼びかけられたときのように遠くから聴こえてきた。「兄さん助けてか・・・・・」と、画家は無意識に繰り返していたが、はっと我に返って飛び上がった。
弟は椅子から転げ落ち、口から大量の血を吐き、呻き声を上げながら床の上を転げまわり、床板を掻き毟っていた。床の上にはコップが転がっていた。画家は何が起きたのか一瞬のうちに悟った。弟は画が仕上がるのを待つ間に、棚からウイスキーの壜を取り出し、農薬入りのウイスキーを飲んでしまったのだ。
画家は弟のところへ駆け寄り、抱きかかえて薬を吐き出させようと、口の中に指を突っ込んだ。その瞬間ガリッと鈍い音がして、画家の腕から脳天にかけて金串を突き刺されたような激痛が走った。画家は反射的に手を引いたが、人差し指と中指の第一関節から先が食い千切られ、見る見る鮮血が噴き出してきた。弟はがっくりと頭を垂れ、兄の腕の中で息絶えた。
翌日、弟が帰宅しなかったのを心配した母親が、兄の部屋を訪ねてきた。部屋の床に血を吐いて倒れている弟と、ずたずたに引き裂かれたキャンバスの上で、口と指先から血を流した兄の、二人の息子の亡骸を見つけたのである。(完)(‘64/4/18)
©2010(無断で転載することを禁じます)
|