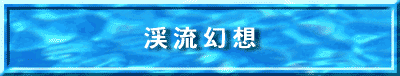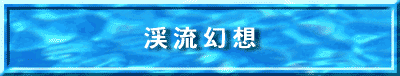|
柳原 釣童
1977年8月
1977年の8月7日、会社の夏休みを目一杯使い、一週間の予定で北海道に釣りに来て、いよいよ明日東京に帰るという日のことである。その日、小宮山敬三は北海道在住の釣友のKとOと三人で尻別川の源流で釣りをしていた。敬三とKは、数年前富士山麓の忍野で知り合い、それ以来交友が続いているのだが、OはKの気の置けない釣友である。
朝から願ってもないような好天で、北海道に来てから初めて満足のいく釣果を得ていた。ところが、昼を過ぎた頃から、足元が揺れるのである。最初、気のせいかと思ったが、1時間ほどの間隔でまた大地がぐらぐらと揺れた。今度は間違いなく地震であり、それも震度三から震度四クラスの強さであるとはっきり分かった。揺れは僅か数秒で終わり、通常の地震とは明らかに異なっていた。KとOも驚いていたが、差しあたって周囲の山が崩れたり、地割れが起きるといった被害もないようなのでそのまま釣りを続行した。敬三も一週間目にやっと巡り合ったチャンスとあって、釣りを止めようなどという気はさらさらなかった。魚はエゾイワナであるが、大地が揺れても少しも影響を受けないらしく相変わらず釣れ続いた。その間、地震の間隔が少しずつ狭まってきているような気がしたが、揺れの強さはまるで起震車が地震の実験をしているように均一で変化がなかった。
敬三が滞在していたのは、洞爺湖温泉の外れにあるKの父親の別荘である。温泉付きの、元はどこかの会社の保養施設だったらしく、二階建で、部屋数が多かった。敬三は8月1日から友人達の案内で、道南の各地の河川を釣り歩いていた。幾ら魚影の濃い北海道とはいえ、8月の渓流釣りは厳しかった。北海道のヤマメは、雌はすべて海に降ってしまい、残っているのは雄だけである。その雄も、水温の低い上流や支流に散ってしまうので、なかなか釣果が上がらない。
最終日に、エゾイワナを狙うことにして尻別川の源流に来たのだが、これが大当たりだった。当時、北海道ではエゾイワナはまるで外道扱いで、釣る人が殆んどいなかったので魚影はすこぶる濃かった。日が翳ると、Kが急にそわそわし始めた。この辺りはヒグマが出没するので暗くなると危険だという。敬三もヒグマの怖さは二人から散々聞かされていたので即座に引き上げることにした。
夕刻洞爺湖畔に戻り、喫茶店でその日の釣果を語り合っていると、またぐらぐらと来た。今度は昼間の揺れより少し大きい感じがした。震源が近いのかも知れない。喫茶店の主人の話によると、昼間からずっとこの調子だという。30分ほどしてまた揺れた。地震の間隔は、明らかに短くなっていた。喫茶店の主人も、友人達もこんなことは初めてだという。彼等は、何かとてつもないことが起きるような気がして得体の知れない不安を感じた。ごく狭い地域の出来事の所為なのか、どこからもこの異変についての情報はなかった。近くの食堂で早々に夕食を済ませ、敬三とKはOと分かれてKの別荘に戻った。敬三は、明日の帰京の支度をして床についた。
床についたものの、地震の間隔は20分から10分とどんどん短くなり、敬三は一晩中まんじりともできなかった。明け方近くになって、5分間隔で揺れていた地震がぴたりと収まった。やれやれやっと終わったかと安堵し、それから少し眠った。うつらうつらしていると家の外が何やら騒々しい。目を開けると、カーテンに朝日が当たっていた。咄嗟に時計を見ると7時を少し回っている。周囲はますます騒がしくなり、中には叫び声や悲鳴のような声も混じっていた。敬三と隣で寝ていたKは慌てて着替えて家の外に出た。
大勢の人が家の外に飛び出して南の空を見上げていた。敬三は有珠山の方角に巨大な黒い噴煙が立ち昇っているのを見た。もくもくとすごい勢いである。まるで黒い入道雲だなと思った。奇妙なことに噴煙からは全く音が聞こえてこない。不思議な静けさが漂っていた。昨日の地震は、所謂火山性微動だと気付いたが、「微動」というにはあまりに大きな揺れであった。
敬三が見ている間に、ますます噴煙は高く立ち昇っていく。黒い噴煙の中で火花が散り、時折稲妻が走るのが見えた。その時、敬三の錯覚かも知れなかったが、噴煙の中に大きな凄まじい形相の鬼の顔が見えた。噴煙がさまざまに動き形を変えるうちに、偶々そんな風に見えただけのことかも知れない。一瞬のことで、その顔はすぐに消えてしまったが、敬三にはその顔に、確かに見覚えがあった。その記憶を呼び覚ます暇もなく、Kに促されて敬三は慌しく帰り支度を整え、Kの車でJR虻田駅(現在の洞爺湖駅)まで送ってもらった。
敬三は室蘭本線の急行に乗り、千歳空港駅に向かった。室蘭に行く途中列車の外は降灰で真っ暗になり、車窓から見える車は皆ヘッドライトを点けてのろのろと走っていた。電灯が灯った車内に、どこからか細かい火山灰が入ってきて周囲が霞んでしまった。昔SLで旅行した時、トンネルの中が煤煙で煙ったときのようであったが、石炭の臭いはしなかった。定員の半数くらいの乗客はいずれも不安そうに列車の窓から外を眺めていた。
千歳空港に着くと、場内アナウンスで有珠山の噴火で航空機の運行が乱れていることが告げられていた。待合室のテレビの前には大勢の人だかりができて、ニュースの画面に見入っていた。火山灰で飛行機のフロント・ガラスに罅が入ったというようなニュースを、人々は不安げな面持ちで聞いていた。
予定の時刻よりだいぶ遅れたが、何とか予約していた飛行機に搭乗することができ、敬三はホッと一息ついた。機内アナウンスで、噴煙を避けて迂回する旨が告げられた。敬三は、有珠山の噴火で友人達はどうなってしまうのだろうと心配になった。敬三の脳裏に先ほどの鬼の顔が甦ってきた。どこで見たのだろう、敬三は懸命に記憶を遡った。そして、中学2年に上がる前の春休みに、桜島に登った時のことを思い出した。
1954年3月
数十年も昔のことなので細部についてはよく思い出せないが、敬三が中学1年の春休みに、仲のよかった同級生Nと一緒に桜島に登ったときのことである。敬三はある官庁に勤めていた父親の転勤に伴い小学六年の時福岡から鹿児島の小学校に転校してきた。中学時代を1年間過ごし、中学生活にも慣れ数少ないが友達もでき、その中でもNとは特に気があってよく一緒に近くの甲突川へフナ釣りに出かけたりしていたが、3月のある日、Nから桜島へ登ろうと誘われた。敬三は二人だけで登山するのは少々不安だったが、Nは何度も桜島に登ったことがあるらしく自信ありげに強く誘うので断りきれなかった。
鹿児島港から桜島港(袴腰)まで連絡船で渡り、その後登山口までバスに乗って行ったように記憶しているが定かではない。登山口から頂上まで3、4時間かかったような気がする。途中、道端に少し雪が残っていたのが珍しかったのではっきりと覚えているが、辛かったという記憶はないので、それほどきつい登山ではなかったのだろう。
山頂に着いたが、そこは砂と小石ばかりの、まるで起伏に富んだ砂漠のようだった。野球場のように広い平らな砂原が遠くに見え、手前に深さ30メートル、直径100メートルはあろうかという、巨大な擂鉢状の深い穴が開いていた。今思えばそれはクレーターのひとつだったと思われる。二人は、クレーターの壁の上でおにぎりを食べたり、水を飲んだりして一休みした。
Nがクレーターの底へ降りてみようと言い出した。覗いてみると、底は砂と小石で半ば埋まって平らになっていた。クレーターの縁から底まではかなり急な傾斜になっていたが、降りるのはそれほど難しくなさそうだった。Nはもう斜面を走り降りていた。身体の重心をやや後ろに傾けてバランスをとりながら、踵を交互に斜面に突き立てるようにして器用に降りて行った。敬三も続いて降りていったが、途中何度か尻餅をついたり滑ったりした。
噴火口の底は、特別に熱いとか、煙が出ていたりすることもなく、ただの砂地だった。暫く歩き回っていたが、すぐに飽きて戻ろうということになった。Nは手馴れた様子で急斜面を四つん這いで登っていったが、敬三は苦戦を強いられた。腕を伸ばして斜面に指を立てようとすると指先から砂が崩れてきて、蟻地獄に落ちた蟻のように けば けば くほどずるずると下がってしまうのである。Nはもう疾うに斜面を登りきって敬三を見下ろしていた。漸く斜面の中ほどまで登ったとき、敬三は誰かに足首を掴まれ、引っ張られたような気がした。敬三はぎょっとして足元を見下ろした。 くほどずるずると下がってしまうのである。Nはもう疾うに斜面を登りきって敬三を見下ろしていた。漸く斜面の中ほどまで登ったとき、敬三は誰かに足首を掴まれ、引っ張られたような気がした。敬三はぎょっとして足元を見下ろした。
蟻地獄の底から地獄の主が姿を現したように、砂の中から凄まじい形相の鬼が上半身を現し、その両手が伸びて敬三の足首をむんずと掴んでいるではないか!敬三は鬼の手を振り払おうと、必死になって足ばたばた動かした。敬三は心の中で思わず「神様、助けて」と叫んだ。暫く いているとふっと足が軽くなった。振り返ると鬼は消えていた。その後はもう無我夢中で噴火口を攀じ登った。 いているとふっと足が軽くなった。振り返ると鬼は消えていた。その後はもう無我夢中で噴火口を攀じ登った。
真っ青になって頂上に着いた敬三を見て、Nは「何をばたばたしていたんだ」と笑った。Nには鬼の姿が見えなかったらしい。敬三は、夢でもみたのかと思った。或いは自分が作り出した幻像だったのか。どうやら自分だけにしか見えなかったらしいと覚り、Nには鬼の話はしなかった。敬三は、鬼に掴まれた足首に痛みを感じた。Nに気付かれないように、そっと自分の足首を見た。足首には、くっきりと赤い手の跡が残っていた。
それから、どうやって家に戻ったのか敬三ははっきりとは覚えていない。あれは、現実だったのか、幻を見たのかよく理解できないでいた。鬼だったのか、火の神だったのか。
桜島は、近くに高い建物さえなければ、鹿児島市内ならどこからでも見えた。敬三は桜島のことが気になって、いつも見ていた。最初は小さかった噴煙が、徐々に大きくなっていくのが敬三には分かった。桜島が噴火するような気がして、そのことを友達とか周りの大人達に話したが、誰も信じてはくれなかった。
その年の12月、敬三は東京の中学校に転校した。次の年桜島が噴火して、死者が出たとラジオや新聞が報じた。地元でも桜島の噴火を予想した者は誰もいなかったようである。敬三は自分の予測が当たったと思った。1955年10月のことである。
1979年10月
敬三は都立有数の進学校に進んだ。小学校、中学校を通じて敬三の成績は常にトップクラスだった。敬三の母親は、ノン・キャリアの夫に不満を持ち、敬三にはキャリアになり、できれば大蔵省の高級官僚になることを望んでいた。T大学の法学部の受験に2度失敗し、敬三は生涯で初めての挫折を味わった。そのころには、母親も息子をキャリアにする夢を諦めていた。敬三は、当時産業界でもてはやされていた心理学科を選び、T大の文学部に入学した。特別に心理学が好きだったわけではない、就職に有利だというのが最大の理由だった。心理学を学ぶ者が人の気持がよく分かるとは限らない。むしろその逆で、人の気持が分からないから心理学を学ぶのだといった方がいいかも知れない。本当に人の気持が解るのはソポクレスやシェークスピアのような優れた芸術家だけである。
法学部に進めなかったことは、敬三には大きなトラウマとなった。その後大手の電機メーカーの人事部に就職して、順調に昇進していったが、周りの人間には冷たい人間だと見られ、時として法学部を落ちたコンプレックスが、法学部卒の上司に対して卑屈にさせたり、その反動で私学卒の人間に対して尊大になったりしたので評判は芳しくなかった。終に敬三は本社の中枢には残れなかった。要するに敬して遠ざけられたのである。
敬三は学生時代友人に誘われ釣りを始めた。最初は、多摩川でオイカワを釣ったりしていたが、そのうちに本格的に渓流釣りを始めるようになった。釣りをしているときだけが敬三の心が開放される時間だった。一人でフライ・フィッシングを始め、段々上達して度々忍野(山梨県・相模川源流)にも通った。忍野でKを始め何人も釣り仲間ができた。趣味の友達というのは、何の利害関係もないので、そんなとき敬三は小学生のように無邪気になれた。しかし会社では趣味の話は一切しなかった。趣味に溺れていると見られると出世に障ると思ったからである。趣味以外でも、会社の人間に対しては、自分の個人情報はできるだけ知られることを避けていた。
1979年の夏、敬三は長野県御嶽山直下の王滝川に出かけた。敬三にはもう一つ甲虫の採集という趣味があった。近頃では釣りの方が忙しく昆虫採集の熱は冷めていたのだが、我が国最大のヒゲナガカミキリを捕まえたくて木曽の御嶽山に出かけたのである。昼間は王滝川でアマゴを釣り、夕方営林署の土場でヒゲナガカミキリを採集した。季節の所為か、♂しか見つからなかった。
木曽から帰って2ヶ月ほど過ぎた1979年の10月、御嶽山が有史以来初めて噴火したことを知った。敬三は自分の行く先々で火山が噴火するので不気味な感じを抱いた。さすがに敬三も自分と火山との関係を思わずにはいられなかった。そう言えば、大島や三宅島も敬三が島を訪れた直後に噴火したことを思い出した。
1984年の9月13日の夜、敬三は火山と自分が関係があるなど自分の思い過ごしに過ぎないと自分の考えを一笑に付し、休暇を取って王滝川に出かけた。王滝川の流域で好釣というニュースが流れ、居ても立ってもいられなくなったのである。翌14日は朝から小雨が降っていた。朝の7時頃、敬三は王滝川の支流・大又川に掛かる橋の袂に車を置いて入渓した。雨模様の絶好のコンディションで、大型のアマゴやイワナがよくヒットした。
2時間近く釣り上がって敬三が一息ついていたとき、突然どーんと地面が突き上げられた。河原の浮石があちこちで生き物のように跳ね上がった。左右の崖の立ち木は倒れ、大きな石がもんどりうって転がり落ちてくる。敬三が逃げる暇もなく、沢の上流からどす黒い大量の土石流が激しい音を立てて襲ってきた。御嶽山の火山灰を含んだ土石流の中に、敬三は恐ろしい形相をした火の神を見た。転石の一つが敬三の頭を直撃したのと同時に敬三は土砂に巻き込まれ、その姿はすぐに見えなくなった。橋の袂に止めてあった車も、大量の土砂に流されてしまった。
敬三の行方は杳として知れなかった。地元では、行方不明になった釣り人が何人かいると噂された。
なお、この地震は後に「長野県西部地震」と名づけられた。(2008/3/20)
©2008(無断で転載することを禁じます)
|