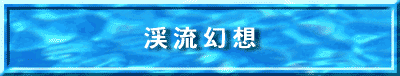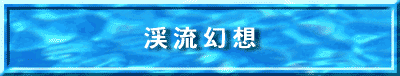|
柳原 釣童
人には、どう考えても理解できないような、不思議な出来事に遭った記憶が、一つや二つあると思う。これからお話するのは、私が体験した不思議の一つである。
今から三十五年も前のことである。当時私は、あるレコード会社で、邦楽レコードのジャケット制作の仕事をしていた。邦楽といっても今の人にはよく分からないと思うが、いわゆる歌謡曲、演歌などの流行歌である。現在は、J-POPが全盛であるが、当時は流行歌が全盛だった。
ジャケット制作といっても、実際に自分でデザインをするのではなく、出来上がった曲を試聴して、その曲に合ったジャケットのイメージを考え、カメラマンに歌手の写真を撮らせ、デザイナーにデザインを発注するアート・ディレクターの仕事である。当時レコード会社には、音楽制作のディレクターがいて、会社専属の作詞家と作曲家に作曲を依頼し、専属の歌手にその曲を歌わせ、自社のスタジオでレコーディングするケースが殆どだった。
当時のレコード会社の力は絶大で、まさにレコード会社全盛の時代であった。従って、私のような駆け出しの編集者(当時ジャケットの制作を編集と呼ぶことが多かった)でも、ジャケットのデザインを自由に考え(勿論、音楽制作のディレクターと打ち合わせするが、あまり細かな注文を出されることは無く、殆ど任せてくれた)、作ることができたのである。
その後、Wプロが、自社所属の歌手に、自社が著作権を持つ楽曲を歌わせ、レコードを自主制作したのを皮切りに、いわゆる原盤権を持ったプロダクション、制作会社が増え、レコード会社から制作の機能を徐々に奪い取っていった。その結果、レコード会社は、ただのレコード製造(プレス)と、レコード販売(ディストリビュート)の会社に成り下がり、音楽ディレクターは、制作するのが仕事ではなくなり、持ち込まれた原盤を選ぶセレクターの仕事がメインになるのである。セレクターの仕事でもできれば良い方で、どこのレコード会社に、どの歌手(アーティスト)、どの原盤を預けるかということまで、大抵は制作会社が決めてしまうようになるのである。現在は、レコード(CD)ジャケットのデザインも、プロモーションや宣伝計画に関しても大抵は制作プロダクションが作ってしまうので、レコード会社がジャケットのデザインを考える余地は、殆ど無くなってしまっているようである。
当時私は、レコード会社に途中入社して2〜3年経ったばかりの駆け出しであった。レコード会社に入る前は、ホテルや旅館のパンフレットなどを印刷する、小さな印刷会社に勤めていたが、そこの上司と喧嘩して飛び出して、新聞でレコード会社の求人広告を見て応募したのである。「文芸部のレコードジャケット編集者」ということで、最初から配属先は決まっていたのであるが、私は、学生時代からクラシック音楽が好きで、クラシックの仕事ができればいい、と言う気持ちだった。
いざ入社して面食らったのは、自分の担当が、それまで殆ど接することの無かった流行歌のジャケットだけを作る仕事であったことだった。私は、生まれてこの方、NHKの紅白歌合戦すら一度も見たことが無いような、堅い、或いは、いささか偏った家庭で育った。父親が無類のクラシック好きで、母親も若い頃シャリアピンを実際に聴きに行ったことがあるような女性で、その上、兄が声楽家というように、流行歌とは殆ど無縁な家庭だった。それが、いきなり流行歌の元締めのような仕事に関わることになったのである。当時、私が歌える歌といえば、子供の頃口ずさんだ、「異国の丘」、「お富さん」、「上海帰りのリル」や、高校生のときに流行った「有楽町で逢いましょう」くらいのものであった。
しかし、クリエイティブな仕事はというのは、何でもそうであろうが、実際始めてみると面白いのである。当時のレコード制作の事情を少し説明すると、月に一回、編成会議というのが開かれて、数ヵ月後に発売するレコードを選定するのである。シングル盤(17cm、45回転)は発売の60日前、LP(30cm、33
1/3回転)は発売の90日前に編成会議にかけることになっていた。制作を担当したディレクターから企画の説明があり、その場でシングル盤の、A、B両面の曲が試聴されるのである。片面だけのレコードというのは存在しないので、必然的にA、B両面の曲が必要になり、2曲あわせて1Wと呼ばれた。シングル盤の試聴の後、LPの企画が説明される。インストゥルメンタル(器楽曲)のLPを別にすれば、当時は芸術祭参加作品など特別な企画を除いて、ボーカルのオリジナル企画(アルバム)というものは殆ど無く、大抵はシングル曲が12曲集まったときにベスト盤としてLP化されるに過ぎなかった。
当時のシングル盤の編成W数というのは、今と比べて、嘘みたいに多かった。欧米では、アルバムの中で特に評判の良い曲がシングルカットされ、それが発売されるというケース多かったが、わが国では、そういう例は殆ど無かった。当時、わが国のレコード会社の売上は、大半をシングル盤のヒットに依存していたので、歌手のシングル盤のローテーションは短く、それこそ、2カ月、3カ月おきに発売し、毎月15〜20Wが編成され発売されていた。
当時、私が所属したレコード会社で、邦楽のジャケット制作を担当していたのは私ひとりだった。従って、編成会議が終わり、レコードの発売が決まると、会議が終わった直後から、猛烈に忙しくなった。各曲の歌詞を集め、歌詞の内容をそれぞれの歌手と対比させながら、ジャケットのイメージを考えるのである。シチュエーションによって、六本木アートセンター(商業写真撮影スタジオの先駆け的存在)等の写真スタジオにするか、適当な場所にロケに行くか、服装(当時はヘアーメイク、スタイリストは付かなかった)や小道具はどうするかなど、制作ディレクターや、プロダクションのマネージャーと打ち合わせし、それぞれの歌手のイメージに合ったカメラマンを選び、撮影に立会い、出来上がった写真をデザイナーに渡し、デザインを依頼するのであるのである。集めた歌詞は、暇を見つけて実際の唄と聞き比べて(業界の用語で“抱き合わせ”と言う)確認する。1週間以内に、同様の作業を15〜20Wのシングル盤すべてについて行い、出来上がったデザインを印刷所に渡して印刷を依頼する。表紙の色校正は大抵2回、歌詞の文字校正は3回それぞれのジャケットについて行い、それと平行して、5〜10タイトルのLPジャケットの制作に取り掛かるのである。
猛烈に忙しかったが、洋楽のレコードが、大抵海外から送られてきたデザイン(“アートワーク”と言って、印刷見本、カラー写真、4色分解されたネガ等が一式になっているもの)のレコード番号を変え、クレジットを加えるなど多少手を加えただけで印刷に回し、日本語の解説をレコード評論家に依頼するだけの作業であるのに対し、邦楽レコードは、何も無いところから、ジャケットを作り上げるクリエイティブな作業であり、毎回曲の内容に合わせて、新しいジャケットを考える楽しさがあった。また、自分がジャケットを手がけたレコードがヒットしたりすれば、それこそ、ジャケット制作者冥利に尽きるというものであった。
色校正が、何点も集中する日は、こちらから印刷所に出かけて、いわゆる出張校正をした。校正刷りが、同時に刷り上がることは無いので、次ぎの校正が刷り上るまでの待ち時間を利用して、印刷所から近い多摩川のグラウンドでキャッチボールをしたり、時には、かいた汗を流しに銭湯に行ったりした。今から考えると、結構のんびりした古き良き時代だった。
当時、私が所属していた編集課には、課長の竹下さん、流行歌担当の私の他、学芸・教養(民謡、小唄や長唄等の純邦楽、学校教材、国内制作のクラシックなど、流行歌以外の国内制作すべてのジャンル)担当の山本君、油木君と、岩田さんという女性がいた。山本君は、私より一つ年下で、工場に在籍して、会社のバレーボール部に長くいたが、部の閉鎖とともに編集課にやってきた。油木君は高校を卒業して、2年ほど工場にいたが、レコード関係の仕事がしたいということで編集課に異動してきた。岩田さんは、大学の新卒で配属された。学芸・教養のレコードは編集に手が掛かり、発売タイトル数も結構多く、この三人も私同様忙しく働いていた。
昔から、各レコード会社には、それぞれ決まった印刷会社があり、協力工場などと称していた。何故それぞれ決まった印刷会社があるのかと言えば、レコード会社同士が競合関係にあり、発売するまでは、自社の企画が他社に漏れるのを嫌った事が最大の理由である。また、印刷会社が何社もあると、バックオーダーなど商品の生産や管理が難しくなることや、そのほか、毎月、一定量の仕事を発注する代わりに、印刷費を安く上げるという狙いもあった。私の所属したレコード会社にも、勿論決まったKという印刷会社があり、そこの営業マンは殆ど毎日のようにわが編集課に出入りしていた。毎日のように顔を合わせていると、親しくなるのは当然であり、同じ会社の他部門の人間より、よほど気心が知れていたのである。親しくなりすぎて、甘えたり、馴れ合いになったりする弊害も無いではなかったが、お互い最低限の節度を守るように気をつけていた。
K印刷会社に松井君という営業マンがいた。私と同じ年ということで、何かと気が合って非常に親しく付き合っていた。彼の父親はK印刷会社の生え抜きで、K社の常務をしていた。見るからに豪傑という感じで、背はそれほど高くはなかったが、恰幅がよく、磊落な性格で、反面、細かいことによく気がつく人で、何かと我々若い者の面倒を見てくれた。この常務は、K社に対する功績は勿論、我がレコード会社草創期の事業基盤確立に多大な功労のあった、まさに伝説的な人物だった。我が社は、昭和初期に設立されたが、設立の当初からK社は我が社のジャケットの印刷を一手に引き受け、他社と競作のレコードが発売されると、若き日の松井常務は我が社のセールスマン達と一緒に、宣伝やイベントの先頭に立ち、たとえば、盆踊りの新曲が発売されると、社員と一緒になって踊り、レコードのヒットに絶大な貢献をした、というエピソードの持ち主である。
K社の松井君が、編集課の担当となって通い始めた頃は、親父さんの松井常務も頻繁に編集課に顔を出していたが、1年も過ぎるとさすがに顔を出す回数が減ってきた。或いは、息子が、親父が自分の得意先にあまり顔出しするのを嫌がったのかも知れなかった。私がK社へ毎月のように出張校正に行くと、松井常務はニコニコしながら校正室に顔を出して、挨拶してくれたものだった。K君も、最初はスマートだったが、酒好きで、そのうちだんだん体型が親父さんに似てきた。
それから、また1年ほど過ぎたが、その頃になると、松井常務は滅多に編集課に顔を出さなくなった。私がK社に出張校正に行っても、忙しいのか、松井常務の顔を見ることは無くなった。編集課内でも、最近松井常務の顔を見ないですねなどと話題になった。息子の松井君に訊くと、元気ですという返事が返ってきた。
そんなある日の午後、珍しく松井常務がひょっこりと編集課に顔を出した。確か、松井常務が、着ていたコートを脱いで入り口のハンガーに掛けたのを見た記憶があるので、確か季節は冬だった筈である。相変わらず元気そうで、冬だというのに額の汗を拭ったりして、相変わらずエネルギッシュな人だなと、私は感心した。30分ほど皆と話をしていただろうか、仕事の上でも、それほど問題になるようなことも無かったので、松井常務は「今後とも宜しく」と言って、慌しく帰っていった。
翌日、K社の松井君が、校正類をいっぱい大きな鞄に詰めてやって来た。早速、竹下課長が松井君に、
「昨日、君の親父さんが久しぶりに見えたよ。相変わらずお元気そうだね」と、言った。
その言葉を聞いて、みるみる松井君の顔色が変わった。彼はしばらく黙っていたが、
「そんな筈はありません。父は、××病院に入院しており、私は、昨日昼から見舞いに行って来ました」と、静かだが、きっぱりとした口調で言った。
松井君は、もう3ヶ月も前から、親父さんが胃癌で入院していること、病気が分かったときには既に手遅れで手術もできなかったこと、それから、親父さんから病気のことは我々に知らせないように言われていたことなどを話してくれた。
今度は、我々が言葉を失ってしまった。課の者は、ただ黙って顔を見合わせるばかりだった。室内の空気が凍りつき、沈黙がしばらく続いたことは覚えているが、その後のことはよく思い出せない。それから一月も経たない内に松井常務は亡くなった。
このときのことは、しばらく誰も話をしなかった。数年経って皆で飲んだとき、課内の全員が松井常務の姿を確かに見たということで話が一致したが、なんとも不思議な出来事だった。
今思うと、松井常務は、よほど自分の息子の将来と、K社と我が社の関係の行く末が気になっていたものと思われる。(2003/11/12)
©2004(無断で転載することを禁じます)
|