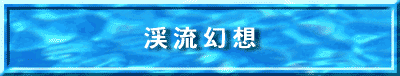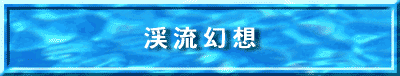|
柳原 釣童
ある年の九月十五日、当時山梨県の渓流の禁漁日は九月十六日だったが、私は忍野の桂川へその年最後の釣行を試みた。
忍野の桂川は、今でこそ釣り場としては見る影も無くなったが<注>、三月の解禁当初、私が毎日のように通った一九七〇年代の忍野は、フライ・フィッシングのパイオニア達の間でネイティブのブラウン・トラウトが釣れる川として人気が高かった。川幅いっぱいのゆったりした流れはまだ見ぬ英国のチョーク・ストリームを思わせ、透き通った川底には、長い藻が女性の髪のように揺らぎ、藻の間を泳ぐ大ヤマメやレインボー・トラウトの姿がはっきりと見えたものだ。(<注>1980年代後半から1990年代にかけての一時期、忍野の漁協が廃止され漁業権は消滅し、従って放流は行われず禁漁期間も無くなり、その後忍野は長い間荒廃した)
その日は、昼過ぎから釣りを始め、富士急ホテルの前から最上流の禁漁区の橋まで二度往復した。二度あったライズを合わせ損ない、#10の大型のホワイト・イレジスティブルが識別できなくなる夕方遅くまで粘りに粘ったが、結局一尾のトラウトも手にできないまま、その日と、そのシーズンの釣りを終えなければならず意気消沈した。
とっぷりと日が暮れた帰り道、国道百三十八号線を中央自動車道の河口湖インターチェンジに向かって車を走らせていると、富士吉田市内に入ってすぐ道路の左手にラーメン屋の明かりが目に止まった。私は急に強い空腹を覚え、駐車場に入って車を停めた。
だだっ広い敷地の中に一軒ポツンと建っているその店は、方形(ピラミッド型)の赤い屋根のある真四角な平屋で、白い壁が洒落た感じだった。
ガラス戸を開けて中に入った。店の中はむっとするほど蒸し暑く、掛けていた眼鏡がさっと曇った。私は眼鏡のガラスを拭きながら、店内を見回した。明るい店内の正面に厨房があり、厨房の三方をカウンターが取り囲んでいた。三方クロス張りの壁際にはテーブルと椅子四脚のセットが並んでおり、客席は半分ほど埋まっていた。カウンターの中では夫婦らしい若い男女が甲斐甲斐しく働いていた。
ラーメンを食べ終え、私の体はすっかり温まった。私が勘定を済ませて外に出ようとしたとき、入れ違いに十人近い若い男女の一団がどやどやと入ってきた。お揃いの紺のブルゾンに、男は白の短パン、女は同じく白のミニ・スカートといった姿で、ラケットは持っていなかったが、テニス同好会の合宿の学生らしかった。背中にはある大学の縫い取りがあった。男女とも屈託なく、眩しいほど健康的な若者たちだった。──
明るい笑顔、歓声と弾む会話を背に私は店を出た。
ドンと胸を突かれたような強い衝撃を感じた。私の胸の奥底で眠っていたマグマが突然吹き上げてきたように、二十年前の孤独で惨めな学生時代の記憶が鮮明に甦ってきた。人生の意義が見出せず、家に閉じ篭もり本を読み耽っていた自分の姿が・・・・。クラブ活動、スポーツの持つ爽快さ、心地良い汗・・・、私は彼らの姿の中に自分の失った青春の可能性を見たのである。
私はそれまで自分の人生を後悔したことは無かったが、この時初めて私は自分の青春を悔いた。同時に、自分が青春から遙か遠いところに、リップ・バン・ウインクルのように悄然と立っていることを悟った。
富士山麓の初秋の夜気が、身震いするほど冷たく感じられた。(1994年11月)
©2007(無断で転載することを禁じます)
|