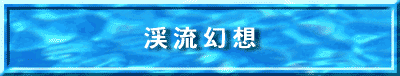
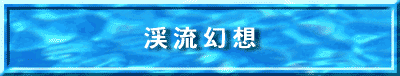
|
ヤマメ奇譚 |
|
柳原 釣童 ある年の五月、私は奥多摩のA川へ釣りに出かけた。この渓は私がホーム・グランドにしている渓で、自宅から車で一時間もあれば行けるので、夕方からぶらっと出かけることが多かった。 この日は、久しぶりにM橋の袂から入渓するつもりで出かけた。M橋から入渓すると渓が深くなり、道路が渓から離れて、1kmほどは渓から出られなくなるので、少し時間の余裕を見て昼前に家を出た。M橋の近くの空地に車を駐め、手早く昼食を済ませ入渓した。 釣り始めて暫くは開豁な渓が続く。五月の渓流と云うのは、恐らく自然の風景の中でも、最も美しいものの一つであろう。渓は生命に満ち溢れ輝いている。樹木や草の葉の、黄緑色を基調に、黄色味がかったのから、赤味がかったのまでの変化に富んだ色相、彩度と明度の無限とも思える階調の組み合わせによる色調の変化が、これだけ際立つ季節は他にはない。どんな高価な色見本帳でも、これだけの色数は到底表現出来ないだろう。山吹、藤、山躑躅の花が渓間を彩り、その中を冷たい澄み切った渓水が流れている。 落差の無い平瀬を300mほど遡ると、渓はほぼ直角に右へ曲がり、曲流点は大きな淵となっている。数年前の出水で土砂が流れ込み、淵はすっかり浅くなってしまったが、それでも夕方などはヤマメのライズが多数見られるところだ。淵の流れ込みは、丁度直角に流れ込んでおり、魚の右の視角に下流の釣り人の姿が入ってしまい、魚達は警戒して明るいうちはフライを追わない。 流れ込みの上流は、適当な落差の落ち込みが連続し、好ポイントを形成している。いつもはここで大抵ヤマメがライズし、型を見ることが出来るのだが、今日はライズが無い。ほんの少し前に通過した釣り人でもいたのだろうか。 大淵を過ぎて暫く歩くと、渓は深まり道路は頭上遙か高く離れてしまった。両岸は絶壁となって狭まり、欝蒼と生い茂る樹々が陽光を遮り、空気は冷涼と淀み、深山幽谷の佇まいを見せるようになる。渓はすっかり落差が無くなり、水溜りのような瀞場と、極く浅い平瀬が糾える縄のように延々と続いている。 私は先程からずっと、背後に何者かの視線を感じていた。人か獣か分からないが、大淵を過ぎた辺りから、そいつは私を付けているようだった。私は立ち止まり、振り返って四囲を見回した。日陰の谷底はしんと静まり返り、人影はなかった。猿か?野犬か?それとも熊か?背中に冷たいものが走った。暫くじっとして様子を見ていたが、別に何事も起こらないので気を取り直して釣りを再開した。 それにしても今日は不調だ。全くライズが無い。私はぼんやりと薄暗い水面を眺めていた。ふと、黒い魚の影が私の目の前を通り過ぎて上流に遡って行くのが見えた。可なりの大物だ。何処にこんな大物が潜んでいたのだろう。黒い影は上流の小さな落ち込みの淵にすっと入っていった。奴も私の姿を見ているに違いないのでフライを追うことはないだろう。そう思うと、まるで釣り落とした時のようにがっかりした。 落ち込みの上流はまた渓相が良くなり、底石が点在する水深のある瀬と、小さな淵が交互に現れた。私は瀬の中央に大きな底石が沈んでいて流れが複雑に縒れ、いかにも魚が潜んでいそうなポイントを見つけた。私はその石の1mほど上手にクイル・ゴードン#14を投げた。二投目でライズがあったが僅かにタイミングが遅れ、合わせ損なった。私は少しインターバルを取り、百まで数を数えて、再びフライをキャストした。今度先程よりずっと速いライズがあった。私は思い切り早合わせをしてこの魚を掛けた。22cmほどの鰭のピンと伸びた奇麗なヤマメだった。私は手を流れに十分に漬けて冷やして魚に触れ、ヤマメを傷つけぬようにリリースした。その時、リリースしたヤマメを追うように、下流から大きなヤマメが姿を現した。二尾のヤマメは縺れ合うように上流に姿を消した。私は今までこんなことは、見たことも聞いたこともなかったので、ひどく不思議な気がした。 暫く担々とした瀬が続いたが、渓は行く手で大きく左にカーブし、曲流点が深く長い淵になっているのが見えた。この時期、ヤマメは瀬の流心に出ていることが多く、淵でヒットすることはあまり無いが、淵の落ち込みの巻き込みでたまに良型がヒットしたり、超大物は淵の奥深くに潜んでいることが多いので淵を侮ることは出来ない。 また、大きなヤマメが私の足下を擦り抜けて、上流へ泳いでいくのが見えた。ヤマメは別に慌てた様子もなく平然と泳いでいた。一日に三度までも、山女に追い越されてしまった!カナダやニュージーランドの大河で、サーモンが釣り人の脇を猛烈なスピードで駆け抜けていくのは、そんなに珍しいことではないが、こんな狭い渓で、警戒心の強いヤマメが釣り人を悠々と追い越して行くことなど、普通有り得ないことだ。もしかして、ずっと私を付けていたのはあのヤマメだったのでは?まさか!何のために?そんな馬鹿なことはないと、私はすぐに自分の疑問を打ち消した。 私は細く長い淵の手前で立ち止まり、淵の様子を見た。両岸は切り立った絶壁が屏風のように連なり、前方で大きく左に曲がっていた。絶壁の上部は樹々が生い茂り、狭まった渓の底は薄暗く静まり返っていた。左手から急な流れが淵に流れ込み、対岸にぶつかって渦を巻いているのが仄かに見えた。 私は淵尻の駆け上がりを狙って、ヤマメが潜んでいると思われるポイントの1mほど上流に、ライトジンジャー・クイル#14(クイル・ゴードンのパターンでハックルがライト・ジンジャー)をキャストした。一投目で水面に白い飛沫が上がり、ヤマメがヒットした。パーマークのくっきりと現れたネイティブのヤマメだった。私はヤマメを弱らせないよう、手早くリリースした。私は更に5mほど進んで淵の中央部を狙った。濡れたフライを液体のドライ・フライ・ドレッシングに漬け、更にドライ・フライ・パウダーで念入りに乾燥させた。私は淵の規模や水深から可なりの大物を想定して注意深くキャストした。 フライが水面を1mほど流れ下ったとき、ゆっくりと頭を現わしてヤマメがフライを吸い込んだ。薄暗い水面に小さな波紋が起きた。静かだが断乎としたライズだ。私はヤマメの動きに合わせてゆっくりと竿を立てた。がっちりと鉤掛かりした。ヤマメは大した抵抗もせずにランディング・ネットに納まった。 見ると九寸ほどの見事なヤマメだった。フライをヤマメの口から外していると、ふと、ヤマメの口から何か白っぽいものが食み出しているのが見えた。何かよく分からないが、ゴムのようにビラビラして少々気持ちが悪かった。私はヤマメの口から食み出しているものを摘んで引っ張り出そうとした。ぬるっとして指が滑った。私は今度は親指と人差指の爪を立ててそれを摘んで引っ張り出した。途中でそれはヤマメの喉の骨に二三度引っかかる感じで、ずるずるとヤマメの口から出てきた。見ると15〜6cmはありそうな大きなカジカだった。頭から腹まで溶けかかっていたが紛れもなくカジカだった。私の摘んでいたのはカジカの尾鰭だったのだ。大人の親指ほどもある大きなカジカの頭が、ヤマメの喉に支えて飲み込めなかったようだ。 暫く絶食状態で、空腹に耐え兼ねてフライに飛びついたものと思われた。私はヤマメの獰猛さと意外な愚かさに呆れながら、「飲み込めないような大きな餌を食うんじゃないぞ」と言いながらヤマメをリリースしてやった。 ヤマメは暫く水中でじっとしていた。「弱ったかな?」と心配しながら見ていると、山女は頭を下げるような動作をして、それから静かに淵の奥深く姿を消した。 その時、私はふっと、その山女が喉に支えたカジカを外して貰いたくて、私の後を付け、私が釣った魚をリリースするのを見届けた上で、私のフライに食いついたのではないかと言う気がした。(2001/11/15) ©2001(無断で転載することを禁じます) |