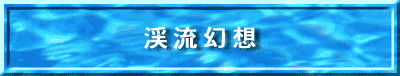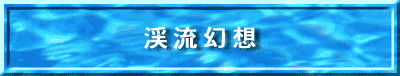|
柳原 釣童
ある年の解禁直後、私は何処かよい釣り場はないかと考え、近郊の地図を眺めていた。私の家から車で1時間ほどの距離にあるA川の支流を細かく調べて、有望そうな支流の幾つかに目をつけた。その日の午後、私は手始めに南A川の上流に出かけてみた。T山の登山口を過ぎて暫く車を走らせると、南A川に掛かる橋があった。橋の手前で道路が左右に分かれ、右側の本道はそのまま橋を渡り、左側の細い道は川の右岸に沿って伸びていた。
私は左側の未舗装の小道に入り、車を下りて右手に見える南A川の様子を見た。水は細いが、解禁直後の今なら水温が低く、この辺りでもヤマメが釣れるかも知れないと考え竿を出してみた。ところが予想以上に水質が悪く、50mほど釣ってみたが全く魚影が無いので早々に諦めて竿をたたんだ。
地図で見当をつけていたもう一つの釣り場、北A川の上流に移動した。初めて見る北A川支流O川は水が涸れて石ころが河原を埋め尽くしていた。私はそれでも諦めずに、農家や林の点在する川沿いの舗装された道を1kmほど上流に車を走らせた。車を止めて何度も川の様子を見た。そのうちに伏流していた水が僅かに姿を現し始めた。私は川の様子を見るため、なおも車を上流に走らせた。
この辺りでは珍しく人家が続くO集落の細い路地を抜けると、道路は川の左岸に移り、視界がぱっと開けた。窓から何気なく辺りを見ると、川を挟んで左右になだらかな小山があり、春の柔らかな陽射しを一杯に受けた丘の斜面には白や赤の梅の花があちこちで咲いており、道端や川岸には水仙や蒲公英の花が見えた。私は思わず車を止め、車を降りて周辺を見回した。なんという優しい風景だろう。どこからか鶯の鳴き声が聞こえてきた。川を覗き込むと、対岸(右岸)のブッシュの陰に魚が逃げ込むのが見えた。ヤマメだろうか?川幅は3〜4mほどあり、水量はまずまずで、何より魚影が見えたのでこの辺りから釣ってみようと思ったが、護岸が高く河原に降りることが出来ない。私は50mばかり引き返し、適当な駐車スペースを見つけて車を留め入渓した。
ごく浅い平らな河原には大小の石が転がっており、石の間を縫うように細い澄んだ水が緩やかに流れていた。水深は平均して10cmほどで、深いところでも20cmほどしかない。これでは、釣りは無理かと思ったが、それでも私の自信鉤、クイル・チョードーを投げてみた。やはり当たりは全くない。私は、大急ぎで先ほど魚影が見えたところまで遡った。
崩れかけた古い石積みの土手の、石の隙間から何本も潅木が生えており、葉を落とした枝が水面に伸びていた。枝の下には立ち枯れた葦が叢生し、魚の絶好の隠れ家になっている。私は、水面と枯れ葦の僅かな隙間を狙ってフライを投げてみたが、先ほどの私の影に怯えたのか魚は姿を見せなかった。
私は諦めて左岸の崩れた石積みから道路に上がり、上流に向かって歩き出した。左手に見えた小山が川に接近し、川は崖の下を流れていた。道路は川岸に沿って続いており、道路の両端には欅やカエデ、桜などが植えられ発芽前の枝を伸ばしていた。新緑の頃にはさぞ見事なアーチが見られるに違いない。川幅は5〜6mに広がり、大小の転石を浸すように僅かな流れが見えた。
私は、時折水深のある場所を見つけては竿を出してみたが、相変わらず当たりはなかった。そのまま500mほど歩いただろうか。川が左にカーブして道路から離れようとしている辺りで、私はよいポイントを見つけた。そこは川底が岩盤のため侵食を免れて川幅が極端に狭まっているところで、岩盤に刻まれた長さ2mほどの深い溝の中を、圧縮された水がゆっくりと流れていた。私は慎重に、窪みの中ほどにフライをキャストした。窪みの水が流れ出す直前、所謂落ち込みの肩の部分でライズがあり、10cmほどのヤマメが釣れた。私は「有難うよ」と呟きながらヤマメをリリースした。小型とは言えこの日初めて釣れたヤマメであり、何よりこの川にヤマメが棲息していることが確認できて嬉しかった。実のところ、この川にはヤマメはいないのかと半ば諦めていたところであった。
川は道路から離れ、私は鬱蒼と茂る暗い杉木立の中を700mほど歩いていった。道路の突き当たりにマスの釣堀が見え、釣堀の手前で道路は直角に左に曲がり、曲がってすぐにコンクリートの橋が川を渡っていた。
橋に立って上流を見ると二段堰堤があった。手前の堰堤はごく低いものだったが、その上の堰堤はかなり高かった。低い堰堤を越して上に出ると、経10m緯7mくらいの大きなプールがあった。水深は深いところで3m近くあるだろうか、プールの奥に大きな枯れ木が沈んでいるのが見えた。私は堰堤付近から生じた泡が消える辺りにフライを投げた。フライが50cmほど流下すると、沈んでいる枯れ枝の陰からヤマメが浮上してくるのが見えた。水面にヤマメが口を出すのと同時に私は合わせた。今度は先ほどとは桁違いの手応えがあって、ロッドが何度も絞り込まれた。私はヤマメが枯れ枝の中へ駆け込まないように、ロッドを高く保持した。取り込んでサイズを計ると26cmあった。この規模の川としては最大級かも知れない。
私は、堰堤横の急斜面を立ち木に掴まりながら攀じ登り、再度釣り始めた。堰堤を越すと水量が増し、落差のある本格的な渓相になった。これではもう川とは呼べない、立派な渓である。随所に落ち込みと渕、水深のある瀞場が点在する好渓である。私は胸をときめかせながら釣り上がって行った。ところが、どこまで行っても当たりはない。気が付くと周囲は薄暗くなっていた。気温が下がり、足の爪先から寒さが這い上がってきて思わず胴震いした。これだけ寒いと水温が低下し、魚のライズは望めないだろうと考え、すぐ目の前に見える木製の橋の袂から右岸の道路に上がった。
今まで気が付かなかったが、対岸からカチン、カチンと云う何か硬いものを金属で叩いているような音が聞こえてきた。見ると橋を渡ったところに大きな空き地があり、空き地の片隅に粗末な小屋が建っていた。開けっ放しの戸口から明かりが漏れており、小屋の中で誰かが作業をしているらしい。
小屋の中を覗いてみると、天井からぶら下がった二個の裸電球の下で、一人の男が大きな石に向かって鑿を振るっていた。色褪せた紺の作務衣を着た顔中髭だらけの大男で、風貌からは年恰好はよく分からないが、何だか鍾馗様みたいだなと思った。筋骨逞しい左腕に鑿を、右手に大きな金槌を持ち、少し前屈みになって無心に石を穿っていた。床の作業台の上には、長さ、太さ、形のさまざまな鑿と、電動の工具などが雑然と置かれていた。普通素材の石は横にして彫るものだそうだが、この男は荒い割肌の四角な高さ四尺五寸ほどの御影石の石柱を、石の台の上に立てて彫っていた。顔中汗まみれで、作務衣はぐっしょりとかいた汗で色が変わっていた。男は微塵の迷いもなく、石を彫り続けている。見る見るうちに、石の中からお地蔵さんの上半身が現われてきた。まるで、石の中に埋もれているお地蔵さんを掘り出しているような、見事な腕前である。以前誰かの本で読んだミケランジェロみたいだなと思った。私は長い間我を忘れてその熟達の技に見惚れていた。
男はふっと手を止めて私を見た。私はどぎまぎして、咄嗟に「すみません、無断でお邪魔しまして・・・・」と、詫びを言った。
「いや、別に構いませんよ」と、男が答えた。その声は私が想像していたよりずっと若々しく、バリトン歌手のようによく響いた。
「お地蔵さんをよく見せて下さい」
「どうぞ」といって、男は鑿と鎚を傍らの台の上に置いた。
私は改めて、お地蔵さん見た。不思議なことに体全体は未完成で、殊に下半身などまだ割肌の石塊のままで、上半身は胸の前に合わせられた両手が、辛うじて手と分かるくらい荒削りなのに対して、顔は殆んど完成されていた。何と慈愛に満ちたお顔であろうか、私は莞爾と微笑むその表情に思わず息を呑んだ。画や彫刻は作者の心を写すと云うことを聞いたことがあるが、このお地蔵様は、まさしくこの作者の心を写しているに違いない。
彼は彫刻については何も語らなかった。私も、この作品のあまりの素晴らしさに言葉を失っていた。
「釣れましたか?」、突然、彼はニコニコしながら私に尋ねた。髭面に似合わず、柔和な眼をしていた。
「2尾だけです」と、私は正直に答えた。
「この辺りのヤマメは、皆私が放流したものです。あまりいじめないで下さいね」。彼は、いたずらっぽくそう言って笑った。
いろいろ釣りの話しているうちに、南A川の支流、K川の上流にいい釣り場があると、詳しい道順と、目印にお地蔵さんが立っていることを教えてくれた。最後に、他の人にはこの釣り場のことは決して話さないで下さい、と付け加えた。
周囲が真っ暗になってひどく寒くなってきたのに加え、あまり彼の仕事の邪魔をしてはいけないと思い、私は礼を言ってその場を辞した。
一ヶ月ほど過ぎた4月上旬、私はあの彫刻家に教えられた釣り場を訪ねてみた。南A川の支流K川はK峠付近から流れ下って来ている。私はK川に沿ってK街道を上っていった。沿道には桜の花が満開で、まさに春爛漫といったところである。以前、この辺りへは何度か釣りに来たことがあるが、彼に教えられたような川にはついぞ出合ったことがないので私は半信半疑であった。
九十九折の山道をどんどん上っていった。この辺りは高速道路と鉄道が並行して走っているところで、私は彼に教えられた通り鉄道のガードを潜った。ガードを抜けるとK街道は左にカーブしK峠の方へ向かうのだが、彼の話ではそこを左に曲がらず右に進むのだという。今まで全く気がつかなかったが、右手に草に埋もれかけたかなり傾斜の急な道路が見えた。私は、道路の窪みや転石に気をつけながらそろそろと車を走らせた。山道を登っていくと、道路は左にカーブし、カーブを抜けると左右から山が迫ってきて、眼の前に高速道路の橋脚が見えた。頭上を高速道路が通っているのだ。浅い谷あいの道をなおも登っていくと、広い空地に突き当たった。私は空地の入口近くで車を降りて周囲を見回した。かなりの広さがあり、建築資材の置き場のようである。おそらく、この広場は、工事のために山を削って造られたものだろう。
私は目印として立っていると言われたお地蔵さんを探し始めた。探し始めてすぐに、広場の右隅の枯れ草に中にひっそりと立っている高さ50cmほどの小さなお地蔵さんを見つけた。私はすぐにお地蔵さんの顔を見た。お地蔵さんの顔は、あの時のお地蔵さんの顔と瓜二つだった。私は思わずお地蔵さんに一礼した。
お地蔵さんのすぐ横で山に登っていく獣道のような小径を見つけた。密生した樹林の中を急な上り坂が40分ばかり続いた後、小径は山の斜面をゆるやかに下っていった。樹々に視界を遮られて周りは何も見えない。20分ほど下ると、幅5mほどの涸れ谷に出た。ひんやりとした谷底の風が、汗ばんだ頬や額を心地よく撫ぜた。河原には今にも消えてしまいそうな細い流れが左から右に流れていた。私は、あまりの水の少なさに落胆したが、気を取り直して周囲を見回した。川は下流で右に曲がり、その先は樹立ちの中に消えてしまっている。上流は左にカーブしているが、右岸に迫り出した岸壁に遮られてその先はよく見えない。私は、とにかく上流へ行ってみようと思い歩き出した。
右岸に突き出した崖を曲がると、私は今まで見たこともない不思議な光景に遭遇した。川幅は三倍ほどに広がり、全面岩盤で出来た川床が右(左岸)から左(右岸)に緩く傾(かし)いでおり、大量の水が河原を滑るように流れて右岸の崖の下に流れ込んでいた。崖の下には高さ1m、長さ10mほどの穴が開いていて川水の殆んどすべてを飲み込んでいた。私は恐る恐る近拠り3mほど離れたところから穴を覗き込んで見たが、奥は真っ暗で、かすかにゴーという水の音が聞こえてくるだけだった。私は、何だか恐ろしくてそれ以上近づけなかった。この水はどこへ流れ、どこで地表に出るのだろう。
私は上流の様子が見たくて遡った。平衡感覚が変になりかけながら斜面を登りきると、岩盤の河原は再び水平に戻ったが、そこには信じられないような好渓が開けていた。川幅は15mくらいだろうか、大小さまざまな底石が点在する中を、澄み切った水がゆったりと流れている。水深は30cmほどで、ところどころに深い渕と落ち込みが見える。両岸は緩い傾斜で這い上がり山へと続いている。川岸には芝草やハコベ、ヨモギ、オオバコなど背の低い草が青々と簇生し、蒲公英や水仙、スミレやヒメオドリコソウの花が色とりどりに咲いている。左岸の広い河原には山桜や桃、山吹やミツバツツジなどが点々と咲き、すぐ耳元でウグイスやシジュウカラや、その他名前を知らぬ野鳥の鳴き声が聞こえ、モンシロチョウやモンキチョウが花の上を飛んでいる。私は鼻と口から空気を思いきり吸い込んだ。こんな旨い空気は絶えて味わったことがない。まるで夢を見ているようであった。此処こそ話に聞く桃源郷ではないかと思われた。
私は背負っていたナップザックから、6本継、7.5フィート、#4のロッドを取り出し、リールとフライをセットした。期待で心臓の鼓動が早くなり、フライを結ぶ手が震えた。私は陽射しが正面から来るのを避けて左岸に立ち、瀞瀬の深い流心を狙って、クイル・チョードー#14をキャストした。投げるとすぐに大型の魚が浮上し、ゆっくりとフライを吸い込んだ。私は相手のゆっくりとした動作にゆっくりと応じた。ランディングし、サイズを計ると27cmの良型のヤマメである。続けて私は同じポイントで、同型のヤマメを3尾釣り上げた。それにしても、何と釣り易い魚だろう。全くスレていない。管理釣り場のニジマスでもこんなに簡単には釣れない。今まで誰も竿を出したことがないのだろうか。
私は一息ついて空を見上げた。湿気を含んで霞んだ空から陽光が降り注ぎ、真綿のような丸みを帯びた雲が点々と浮かんで、ゆっくりと西から東に流れていた。右手に見える山の傾斜は緩やかだが、左手の山は傾斜がややきつく、稜線が屏風のように右に曲がって遥か前方に立ち塞がっているのが見えた。両山とも広葉樹の芽吹きで、淡い緑、黄緑色、薄茶色、灰色など、色とりどりの紗のベールで覆われていた。見たことはないが、マリー・ローランサンが風景画を描けばきっとこんな風になるだろうと思った。
私は上流に見える小さな渕とその先の落ち込みに近づいた。渕尻に大きなヤマメが尾鰭を動かしながら流れてくる餌をじっと待っているのが見えた。私は斜め後方に立ち、ヤマメの50cmほど上流にフライをキャストした。今度も一発でヤマメがヒットした。尺を超える大物であった。私は尺物をゲットしたら、即座に納竿することを自分に課していたが、その時はこの釣り場の先を見極めたいと思い、そのまま竿を出さずに遡行した。
右岸には遡行を妨げる崖がところどころ張り出していたが、左岸には取り立てて言うほどの障害物は見当らず、快適な遡行が楽しめた。通り過ぎる渕のあちこちに大型のヤマメが悠然と泳いでいるのが見えた。
一時間ほど歩くと、目の前に高い岸壁が立ち塞がった。川はそこで行き止った。右手に深い谷が見えたが、水は涸れていた。崖の前面に大きな渕があり、よく見ると崖の下の裂け目から大量の水が噴出していた。渕の底では一面に繁茂したセキショウモが長い葉を揺らしている。藻の間に大きな魚影が幾つも見えた。出し抜けに、私の目の前で優に40cmはあろうかと思われるヤマメがジャンプした。私は夢見心地で、この情景を眺めていた。ここがこの川の水源だと思われるが、一体この水はどこから来るのだろう。
その後、二度私はこの川を訪れたが、その度に大物が釣れ早々に納竿したので、あまり長時間釣りをしたことはなかった。
あるとき、釣友の一人が不漁をを託(かこ)っているのを見かねて、私はこの釣り場のことをその男に教えた。その後、彼に会っていないので結果を知ることは出来なかったが、連絡がないところをみると、あまりよい釣りをしなかったらしい。
翌年の四月、私は久しぶりにその釣り場に行ってみた。建築資材置き場は確かに残っていたが、目印に立っている筈のお地蔵さんは見つからなかった。お地蔵さんの立っていた辺りを隈なく探し回ったが、恣に生い茂った雑木に埋もれてあの小径はどうしても見つからなかった。私は、その時初めて「人に話してはいけない」というあの彫刻家の言葉を思い出した。
ある日、私は無性にあの彫刻家に会いたくなりO川に行ってみた。あの時の橋は健在で、空地もあったが、小屋らしきものは見当らなかった。小屋のあった跡に、ぽつんと高さ1mほどのお地蔵さんが立っていた。お地蔵さんは、まるで怒ったように口をへの字に結んでいた。(‘08/2/15)
©2007(無断で転載することを禁じます)
|