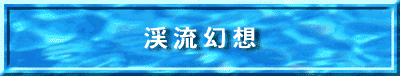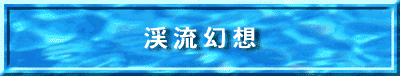|
柳原 釣童
クピドの矢
私の古くからの友人に上田卓也という者がいる。高校のときからの友人で、大学時代の友人よりお互いをよく知っているので、何でも心置きなく相談できる間柄である。
我々は四十を疾うに過ぎてお互いいい年になっていた。普段は冗談や、昔の悪戯などを思い出させては笑いあっていたものである。上田は大手の広告代理店に勤務し、私は出版社に勤務していたが、お互い数人ずつ部下を持っていた。
ある好天の午後、私は神田の古書店街を歩いていて、偶然上田と出会った。いつも快活な上田が浮かない顔をしていたので、どうしたんだと聞くと、「何でもない」と答えた。彼の表情から、話したそうな様子が見て取れたので、無理に聞き出さなくてもそのうち自分の方から話し出すだろうと思った。六月のごく蒸し暑い日だった。立ち話も能が無いので、我々は近くの喫茶店に入った。
アイス珈琲を飲んでいると、我々がまだ若かった、遠い昔のことが思い出された。私は、上田のような古くからの友人と話すのが好きである。現実の、いろいろな煩わしさを一瞬でも忘れることができるからである。上田と昔話をしていると、ふと上田が真面目な顔に戻っているのに気がついた。いよいよ、彼が話す気になったようだ。
「実は、俺の部下に、と言ってもただの嘱託なんだが、名前は島崎加奈子と言って学部は違うが大学の後輩がいる。仕事先の紹介で、無下にも断れず簡単な雑用でもやって貰おうと採用したんだ。本人曰く、卒業時にいろいろな会社の採用試験を受けたが、すべて落ちて正社員になれなかったと言っていた。その後、編集プロダクションだとか小さな広告代理店などでアルバイトをしてきたそうだ。歳はアラサーと言うか、三十路を過ぎ、細身で容姿はまずまずだが、美人と言うほどでもなく、語学力もいまいち、すべて中途半端な感じの女である。実家が医者と言うことで裕福な家庭らしいが、あまり上品な育ちは感じられない。本人は医者になれるほど頭は良くなかったようで、文学部に進んだらしい。」
彼はここまで喋って、アイス珈琲を一口飲んだ。そしてまた話し始めた。
「俺は、雑誌など紙媒体の広告の仕事をしているが、彼女には色校正おろか、簡単な文字校正も危なっかしくて任せられない。注意力が不足しているというか、繊細さが足りない。一例をあげると、手紙を折り畳むにしても、上下左右はみ出して、まるで外人のように大雑把な折り方をする。本人はどうやら、TVコマーシャルなど映像関係の広告の仕事がしたいらしく、勝手に映像セクションに出入りしたりしていた。俺は、この女はとても使えないなと思い、次回の雇用契約は出来ないなどと考えていた。」
「ところがこの女が、若い課員や、外部のコピーライターやデザイナーとか、出入りの印刷業者の受けが妙にいいのである。一流大学を卒業している割にはよく言えば気さく、見方を変えれば蓮っ葉で、媚びるような甘ったるい声で、きわどい冗談を平気で言ったりする意外性が受けているのかも知れなかった。それどころか、映像セクションの部員たちにも上手く取り入っているようで、一体何処の所属だと言いたくなった。俺は、彼女に映像関係のセンスがあるようにも思えなかったので、無駄な努力をしているように俺の眼には写り、愚かで哀れな女に思われた。」と言って、彼はここでまた一息ついた。それから、またやおら話を続けた。
「彼女は、自分が東京生まれのように振る舞い、自分の出身地のことは決して口には出さなかった。福島出身だと言うことに強い劣等感を持っているようだ。俺は、何と浅はかな女だと益々軽蔑するようになった。気位だけは高く、おまけに思い込みが強い。」ここで彼は大きな溜息をついた。
「ところがこんな俺が、こともあろうにこの女が好きになってしまったんだ。ある日の昼休み、外部のデザイナーや、出入りの業者や他の課員と一緒にわいわい話しているところに居合わせ俺もその話の輪に加わったことがあった。その会話の中で、一瞬、確実に俺の心に異変がおきた。彼女のどんな仕草、表情、言葉が俺の心を捉えたのか今でも思い出せないが、何だか急に可愛く思われ、俺の心は、まるでカルメンに恋するドン・ホセになっていた。」
私は、上田の顔を覗き込んだ。冗談を言っているようには見えなかった。上田は高校時代から秀才で、生真面目すぎるほど真面目な男だ。よく出来た奥さんがおり、子供も二人いて家庭を大事にしている。そんな男が、他の女に目移りするなんてことがあるだろうか。彼の話では、あまり程度の良くない女で、分別のある上田がそんな女が好きになることなどあり得ないと思った。
上田は、相変わらず憂鬱そうな顔をして話を続けた。
「俺は、今まで相手にもしてこなかった、それどころか軽蔑さえしていた女に、何故恋をしなければならないのかと自問自答した。俺は、もしかしたら彼女が俺のお茶に媚薬か何か入れたのではないか、と阿呆なことを考えてみたりもした。そんなことはあり得ないが、あの瞬間、俺の心に何か異変が起きたことは疑いが無い。もしかしたら、ローマ神話のあのクピドが、俺の心に悪戯の矢を放ったのかも知れない。」
「胸のときめきを覚えたのは二十数年ぶりだろう。恋する俺には彼女が非常な美人に見え始め、彼女の媚びるような甘えた声が、まるで妙なるオーボエの調べのように聴こえてきた。周囲が見えなくなった俺は、彼女をクラシックのコンサートや、話題の映画に誘ったりした。それも何度もだ。そのたびに、彼女は体よく俺の誘いを断った。恋するドン・ホセの気持を弄ぶカルメンのように、彼女は自分に恋する俺の姿を見て楽しんでいるようだった。」
「そんな状態が何ヶ月続いたろうか。そろそろ社内でも噂になり始めていたらしい。あるとき、懲りずに彼女を映画に誘っていたら、ふと彼女の顔に勝ち誇ったような表情が浮かんでいるのに気がついた。そのときである。また不意に、俺の心臓からクピドの矢が抜け落ちたんだ。俺は、今の自分が如何に屈辱的な立場であるかを自覚した。俺は正気を取り戻した。」
「嘱託契約の話し合いの席で、俺は契約の延長はしないと彼女に告げた。彼女は、映像セクションのプロデューサーに泣きついてそのセクションで働くことになったが、数ヵ月後には向いていないということで首になったらしい。」
「深みにはまらずに済んでよかったじゃないか。むしろその女に感謝すべきだね。それにしても、何でそんな暗い顔をしているんだ。まだ未練でもあるのかね」と、私は上田に訊いた。
「そんなんじゃない。俺が落ち込んでいるのは、気にも止めなかった、馬鹿にさえしていた女に、突如として恋をしてしまった自分の心が、なんとも不可解で、恥ずかしくて、空恐ろしいんだ。」と上田は答え、それきり黙り込んでしまった。(2010/6/20)
©2010(無断で転載することを禁じます)
|