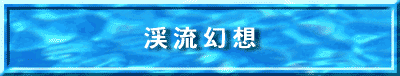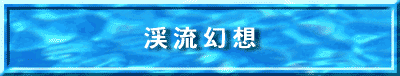|
柳原 釣童
1970年代初めのことである。フライ・フィッシングを始めて5年ほど経っていたが、その頃私は、山梨県の忍野の桂川に毎週のように通っていた。今でこそ忍野といえばフライ・フィッシングのメッカのように言われているが、当時の忍野は餌釣りをする人はいても、フライ・フィッシングをする人など誰もいなかった。私は何年もの間、まるで管理釣り場を借り切ったように、忍野のフライ・フィッシングを楽しんでいた。
三月のある日、私が忍野の桂川の河畔で、木の枝の下で盛んにライズしているアマゴを狙ってキャストしようとしたとき、ふと背後に人の気配を感じて振り返ると、いつの間にか若いフライ・フィッシャーが立っていた。
「釣りを見させて頂いても宜しいでしょうか」と、その若いフライ・フィッシャーが私に訊いた。屈託なさそうに、にこにこしながら私に話しかけた、面長の長身痩躯のその男は、私より四、五歳年下で、長髪の頭にハンチングを被り、服装は私よりよほどフライ・フィッシャーらしい格好をしており、タックルも私より数段上の高級なものを持っていた。
かなり不躾な話だとは思ったが、その男の人の善さそうな顔を見ていると断り切れなかった。
「いいですよ、どうぞ」と、私は答えた。
私の立っていた忍野の川岸は水面より1.5mほど高いので、私はアンダーハンド・キャストで、水面と枝との20cmほどの隙間にフライを送り込んだ。それまで私は人に見られながら釣りをした経験が無く、いささか緊張して1回ミスし、2回目に、あと10cmばかり上流へフライを送り込みたかったのだが、アマゴがライズしている真上にフライをプレースしてしまった。フライが着水すると同時に、アマゴがバシャッとライズした。私は、一瞬木の枝を気にして強く合わせることができなかった。一応鉤掛かりしたのだが、掛かりが浅く呆気なくバレてしまった。
「こんな処でも釣れるんですね」と、彼は目を丸くして、心底驚いたように言った。
「少し合わせが弱かったですね、木の枝が無ければきちんと合わせられたんだけど」
私は少々言い訳がましく答えた。
彼は井口哲夫と名前を名乗り、自己紹介をした。彼は、北海道の道南で育ち、一昨年からフライ・フィッシングを始めたそうだ。上京して就職したがフライをやりたくて堪らず、北海道の先輩から忍野の話を聞いて釣りに来たが、北海道の釣り場とは勝手が違って、全然釣れないと言うことだった。北海道の河川は、尻別川水系のように概して平坦で川幅が広く、カーブごとの渕がポイントになり、ポイントとポイントの間が長いので足で稼ぐ釣りになるようなことは私も訊いていた。当時の北海道はヤマメがいっぱい釣れたので、イワナを狙う人は殆ど無く、従って障害物の多い渓の釣りなど彼は経験したことも無かったのだろう。
餌釣り師ばかりの忍野であっても、ヤマメやアマゴはスレて用心深くなっており、北海道の河川とはポイントやライズの仕方が全く違っている筈である。私は、彼にいろいろアドバイスし、キャスティングを見てやったりした。彼は、その日終日私の後について、私の釣りを眺めていた。これが、私が井口と知り合った経緯であり、彼はその日以来私に弟子入りし、その後の長い付き合いが始まったのである。
私は彼を伴っていろいろな川を釣り歩いた。富士急沿線の桂川やその支流、道志川、千曲川の本・支流、笛吹川上流、日川、日光の湯川、桧枝岐川、その他数多くの渓を釣り歩いた。最初の2,3回は、彼は自分の釣り竿を持たず、私の後について私の釣りを見ているだけだった。私は、自分の知る限りポイントの選定や、フライの選択、フッキングなどを彼に教えた。そのうちに交代で竿を出すようになり、彼は急速に上達した。彼は北海道出身らしく、大きな川が好きだった。彼に誘われて、私は何度も夜叉神峠を越えて野呂川に釣りに行ったものである。彼は私と同行する度に、「フライを見せて下さい」と、私のフライ・ボックスのフライを手にとってじっと眺めていた。
井口はその頃独身だったこともあって、我々家族を花見や水遊びに連れて行って呉れたりした。そのような家族ぐるみの付き合いが十年近く続いた。今振り返れば、その頃が私の釣り人生で最も楽しい時期だったかも知れない。
ある日、井口が一人で東北へ釣りに行くといって出かけて行った。いつもなら、釣行の結果を必ず報告に来るのに、その時に限って何日経っても音沙汰が無いので、どうしたのかと電話してみた。
彼はその夜私の家にやってきた。いつもと様子が違って、ひどく沈み込んでいた。彼は唐突に、
「私は釣りを止めます。いろいろ有難うございました」と、言った。
私はびっくりして、その理由を問い質した。
彼は、青い顔をして長い間黙り込んでいたが、漸く重い口を開いて次のような話をして呉れた。
…………………………………………………………………………
七月上旬、井口哲夫は梅雨の晴れ間を狙って一人で福島のT川の支流に出かけた。地名ははっきりと言わなかったが、T川のかなり源流近くの支流らしい。前日、別の支流で釣って、その日の夕方、地元の人が不帰谷(帰らずの谷)と呼ぶT川の支流に面した集落の、小さな宿に泊ったのである。
井口は、古本屋で三十年も昔の釣り雑誌を買い、その雑誌の中で大イワナが釣れる渓があるという記事を見つけて、この川を訪ねてきたのである。その記事によると、その川の上流は、鬼面谷と夜叉谷という二本に分かれ、両渓とも険谷だが大イワナがいるということだった。
その夜、食堂で若い同宿者に会った。他には宿泊者はおらず、話しているうちにお互いに釣り師で、しかもフライをやると言うことが分かった。その男は加藤修と名乗り、やはり東京で会社勤めをしているという。加藤は井口と違って、身長は同じぐらいだが、かなりがっちりとして肉付きが良く、どちらかと言えば肥満体の部類に入るだろう。以前何かスポーツをやっていたのかも知れない。加藤は丸顔で、顔の造作も大きく、押し出しが良く、しゃがれた野太い声で喋った。こんな男が企業では伸し上っていくんだろうな、と思ったりした。一つ気になったのは、上目遣いに人を見ることである。あまり気の許せる相手ではないかも知れないと感じた。男と言うものは女と違って、趣味は別として一般的にあまり相手のプライバシーに興味を持たないものであり、よほど親しくなった場合を除いて相手の勤務先や、家族構成、生い立ち、住所などを訊いたりしない。二人は互いの名前を訊いただけで、夜更けまでビールを飲みながら、結局釣りの話ばかりしていた。二人は、同じ渓に釣りをしに来たことが分かっていたので、上流の二つの渓に分かれて入ることに決めて、互いの部屋に戻った。
翌朝、二人は六時半に食堂で朝食を食べた。昼食用にお握りを三個ずつ包んでもらい、宿代を払い、七時過ぎに宿を出発しようとしたとき、
「この辺りには、水溜りには決して足を踏み入れてはいけないと、いう言い伝えがあります。どうか、水溜りを見つけたら避けて下さい。くれぐれも水溜りに入らないようにお願いします」という意味のことを、宿の年老いた女将が分かり難い土地の言葉で二人に話した。
唐突に変なことを言われたが、加藤は全く気にも留めていない様子だった。
二股までは林道を歩いて20分ぐらいだと宿の女将に聞いていたので、二人は車を宿に置いて歩くことにした。途中、左股の鬼面谷を加藤が釣り、井口が右股の夜叉谷に入ることを決めた。井口は、先ほど女将に言われたことが気になっていた。その土地土地に、いろんな言い伝えがあること、また、それがまんざら荒唐無稽とばかり言い切れないことを、これまで各地で釣りをして来て知っていたからである。
その日は梅雨の時期にしては、珍しく朝から二日続きの快晴であった。林道の途中に車止めのゲートがあり、厳重に鍵が掛かっていた。ゲートの脇をすり抜け、さらに10分ほど歩くと不帰谷に掛かる橋があり、その先で林道は二股に分かれた。井口は加藤と別れて、夜叉谷に入渓した。
夜叉谷は、落差が大きく、時折大渕のへつりや、通らずを巻くことを強いられる険しい渓であった。水量が多く、渡渉には細心の注意が必要だった。彼は、いまやブッシュなどに煩わされることは無く、キャスティングの技術も一流の腕前になっていた。入渓して、暫く当たりが無かったが、30分ほど過ぎたとき、落ち込みの巻き込みで、いきなり大きなイワナがグリズリー・ウルフ#10にライズした。このフライは浮きが良く抜群に視認性の高い、北海道で実績のある井口愛用のフライである。体調を計ると32cmあった。初めての獲物が、いきなり尺クラスだったので、嬉しい反面、目標が無くなってしまったような空虚な気持になった。その後、良型のイワナを2尾釣って一服し、時計を見ると昼を過ぎていた。急に空腹を覚えて、握り飯を頬張った。この時、彼は先程女将に言われたことなどすっかり忘れてしまっていた。
40cm近いものを含め、尺クラスのイワナを6尾釣った頃、俄かに雲行きが怪しくなってきた。東北の渓では鉄砲水が要注意なのは十分心得ていたので、井口は釣り場に未練を残すことなく、素早く適当な登り口を見つけて林道に上がった。林道に上がると、雨が降るより早く川水が濁りだした。彼は足早に林道を下って行ったが、途中で土砂降りになった。慌てて雨具を着込み、歩みを速めた。雨水が林道上を川のように流れていた。立ち止まって夜叉谷を覗くと、流れは茶色に濁り、恐ろしいほど膨れ上がってゴーゴーと音を立てていた。
先程、林道が二股に分かれたところに着いた。右手の、鬼面谷に通じる林道を振り返ると、雨合羽を着た加藤が下って来るのが見えた。二人は互いの釣果を確認し合ったが、同様の釣果だった。この釣り場の素晴らしさについて話しながら二人が林道を下っていくと、ゲートの100mほど手前で林道の傾斜が緩くなり、路上のあちこちに水溜りが出来ていた。井口は宿の女将の話を思い出し、道路の端を用心深く水溜りを避けて歩いた。加藤は、井口のそんな様子を見て、微かに侮ったような表情を浮かべ、
「あんなの、迷信ですよ」と、声を上げて笑った。
加藤は、ある水溜りを見つけて、井口が制止する暇も無くずかずかと入っていった。
彼は振り向いて、「どうです、なんでも無いでしょう」と、言い終わるか終わらないうちに、恐怖に顔を歪めて「あっ」と、叫び声を上げた。加藤はまるで何者かに足を掴まれ引きずり込まるように、両腕を上げて水溜りに沈んでいった。左手に握られた加藤のロッドの先が、まるで大魚に引き込まれる浮子のように、スーと水中に消えていった。
井口は為すすべも無く、呆然とその光景を眺めていた。こんな小さな水溜りに人が落ちて消えるなど、ある筈も無いことだ。水溜りの波紋が消え、元の静かな水溜りに戻った。知らぬ間に雨が小降りになり、水面には雨粒の波紋の花がポツリ、ポツリと開いていた。思考が完全に停止してしまった。井口の耳には、何の物音も入らなかった。
井口は、はっと我に返った。体中を戦慄が貫き、得体の知れない恐怖に襲われた。彼は、後も見ずに麓の宿に向かって走り出した。足ががくがくし、途中で何度転んだか知れなかった。
…………………………………………………………………………
その後のことは、井口はあまり詳しく語らなかった。警察に駆け込んだが信じてもらえず、挙げ句の果てに、井口が加藤をどうにかしたかのように疑われ、二日間警察に足止めされたそうだ。
井口は、加藤が水溜りに沈んでいった時の顔を思い出すと、二度と釣りをする気にならないと言って、故郷の北海道へ帰ってしまった。(2005/9/11)
©2005(無断で転載することを禁じます)
|