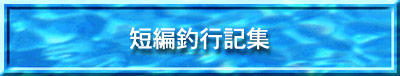
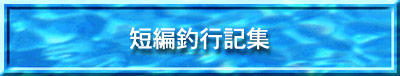
![]() 11/15 「雑魚川のイワナ」追加!
11/15 「雑魚川のイワナ」追加!
|
雑魚川のイワナ |
||||||||||||
|
柳原 釣童
‘01年7月22日の夜11時半、私は八王子の自宅を出て志賀高原の雑魚川に向かった。この川は、私が長年釣りに行きたいと思いながら行く機会の無かった川の一つである。中央自動車道から諏訪の先で長野自動車道に入り、信州中野ICで降り、国道292号線で志賀高原に向かった。途中丸池で道を間違え、気がついたら渋峠まで来ていた。途中、登りばかり続き何度か変だなと思ったが、真夜中で周りの景色が見えない上に標識が一つも無く、とうとう峠の頂上まで来てしまったのである。
道路は雑魚川に沿って下って行った。熟平を過ぎた頃から周囲が明るくなってきた。私は、暗い内に雑魚川に着いて一眠りするつもりだったが、途中道に迷って思わぬ時間を食ってしまい、どうやら仮眠を取る時間がなくなってしまった。「眠くなったら昼寝でもするか」と考え、どこに入渓しようかと考えながら車を走らせた。
フライを取っ換え引っ換え試してみたが、魚は全くライズしなかった。水面近くを漂っている羽化寸前の水生昆虫にライズしていたのだろうか。水温を計ると12℃しかなかった。30分ほどトライしてみたが駄目だった。小型のイマムジャーか、フローティング・ニンフなら食ったかも知れない。
早朝に到着し、まだ入漁券を購入できずにいたので、入漁券を購入できる処を探しながら上流に車を走らせた。熟平で、中電の立派な保養所(現在、この保養所は廃止されている)があり、尋ねると入漁券を扱っていたので早速購入した。入漁料が消費税込みで¥315と聞かされて、そのあまりの廉さに驚いた。理由を尋ねると、イワナの固有種保護のため、環境庁と漁協が話し合って一切放流をしていないからだということだった。その代わり、産卵床を作り立ち入りを禁止したり、1本を除いて全ての支流を禁漁にしたりして在来種の保護に努めているということだった。ちなみにイワナの種類を尋ねると、判らないが雑魚川固有の純粋種に間違いないとのことだった。イワナの種類の識別は専門家にも異論があり、素人の私には勿論正確なところは判らないが、釣ったイワナを見た私の感じでは、オレンジ色の斑点が明瞭で、白点が薄いなどの特徴から、ヤマトイワナではないかと思われる。
徹夜の疲れが出て眠気を感じた。私は先程目をつけておいた駐車スペースで、仮眠を取ろうと思い引き返した。クーラー・ボックスから弁当と冷えたお茶を取り出して昼食を摂った。仮眠しようと、シートをフル・フラットにして横になり目をつぶったが、体はくたくたに疲れているのに、灰の下で何時までも消えない燠(おき)のように神経が昂ぶって眠れない。30分ほど目を閉じていたが、どうにも眠れないので起きだして、先程上った小道を降りて行き、足元から釣り始めた。
大渕を過ぎると、川幅が再び狭まり、両岸から高い崖が迫ってきた。頭上を覆う木の枝が陽射しを遮り、辺りは薄暗かった。遡上ルートを探しながら上って行く途中で、左手(右岸)から水量のある支流が流れ込んでいるのが見えた。(後に、これは雑魚川の分流で、遡ると雑木林の中に造られた産卵床に通じていることが判った。)私は、落差の大きな強い流れの中を、右に左に渡り返しながらこの難所を遡って行き、分流の流れ込みにエルクヘアー・カディスをキャストした。今度は、派手なライズがあり、27cmの大型のイワナががっちりと鉤掛かりした。 |
|
王餘魚(かれい)谷の僥倖 |
||||
|
柳原 釣童 1990年の4月末、私は四国徳島の海部川に釣りに出かけた。初日は途中寄り道をして、吉野川の支流、穴吹川や貞光川を覗き、翌日は海部川の支流・大木屋谷で釣り、三日目は高知の伊尾木川に行ってみた。
午後一時の南国の陽射しは強く、空は抜けるように青かった。今日は5月1日、丁度連休の狭間であった。明け方はかなり冷え込んだが、日が昇るに連れて気温が上がり、河原を歩くとフライ・ベストの下の背中が、じっとり汗ばむほどの陽気となった。
陽は、まだ沈んではいなかったが、後三十分もすればライズが始まるので、これ以上あちこち釣り場を捜し回っている余裕はない。「仕方がない、この渓でイブニング・ライズを狙うか」と、渓沿いの道を少し登って渓への降り口を捜し始めたが、谷が深くなかなか降り口が見つからない。200mほど登ったところでどうにか下降できそうなところを見つけて、杉林の中を降りていった。河原に降り立つと遡行は容易であった。本流との出合い付近の険悪さとは打って変わって穏やかな渓相となった。釣り初めてすぐにライズがあり、15cmぐらいの小型のアマゴが釣れた。遡るにつれて渓は開け、右手に護岸があり、下から見上げると公園か、庭園のようで、河原に降りる石段が見えた。周りが少しずつ暗くなり、フライをブルー・クイルからライト・ヘンドリクソンに取り替えた。 ©2002 (無断で転載することを禁じます) |
|
風の盆とイワナ釣り |
||
|
柳原 釣童 「風の盆」という祭りがあることを知ったのは、今からもう十数年も前のことだった。 私はその時以来ずっと、一度はその祭りを見てみたいと思い続けてきた。と言っても、私が特別に祭り好きだという訳ではない。むしろ、あまり興味の無い方かも知れない。こんな私をこの祭りに駆り立てるものは一体何なのだろう。「風の盆」という言葉の持つ謎めいたロマンティックな響きと、山奥の里で、ひっそりと行なわれる秘密の儀式的なイメージが、私の心を引きつけて止まないのかも知れない。最近でこそ、多くの人々に知られるようになってきたが、「越中おわら節」の節の難解さと同様、この祭りには、今なお、どこか他国者を拒絶するようなところがある。 私は釣りの支度をしながら、まだ見ぬ八尾の町に思いを馳せていると、ふと、昔訪ねた郡上踊りと郡上八幡の町のことを思い出した。そう言えば、井田川沿いの八尾の町と、吉田川沿いの郡上八幡の町、この二つの町は、豊かな清流に恵まれた「川の町」であることが共通している。祭りに惹かれたと言うより、「川の町」に惹かれたのかも知れなかった。 1994年の9月、折よく仕事の都合がついたので、休暇を取り、長年の念願であった「風の盆」を見に行くことした。そう言えば、この祭りが人々を遠ざけてきた理由に、地理的な辺鄙さとともに、この9月1日〜3日という祭りの期日があるものと思われる。 東京八王子の自宅を出て、富山の八尾の町へ向かう時、実際よりずっと遠くへ行くような、同時に、過去の時代へ時間を遡るような、不思議な感覚に捉われた。八王子インターから中央自動車道に入ったのは、午前零時を廻っていた。岡谷ジャンクションで長野自動車道に入り、このときはまだ長野自動車道は上越ジャンクションまで開通していなかったので、須坂インターを出て国道18号線を北上し、北陸自動車道の上越インターを目指した。このルートとは別に、松本インターで降り、国道158号線を通って北アルプスを越え高山に出るルートもあるのだが、時間的には高速道路を利用した方が早いので、北陸自動車道経由を選択した。 富山インター手前のパーキングエリアで仮眠を取り、午前八時頃目を覚まし、前夜国道18号線沿いのコンビニで買っておいた弁当で朝食を済ませた。富山インターを出て、国道41号線を南下し、途中で県道に入り八尾の町を目指した。県道の両側には、水田を中心とした豊かな田園風景が広がっていた。 八尾の町に着いた。JRの八尾駅を覗いてみた。駅前の通りには、人気のない屋台がずらりと並んで、提灯や品書きの短冊、「おわら風の盆」と書かれた幟などが風に揺れていた。祭り二日目の町の光景は、盛り場の朝に似ている。初日の朝の緊張感はなく、気だるさと虚脱感が漂っていた。 駅前の小さな広場に、東京からテレビ局のクルーが取材に来ていて、カメラの前で見覚えのある若い女性のキャスターが盛んに喋っており、周りには小さな人垣ができていた。駅前に祭りの案内所があったので、そこで祭りの紹介のチラシを貰った。チラシにはおわら風の盆の由来、三日間の祭りのスケジュール、町の案内図、JRやバスの時刻表などが、細かい活字でびっしりと書き込まれていた。 そのチラシには次のようなことが書かれていた。文献としては残っていないが、口伝によると、300年も昔、八尾の町の開祖で米屋少兵衛と言う人の子孫が保管していた、町興しの起源に関わる文書が町に返還された。これを祝って、町の役所が、三日間、唄、舞い、音曲は言うに及ばず、その他いかなる賑わいごとでも咎めないから面白く町内を練り廻れと言うお触れを出した。人々は、思い思いの装いをし、三味線・胡弓・太鼓・尺八などの伴奏で、昼夜の別無く、三日間町内を練り歩いたのがこの祭りの由来だと言うことだ。その後、この祭日三日が、盂蘭盆三日に変わり、やがて二百十日の厄日に豊穣を祈る風の盆へと変わったらしい。 私は駅前から引き返し、井田川に掛かる十三石橋を渡って、川沿いの道を車で走ってみた。気がついたら、町をほぼ半周して、町の外に出てしまっていた。祭りが催される町の中心部は高台の上にあるらしい。 八尾の町は、町全体が一つの堅固な山城のようだ。井田川、別荘川、野積川がお堀のように町を取り囲んで流れ、背後には小高い山が迫っている。町に入るには、必ずこれら三本の川に掛かる橋のどれかを渡らねばならず、これらの橋は重要な関所の役目を果たしている。風の盆が催される間、初日、二日目はPM3:00〜AM1:00、三日目はPM7:00からAM1:00と厳しい車両の交通規制が敷かれるが、これらの橋を押さえることによって、非常線のように車の通行を完全に遮断することができる。 二万の町の人口が、この祭りの三日間は二十万に膨れ上がると言われているが、道幅の狭い、空地の少ないこの小さな町は、車の通行を規制しないと、パニックに陥るに違いない。祭りの期間中、もし火事にでもなれば、車の規制がなければ大惨事を招くのは目に見えている。 おわら風の盆は、このような地理的、物理的な限界から、将来も、今以上の観光客の受け入れを拒むに違いない。八尾の町中の、部屋から踊りが見物できる旅館は、一年も前から予約済みということで、急に思いついて出かけてきた私などが、泊まれるところなどあろう筈も無かった。 祭りが始まる三時まで町にいても仕方がないので、私は町を離れて山へ向かった。八尾の町は初めてなので、釣り場についても、雑誌やスポーツ新聞の記事をいくつか読んではいたが、勿論よく分からない。 神通川の支流・井田川は、八尾の町で掌をぱっと開いたように、五本の支流に枝分かれする。久婦須川、別荘川、野積川、仁歩川、室牧川と東西に並んだ五本の指は上流を目指し伸びていく。久婦須川の東には神通川の本流が流れ、室牧川の西には、神通川の支流・山田川、庄川の支流・利賀川、それに庄川の本流が並走して流れている。 私は、今いる地点から一番近い野積川を覗いてみた。その年は全国的に極端な雨不足で、生活用水にも事欠く地域が多く、ここ富山もご多分に洩れず、野積川の水量は少なかった。しばらく上流へ遡ってみたが、とても釣りになりそうもなかったので引き返した。室牧川上流の大長谷川か、山田川上流の百瀬川のどちらかで釣ることにして、室牧ダムの上流へと車を走らせた。 室牧川は室牧ダムで名を改め、ダムより上流は大長谷川となる。大長谷川に掛かる茗ケ島橋を渡ると、栃折という集落で大長谷川上流への道と、山田川上流・百瀬川への道に別かれる。私は一瞬迷ったが、百瀬川への道を選んだ。
菅沼ダムまでの百瀬川は、切り立った峡谷だったが、ダムを越すと急に視界が開け、それまでの険悪さが嘘のように穏やかな平瀬に変わった。渓流の緊迫感はどこにも無い。私は百瀬川の様子を見ながら、川沿いの道を上流へ車を走らせた。 上百瀬にある合掌文化村は、夏期に世界演劇祭で賑わうと言うことだが、この時期はひっそりと静まり返って、その面影はない。上百瀬の集落を過ぎると、ここぞというポイントには、必ずと言って良いほどRV車が停まっており、釣り人が非常に多い。日尾谷の合流点の手前で、三人連れのフライ・フィッシャーが丁度川から上がろうとしているところに出合ったので、そこからまた1kmほど上流へ行った。渓を覗いてみると、イワナの魚影はあるが、水量が少な過ぎてとても釣りになりそうもない。仕方なく引き返し、日尾谷と滝口谷の中間辺りの、堰堤から釣ることにした。堰堤の上の河原に車を駐め、少し早めの昼食をとった。時計を見ると午前十一時を廻っていた。 堰堤の上のプールでフライを投げてみたがライズは無かった。この川は、元来非常な暴れ川なのか、それとも、それほど遠くない過去に、大きな出水があって河川の改修工事が行なわれたのか、堰堤が連続し、堰堤と堰堤の間は土砂が堆積して、自然の渓流の面影はなかった。渓魚の放流量は多いとみえ、釣り人に人気があるようだが、私にはあまり魅力が感じられない。 朝からカンカン照りで、非常に暑くなった。山の向こうに入道雲が顔を出した。夕立が来るかも知れない。1kmほど釣り上がったが、途中二度ばかり魚影を見かけただけでライズは無かった。 しばらく釣り上がっている中に、渓相は多少好転し、川幅が狭まり、落差が出てきた。両岸から伸びた立ち木の枝が水面に影を落とすようになった。ふと気がつくと、辺りは薄暗くなっていた。ポツポツと雨が降り出し、すぐ近くで雷鳴が轟いた。雲の様子を見ると、どうやらこの辺りは雷雲の中心から外れている様子なので、雨が止むまで樹陰で待機することにした。 今回の釣行の目的の一つは、つい一週間ほど前に購入したパートリッジのバンブーロッドの調子を試してみることだった。7.5フィートの#4、デュラケーンのロッドで、実際に使ってみると調子はスローで、持ち重りがした。使う前から調子がスローなのは解かってはいたのだが、釣り始めてすぐに、今日のスレた相手の速いライズには合わせが遅れ、とても歯が立ちそうにないと悟ったが、ロッドを取り替えるのが面倒で、そのまま使っていた。しかし、バンブーロッドに雨というのは最悪の状況だった。雨足が強くなり、私は時々乾いたタオルで雨に濡れたロッドを拭った。 近くにある林道の表土から濁りが生じるのか、流れは見る見る中に濁って白っぽくなった。そのうちに雨足は弱まり、濁りも薄れてきた。濁るのも早いが澄むのも早かった。再び釣り始めて、小さな淵の落ち込みで、ブラウン・ハックルの#14にライズがあった。釣れたのは20cmを少し超えた小型のイワナ。濁りが出たので警戒心が薄れ、フライに飛びついたものとみえる。とにかく、これが今回の釣行で初めての獲物だった。 なんとか型を見ることができたので、漸くこのポイントに見切りをつけることができた。長時間釣りをしていて全く釣れないと、それまでの努力が無駄になる気がして、何としてでも型を見て努力が無駄でなかったことを証明したいと焦ってしまう。或いは無駄で無かったと自分で納得したいだけなのかも知れないのだが、これ以上釣り続けても、おそらく釣れないだろうと内心では承知してはいても、一尾を釣ることに執着して、その釣り場になかなか見切りをつけられなくて、いっそう無駄な時間を費やしてしまうということが、今まで私にはよくあった。今回は、曲がりなりにも長時間の努力が報われた形だが、考えてみると、時間をロスしたことに変わりはなかった。 見切りをつけるのは、早いに越したことはない。これは、別に釣りに限ったことではないのかも知れない。賭け事を始め、投資にしろ、恋愛にしろ、諍いにしろ、泥沼に堕ちたり、深手を負う前に、諦め、見切りをつける。── 分かってはいても中々出来ないことではあるが・・・。 上百瀬の合掌文化村の近くまで戻って、利賀少年自然の家の上手附近から再度入渓した。河原はブルドーザーで均されたように平坦で、短い間隔で低い堰堤が連続する酷い渓相で、とても釣れる気がせず、すぐに諦めて釣りを中止した。道路を歩きながら、今晩泊まるところはないかと、旅館や民宿を探したが中々見つからない。やっと一軒民宿の看板を見つけて、声を掛けたが留守のようで返事が無い。宿探しは諦め、釣り場の状況も悪そうなので、今夜の祭りを見たらその足で東京に帰ることに決めた。 車に戻って、この後どうしようかと考えた。百瀬川は何処へ行っても水不足で釣れそうには思えなかった。もしかしたら、八尾周辺の数ある渓の中で、最悪の選択をしたのかも知れなかった。 時計を見ると三時半だった。これから移動して夕方狙える釣り場は限られている。地図を見ると利賀川が近そうだったので、すぐに出発した。楢尾トンネルという真新しいトンネルを抜けると利賀村だった。利賀村の中心部と思われる、村役場のある辺りからは、谷があまりにも深すぎて、利賀川を見ることが出来なかった。地図を見ると2kmほど上流へ行くと、川が道路に沿って流れているようなので、上流へ向かって車を走らせた。細島から阿別当にかけての利賀川は、護岸された土手が続き、平坦な河原を細々と川が流れていた。あまり冴えない渓相なので、釣る気になれず、どんどん上流へ上って行った。 千束ダムの上流で渓相が改まり、水量もまずまずだったので釣ろうと思ったら、そこにも四駆が駐まっていた。仕方なく、また上流へ向かった。上流へ進むにつれ谷が深まり、道路脇の切り立った崖は岩肌を露出させ、路上には大小様々な落石があちこちに転がって、酷く荒涼として厭な雰囲気だった。 こんな光景が水無ダムまで何キロも延々と続いた。車を走らせながら、今にも崖の上から大きな岩が落ちてきそうな気がして、背筋が寒くなった。私は、滅多にこんな胸騒ぎを覚えたりすることは無いので、もしかすると、この辺りで過去に車の転落事故でもあったのかも知れないなどと、思ったりした。 水無ダムに着いた。ダム右岸の水無川の流れ込み附近から入渓しようとしたら、またしても車が駐まっており、腹を立てても仕方がないので、更に上流に行き、2kmほど遡った地点で車を停め、渓を覗いて見た。水量も、川幅も、まずまずだったので、早速支度をして釣り始めた。時間はもう五時近くになっており、雨がポツポツ降り始めて、辺りはかなり薄暗かった。
大型は出なかったが、中小型のイワナが次々と釣れた。魚影はかなり濃い。しかもネイティブばかりだ。後で、この辺りの釣りに詳しい人の話を聞くと、この渓は、普段は水量が多すぎてとても竿を出せる釣り場ではないそうで、このときは、折からの渇水が幸いして好い釣りができたのだろうと云うことであった。雨足が強まったので、十尾ばかり釣ったところで、日没には未だ少し間があったが、納竿した。八尾までの長い道程を考えると、あまり暗くならない中に山を下りたかったのだ。 八尾の町に着いた時には、とっぷり日が暮れて、辺りは真暗だった。町へ通じる道路の入り口には、車の進入を規制する監視員がいて、街灯もない暗闇の中で、通りがかる車に迂回するよう指示を出していた。迂回路には、辻毎の電柱や壁に、行き先を示す矢印を書いた紙が貼られ、その矢印に従っていくと大きな通りに出た。そこの交差点は丁字路になっていて、右方向は八尾の町へ通じているらしく、観光バスや臨時バス、乗用車が行列を作って、ノロノロと動いていた。左方向の富山方面への道は空いていた。 大通りの両側は駐車禁止となっていたので、私はさっき通った迂回路に戻って、路地に車を留めて八尾の町へ歩いて向かった。乗用車が町へ入れないのは、午前中、八尾の町を通った時に確認していた。丁字路から、大きなカーブを描きながら下る長い坂道を下って行くと、臨時の検問所があり、車の列の先頭で、トランシーバーを持った交通整理員が車を止めて、一般車は右折して迂回させ、大型バスだけを、間隔を置いて発進させていた。 数百米ある坂道を下って来る間、誰ともすれ違わなかったこと、盆踊りにつきものの、賑やかな唄声が聞こえてこないことに気がついた。まだ夜八時を廻ったばかりだというのに、検問所先の井田川に架かる八尾大橋を渡る間も、誰にも会わず、街の灯りを反射して、暗闇の中でキラキラ光る川面を渡ってくる夜風が、ひどく涼しく感じられた。 橋を渡ると広場があり、その広場には大型の観光バスが何台も停まっていた。それらのバスからは大勢の観光客がどやどやと降りて来た。バスの乗客達は、それぞれ数人ずつのグループになって、坂道を登って行く。私はその集団の後に付いて行った。かなり急な、狭く長い石段を、二カ所登り切ると、急に人の通りが多くなった。 そこは八尾の町のメイン・ストリートらしかった。道幅は5mも無いように思われたが、道の両側には、二階建ての商店、旅館が行儀よく軒を連ねていた。明かりは暗い雪洞に街灯、建物の門灯、窓から洩れる明かり、商店のショーウインドウの明かりなどだけで、他に特別な照明などはなく、道幅一杯に行き来する夥しい人々の顔も、判然としなかった。 ひどく静かな祭りだ。スピーカーから噴き出してくる、人の神経をタワシで擦るようなあの大音響は無い。肩を触れ合わんばかりに人で溢れているのに、人々は大声を出したり、笑ったり、大きな音を立てたりしなかった。まるでパントマイムを見ているような、静かな雑踏だ。お祭り特有の陽気さ、騒々しさ、猥雑さと言うものがまるで感じられない。大声を出すのが憚かられるような雰囲気すらある。思索的と言うのは言い過ぎかも知れないが、普通の祭りとはどこか違った厳粛な空気が漂っている。 十数人ほどの編笠に、揃いの法被を着た一団が通りかかったかと思うと、いきなり踊りが始まった。高校生ほどの若い男の踊り手が、生真面目に黙々と踊っている。伴奏も、そのグループの中の数人が演奏していた。胡弓と三味線と太鼓と唄。電気的に増幅されない、等身大の音色と響きがそこにはあった。何を唄っているのか耳を澄まさないと聞き取れないほど小さな唄と演奏。街灯や雪洞や家々から洩れてくる僅かな明かりを受けて、仄かに揺れ動く人影が浮かび上がり、夕空に舞う蜉蝣のように、ひっそりと踊っている。 踊りの終わりもまた、唐突だった。踊り終わった一行は、雑踏と夜陰に紛れてそそくさと行ってしまった。このような踊りの小さな集団が、町のあちこちで見られた。編笠に色とりどりの浴衣を着た女性の姿が、ひどくなまめかしくて思わず見とれてしまう。 気がついたら、私は商店のショーウインドウに押しつけられていた。狭い露地で踊りが始まると、見物の人垣が出来て、踊りのスペースを空けるために、周囲の見物客は必然的に両側に押し退けられ、身動きもままならない状態になってしまうのだ。踊り手は、抑圧されたエネルギーを、踊ることによって発散させているのかも知れない。その踊り手に、自分を投影させることによって、見物客もまた、抑圧された自分を昇華させているのだろう。踊る者、見る者、それぞれ非日常的な時間と空間を共有し、共有することである種の後ろめたい連帯感で結ばれている。 男と女が、大勢集まって踊っていたら、それがお祭りだ。これは何も人間に限ったことではない。蜉蝣の舞い、蚊柱、シオマネキの踊りもまた立派なお祭りだと私は思う。 私は祭りの終わりを見届けることなく、八尾を後に帰途についた。祭りには、いつ参加しても、いつ抜けてもいい自由がある。(1995年8月15日)
©2002 (無断で転載することを禁じます) |