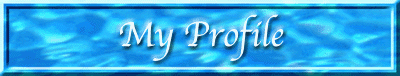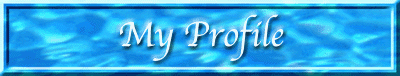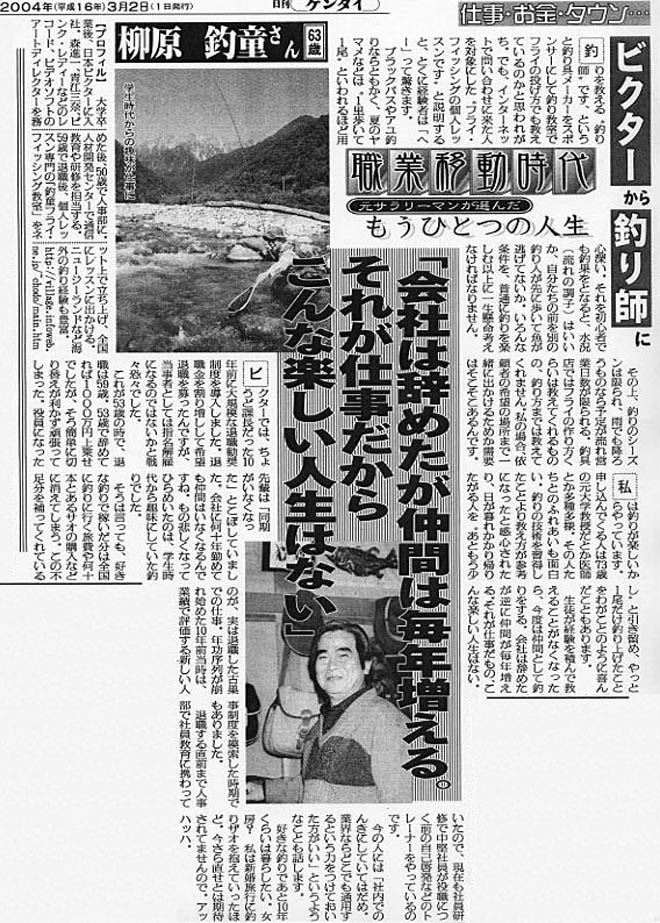|
釣りをする金と暇があるということは、考えて見れば最高に贅沢なことではないだろうか?釣りに関心のない人には一笑に付されるかも知れないが、これが釣りではなくて、他の遊び、趣味だとしたら、もっと納得する人が増えるに違いない。
この不況の世の中、住む家があり、一定の収入があるということは、幸せなことだと熟々思う。町を歩いていて、所謂ホームレスと呼ばれる人たちを見て、まかり間違えば自分もこうなっていたかも知れないと考えると、益々その思いは強くなる。
私は、アイザック・ウォルトンや幸田露伴、その他有名・無名の釣り師たちの人生哲学、世界観、もっと具体的に言えば、彼らが人生で何に価値を認め、何に価値を認めないのかという「価値観」が知りたかったのだが、彼らは、こういう問題について大上段に構えるのが憚られるのか、或いは愚かしく思うのか、具体的に語ってはくれない。
唯一冊だけ本の所持が許されるとしたら、私は躊躇わずマルクス・アウレーリウスの「自省録」を選ぶだろう。それほどこの本は、私にとって大切な本であり、私の価値観を決定づけた本なのである。マルクス・アウレーリウスは、ローマ時代を通じて唯一人の、皇帝にして哲学者であった人で、恐らくローマ時代のみならず、世界史上唯一の帝王・哲学者である。私が初めて「自省録」(神谷美恵子訳・岩波文庫)を読んだのは大学2年の時で、それ以来折りに触れてこの本を繙いている。本の内容については、今更説明するまでもないと思うので割愛するが、富や権力や名誉というものが、マルクス・アウレーリウスにとって何の意味も無いもの、少しの満足も齎さないものであったという事実に、私は深い感銘を受けた。元来ストイックな傾向があった私にとって、マルクス・アウレーリウスは最高の手本であり、理想像となった。
ローマ皇帝ほどの富と権力と名誉を以ってしても、人の心を満足させることが出来ないのなら、今の世の中どれほど出世しても、得られるものは多寡が知れているし、どういう職業に就こうと、マルクス・アウレーリウス的な、高潔、誠実な生き方をしたいと心に決めた。そのとき以来、富、権力、名誉などと言うものは、私にとって、大して価値のあるものでは無くなってしまったのである。私が、価値を認めるのは、絶対的存在である神と、清廉、温和、つつましさ、雄々しさ、神を畏れること、惜しみなく与えること、悪事をせぬのみかこれを心に思うさえ控えること、簡素な生活をすることなど、すべて美徳と呼ばれるもの、文学、美術、音楽、哲学などの知的創造物、それと純粋な意味の遊びである。私が価値を認めないものは、先に述べた、富、権力、名誉などの他、すべての悪徳、すべての生理的欲求などである。
私は学生時代に、どのように生きるかということは決めたが、どうやって生きるか(生活するか)、どういう職業に就こうかと言うことは、呑気な話だが殆ど考えもしなかった。卒業間際になって、慌てて就職先を探したが、ろくに授業にも出ず、成績も悪かった(家にいて本ばかり読んでいて、卒業するのに6年かかった)私に、大した就職先がある筈も無かった。已むなく、熱海にあった小さな旅行関係の印刷会社に、海が近く釣りが出来そうだと言う不真面目な動機で就職したが、その年の暮れに上司と衝突して退社してしまったのである。
その後、あるレコード会社に再就職したが、どういう会社であれ、営利を目的とした企業であるから、金儲けに後ろめたさを持つ人間にとって、居心地満点と言う訳にはいかなかった。自分の価値観と企業の価値観の差は、ある程度予測はしていたが、企業で働く人間との価値観の差は殆ど絶望的と言えるほどのものであった。私は職場の人間と、勤務時間中は言うまでも無く休憩時間でも、文学や、哲学や、美術などについて話し合ったことなど一度も無かった。私は仕事を通じて知り合ったイラストレーターや、映画や音楽の評論家たちと、時折オペラや、絵画、文学の話をして、私の渇望を辛うじて癒したのである。私の周りの人間たちは、まるでタブーに触れるかのように、仕事以外の事柄については沈黙を守っていた。後年、職場が変わったりして、話の通じる幾人かの友人を見出したが、彼らは例外的な少数者だった。
私自身、会社生活においてマルクス・アウレーリウスのように、すべての悪徳から遠ざかるなどと言うことはとても出来なかった。それどころか、心がすさんで怒りに駆られて声を荒げたり、自分の感情を露骨に顔に出したり、家に帰っても不機嫌でいたりしたこともあった。それでも、人に諂ったり、阿ったり、陰口を叩いたり、陰謀を企んだり、人を裏切ったりしたことは一度も無かった。この程度の非悪徳ですら、貫き通すことが難しいのが、ビジネス社会の現状である。退職するまで女房にも話さなかったことだが、私はある時、先輩に義理立てして昇進の内示を蹴った事があった。それ以来、私の昇進の路は閉ざされてしまったが、私はそのことについて別に後悔したことは無い。自分の価値観に従って行動するのが、私の美学だからである。私は、自分の能力が人より劣っていたとは思わない。何故なら、仮にも一流と言われた会社で、私は三十歳で課長になっていたからである。私は、会社が私の力を必要とした時には、常に全力投球をしてきたし、その後もずっとそうしてきたのである。
今や終身雇用も怪しくなってきたが、終身雇用とは、考えて見れば、たかが金儲け目的の私企業に、一人の人間が生涯自由を束縛され、忠誠を誓わされ、自尊心を傷つけられ続けると言うことでは無いのだろうか?僅かな生活費を稼ぐために、自分の魂を会社に売り渡してしまっていいものだろうか。職場では人間関係における不公平、依怙贔屓、屈辱に耐え、社内外の不正に対しても、自己保身のために抗議すら出来ず、少しでも高い地位に就きたいと互いに足を引っ張り合う。ひたすら会社のため、家族のために盲目的に仕事をする。自分にとって信じられるもの、頼りになるものは金銭だけである。金銭がすべて、金銭こそ全能の神、と言う拝金教が我が国の宗教なのだ。人間にとって何が大切で、何が大切でないか、言い換えれば何に価値があり、何に価値が無いかと言う価値観の喪失こそが、現在の社会を荒廃させてしまったのだと私は思う。
最近行われた大統領選挙で、アメリカは全世界に醜態を晒したが、最終的にゴア候補が敗北を宣言して決着した。そのとき彼は、神の名のもとに国民に結束を呼びかけたが、これを見ていて正直言って、この国にはとても敵わないと感じたのである。物質万能の社会のように見えるこの国の根底に、神(と言う絶対的価値)を信じる敬虔な精神があり、大統領候補が堂々と神の名を口にすることが出来るのであるから。
翻って我が国は如何だろう。政治家や、企業経営者など、権力闘争や金儲けに明け暮れる一部の連中を例に取るまでも無く、ごく普通の市井の庶民達は、日常生活の中で他人より1円でも多く収入を得ようと狂奔する。ふと我に返ると、自分の人生には安らぎ、楽しみと言うものが何も無かったことに気付く。そのことに気付かぬまま死んでしまう者も数多い。生存本能と言う盲目意志によって突き動かされているだけで、時として集団自殺してしまう鼠の群れと一体どこが違うのだろう。
このような、確固とした価値観を持たずに日常生活を送っている人間が、家で自分の子供を叱り、真っ当な人間になるように教育するなどと言うことが、果たして出来るものだろうか?「いじめ」、「リンチ」などというものは、結局は協調性を無理強いする大人社会の縮図に過ぎない。家庭内暴力、動物虐待、親殺し、子殺し、幼児虐待、バラバラ殺人、保険金殺人、集団リンチ殺人、無差別殺人、公務員の汚職、警官や教師たちの犯罪、こういったおぞましい出来事は、価値観を持たぬ大人たちが、自分の子供たちに善悪の区別さえ教えられなくなったことの、当然の帰結では無いだろうか?
この社会に生きている限り、この社会の出来事と全く無関係でいられる筈は無い。社会の荒廃について、すべての人間が責任を負わねばならぬとしたら、私もその例外ではあり得ない。しかし、残念ながら私に出来ることは、この社会の荒廃に手を貸すことを控えると言うことだけである。だが、もしすべての人間が、荒廃に手を貸さなくなれば、荒廃の進行を食い止めることが出来るだろう。
私は、余暇に釣りをすることで、日常生活のバランスを取ってきた。会社勤めが日常生活なら、釣りは非日常の生活である。釣りを含め、遊び、趣味と言う非日常生活には、リクリエーション(自己の再創造)と言う大きな効用があり、このリクリエーションが行われないと、人は正気を保つことが出来ないのではないかと私は考えている。正直に言えば、仕事が上手くいっている時には、釣りをしていても楽しかったし、その逆も言えたのであるが、釣り場では、私は努めて仕事その他日常生活のことを考え無いようにした。そのうちに努力しなくても、日常生活のことはさっぱり忘れてしまうことが出来るようになった。
プロの釣り師になったある高名な作家が、釣り人の皮膚の皮を剥ぐと、その下には醜悪、下劣、珍妙、陰惨と言った妄念や妄想の類が満ちみちていて、思わず顔を背けたくなるほどだと言う意味のことを書いている。最初私がこれを読んだ時、この作家の気持がどうしても了解出来ず、この人は一体どういう精神構造の持ち主だろうと訝しく思ったものだ。後年になって、この人がスポンサーに費用を提供して貰って、仕事として釣りをしていたのでこういう精神状態になったのだということに思い当たり、納得したのである。粋に、自腹を切って釣りを楽しむ釣り人は、決してこのようなおどろおどろしい気持で釣りはしないものである。勿論、釣り師が釣れなくてイライラしたり、焦ったりすることはしょっちゅうあるが、唯それだけのことで、人が顔を背けたくなるような醜悪な妄想などを抱いたりはしない。
渓流釣りが解禁になり、冷たさの残る風を頬に受けて、岸辺に咲く色とりどりの梅や桃の花を眺めながら釣りをしていると、私は、また新しい春が迎えられたことを実感し、しみじみと生きていて良かったと思うのである。夏場、アスファルトも溶ける炎熱の都会から遠く離れて、北アルプスの残雪を間近に望み、気の合った友人と他愛の無い自慢話を交わしながら岩魚を狙って釣り上がる。河原に咲く草花の上で、白や黄色の蝶たちが舞い、近くの森からは郭公の鳴き声が聞こえて来る。そこには日常生活の煩わしさや、暗い世相を偲ばせるものは何も無い。
なかなか魚が釣れずイライラしてくると、私は「こうやって釣りが出来るだけでも、幸せなことじゃないか」と、自分自身に言い聞かせるようにしているが、そうすると不思議に気分が静まって、その後すぐに魚が釣れたりするのである。また、その日初めての魚をやっとの思いで釣り上げた時、その魚がひどくいとしく思われて、「有難う」と言いながらその魚の頭を撫でてやり、鉤を外して「ご苦労さん」と言って逃がしてやったりすることもある。釣り人たちは、思い思いに自然の美しさを愛で、魚たちとの出会いを楽しみ、至福の時を過ごすのである。
このように、日常生活と背中合わせに、非日常の幸せな世界が存在しているのである。人は皆、その気になりさえすれば桃源郷に入ることが出来る。この世の楽園は、「山のあなた」では無く、すぐ身近に「青い鳥」のように存在しているのだと私は思う。
|