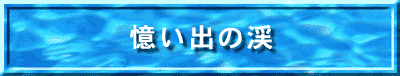
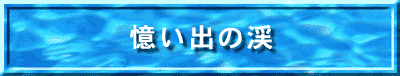
![]() 8/15 憶い出の渓<大分川支流・阿蘇野川> 追加!
8/15 憶い出の渓<大分川支流・阿蘇野川> 追加!
|
憶い出の渓 私は30年もの間フライ・フィッシングを続けてきた。これだけ続いた訳は、フライ・フィッシングが楽しいからである。遊びとしての条件を、フライ・フィッシングは完璧に満たしていると言って良いだろう。楽しい上に奥が深く、全く飽きが来ないのである。 私はこれまで数多くの渓を訪ね、釣りをして来た。母親のように優しい渓、父親のように厳しい渓、穏やかな渓、険しい渓…どんな渓にもそれぞれ個性があり、又、訪ねる季節、天候などによっても、それぞれ異なった表情を見せてくれた。得意の渓、満足の渓、後悔の渓、失意の渓…どの渓も私の脳裏に深く刻み込まれ、記憶の中で絶えることなく流れ続けている。 最近私は遠出する機会がめっきり減り、嘗て釣り歩いた渓を再び訪ねることが出来るかどうか覚束なくなって来た。そこで私は記憶の中を流れている渓を訪ねてみることにした。 私は大分県出身の父と、愛媛県出身の母との間に大阪府で生まれ、四国や九州で育ち、山口県出身の女房を持つなど、西日本とは縁が深く、関東・中部を除けば西日本で釣る機会が多かった。私の記憶の中を訪ねる旅も、西日本の渓が多くなることだろう。 取上げる渓は、私が実際に釣ってみて、釣り場として価値が高いと判断した渓である。半日コース以上の渓を選んだが、それより短いコースも含まれている。取り立てて選択の基準があるわけではなく、強いて言えば、私の独断と偏見、私の好みで選んだものである。 |
|
1.四万十川水系 梼原(ゆすはら)川支流・大田戸川(高知県) |
||
|
四万十川は中流の大正町の田野々で、渡川(四万十川)と梼原川に大きく枝分かれするが、流域面積がやや広い渡川が四万十川の本流とされている。四万十川は、ダムの無い河川として有名であるが、梼原川には初瀬ダム、津賀ダムなどを始め、大きなダムが幾つもあり、この点では四万十川を代表する河川としては相応しくないかも知れない。しかし、渓流釣りの観点から見ると、渓流釣りができる支流を数多くを持っている梼原川の方が、断然渡川に勝っているように私は思う。
高知県と愛媛県を跨いで、四国カルスト台地が広がっているが、梼原川はこのカルスト台地の南面を水源としている。梼原川は、最上流の越知面(おちめん)と言うところで同じような規模の3本の支流に枝分かれする。右又が大田戸川、中又が永野川、左又が田野々川である。 大田戸川は、ごく小さな、落差の少ない穏やかな渓である。私は、'92年の4月下旬にこの渓を訪ねたが、そのときは、岸辺の枯れた葦の間から緑色も鮮やかな葦の若葉が伸びており、その若葉に混じって、点々と黄色い菜の花が咲いているのが見えた。水際まで密生する葦が清冽な流れを狭め、私は川通しの釣りを強いられたが、川底は平坦で流れも緩く、徒渉は全く苦にならなかった。
しばらく鬱蒼とした暗い木立の中の遡行を続けていると、急に視界が開け、見上げると正面の奥にカルストのなだらかな稜線が見えた。私は、天上界の別天地に来てしまったかと錯覚した。フナやメダカを追った子供の頃の原体験が甦ったような、懐かしい光景がそこにはあった。私はそれまで、これほど長閑な渓でフライ・フィッシングをしたことは無かった。 私は3時間ほど釣って満足し、納竿した。 (2001/3/13) |
|
2.一ツ瀬川支流・大藪川(宮崎県) |
||
|
新緑の頃の渓流はどこの渓流も美しいが、この日の大藪川はとりわけ素晴らしかった。 花にはいろんな花があるが、すべてが同じように美しいとは限らない。しかし新緑は、木や草の葉を問わず、瑞々しい生命感に溢れていて、どんな若葉も並べて美しい。 宮崎県は、五ヶ瀬川、耳川、一ツ瀬川、大淀川、小丸川などの傑出した渓流釣り場を擁し、九州一の渓流王国を誇っている。大藪川は一ツ瀬川の支流で、九州山地南部の三方岳(1476m)を水源としている。
私が大藪川を訪ねたのは、‘93年の5月の初旬だった。私が大藪川を訪ねる2日前、九州南部は大雨に見舞われた。実は私は、大雨の翌日現地に着いて、川内川(せんだいがわ)の源流や、大淀川支流・本庄川などを覗いて見たのだが、増水していて釣りはおろか、渓に近づくのも恐ろしいような状態だった。私はもっと北に行けばそんなに雨は降らなかったかも知れないと考え、狙いを一ツ瀬川に変えて悪路の山道を延々と移動し、西米良村の村所(むらしょう)と言うところに着いて一泊した。 翌朝、一ツ瀬川の様子を見ると、本流はかなり増水していた。午前中は、村所から近い井戸内谷というところで竿を出してみたが、この渓も渡渉が侭ならない状態で釣果は無かった。午後、私は大藪川に移動した。大藪川も本流との合流点付近は水が太く、私はまるで源氏に追われる平家の落人のように、増水をのがれて椎葉の山奥へと逃げ込んだ。 入渓点を探しながら、私は車で大藪川沿いの山道を登って行った。登るに連れて、道は大藪川から遠く高く離れてしまった。私は道端に車を停め、様子を見ようと車を降りた。私は、眼下に広がる光景の美しさに思わず息を呑んだ。百数十メートル下の、箱庭のような谷底を大藪川が流れ、その上に赤い鉄の橋が架かり、細い山道が橋の前後に延びていた。谷全体が新緑に包まれ、山裾が左右から幾重にも谷底に向かって落ち込んでいた。見上げると、遥か遠くに秀麗な市房山の姿が見えた。 私は入渓点を通り過ぎてしまったことに気付き、引き返した。先程山の中腹から見えた赤い橋に続く脇道に入り、漸く入渓することができた。 水量は多かったが、何とか遡行できた。水は澄み切っていて、身も心も洗われるような爽快な気分になった。川幅が広く、伸び伸びとロッドが振れ、何よりも頭上に青空が拡がっていて、圧迫感が無いのが嬉しかった。
赤い鉄の橋は、以前上流にある取水堰堤の工事用に造られたらしく、がっちりした本格的なものだったが、最近は殆ど使われていないのか、老朽化し錆びついていた。橋の下にはやや浅い、大きな淵が2つあって、どちらも良いポイントを形成していた。 3時間ほど釣って、大物は姿を見せなかったが、中・小型のヤマメが7尾ヒットした。取水堰堤の上も良い釣り場らしかったが、この時間から釣り上がっても途中で日が暮れてしまい、谷が深くとても道に上がれそうも無かったので、諦めて納竿した。 (2001/5/16)
|
|
3.古座川支流・平井川 (和歌山県) |
|||
|
私は和歌山県の渓で釣りをしたことは、過去一度しかない。一度しかないからこそ、そのときの記憶が鮮烈に残っているのかも知れない。 ‘91年の4月末、私は古座川支流・平井川を訪ねた。平井川に来る前の2日間、私は奈良県の吉野川の源流域で釣りをしたが、事前に予想はしていたが、阪神からの入渓者が多いせいか小型ばかりで、取り立てて言うほどの釣果は得られなかった。
私は紀伊半島南端の独立河川なら、入渓者も少ないし、魚影も濃いのではないかと考え、紀伊山地を越えて新宮に出たのである。山越えをする前、私は古座川か、日置川のどちらかで釣ろうと漠然と考えていたが、新宮に着いて地図を見ると古座川が断然近く、いささか草臥れていたこともあって、古座川で釣ることにしたのである。 手始めに古座川支流の小川に入ってみたが、釣れたのはカワムツだけだった。私は小川の水源付近の標高が低いので、水温が全般に高く、アマゴ釣りには向かないのだろうと判断した。 私は、再び古座川の上流を目指し、古座川沿いの道を上って行った。この道は私には判り難く、途中三尾川(みとがわ)に迷い込んだりしながら、漸く七川ダムに到着した。 古座川は七川ダムで古座川と平井川に大きく枝分かれする。古座川が大塔山(1122m)を水源としているのに対し、平井川は大塔山から連なる1000m級の幾つかの峰や、高尾山(942m)を水源としている。両者は似たような規模で、流程は古座川の方が長いが、渓相は平井川が断然勝っている。私は平井川へのルートを選んで車を走らせた。 午後5時、漸く平井の集落に着いた。私は入漁券の販売所に立ち寄り、渓の様子を聞いて集落の1kmほど上流に入渓した。
厚い雲が上空を蔽い、辺りは薄暗くなってきた。渓相は抜群に良く、水量は多いが遡行に支障は無かった。すぐ目の前で1尾、アマゴがライズした。辺りがすっかり暗くなったので、日没と勘違いしたのか、あちこちでアマゴのイブニング・ライズが始まった。私が2尾目のアマゴを釣り上げたとき、大粒の雨が落ちてきて、あれよあれよという間に、大雨になった。 私は一旦車に戻って雨が上るのを待ったが、雨足は強まるばかりなので、釣りを諦め七川ダムに引き返し、湖畔にあった小さな旅館を見つけて投宿した。 翌朝早く宿を出て、平井川上流の玉ノ谷へ入渓した。天気は快晴で、空は青く、私はふと、紺碧というのはこんな色かも知れないと思った。渓は、適度な落差があり、澄んだ豊かな渓水が、落ち込みで心地よい水音を立てていた。樹木の若葉の緑が、初夏の陽光を浴びて鮮やかに輝き、ところどころに出現する深い淵は、空の青さを飲み込んで、コバルト・ブルーに映えていた。午前中釣って、朱点鮮やかな、殆んど高貴といっても良いほど上品なアマゴが10尾ほど釣れた。
午後、古座川本谷に移動した。古座川の魚影も、平井川に劣らず濃かった。石の河原は殺風景だが、河原に障害物が無い分こちらの方がフライ・ロッドを振りやすく、フライ・フィッシング向きかも知れない。良型のアマゴを8尾釣って、午後4時に納竿した。 (2001/7/15)
|
|
4.ウィルバーフォース・リバー(ニュージーランド南島) |
|||
|
今一番行きたい釣り場はどこかと訊かれたら、私はためらいなく、ウィルバーフォース・リバーの名前を挙げるだろう。それほどこの川は、私に強烈で、至福の記憶を残している。 私がニュージーランドに行ったのは、1997年の1月である。ニュージーランドで私は4日間釣りをしたが、この川で釣ったのは2日目である。このウィルバーフォース・リバーはニュージーランド南島のクライスト・チャーチの南にあるカンタベリー平原を流れているラカイア・リバー上流右股の支流で、サザン・アルプスを水源としている。 この辺りは、平原というより高原の趣で、樹木は少なく、どちらかというとパタゴニア地方か、モンゴルの奥地というイメージである。それにしても、樹木の少ない割には、どのリバーやクリークも、水量豊かなのには驚かされる。 ガイドしてくれたのは、アラン・カーシャーという好漢で、彼は愛車の日産サハリを駆って、広い河原や流れを横切って、上流奥深く案内してくれた。本流はサザン・アルプスの奥から流れてくるようだが、ところどころにスプリング・クリーク(湧き水の川)があって、ゆったりと本流に流れ込んでいた。川幅は驚くほど広く、2km以上もあるだろうか、はるか遠くに対岸が見え、荒涼とした砂礫の中を何本にも分流し蛇行する流れが見えた。 私は本流のニジマスを狙って、ブラインド・フィッシングを試みた。ブラインド・フィッシングとは、我々が日常行っている普通のフィッシングで、魚の姿を見ずに、ポイントと思しきところにフライをキャストするのもので、この逆がサイト・フィッシングで、魚を見つけて、その魚を狙うフィッシングのことを言うのである。
暫く経って遠くのスプリング・クリークで、アランが手招きをしているのが見えた。大急ぎで駆けつけると大きな淵があり、60〜80cmの巨大な鱒が5〜6尾、思い思いの場所占めて就餌していた。ここは、この地方には珍しく緑豊かな、鱒釣りにふさわしい別天地という雰囲気だった。 私は、鱒たちのいるのが、流れのあまりない淵の、水深2mほどの水底なので、アランの奨めもあり、フラット・シルバー・ティンセルをウイング・ケースに使ったニンフを使ってみた。タックルは、8フィート・#6のロッド、WF6Fのライン、3X、12フィートのリーダーに、4X、3フィートのティペットを足したものである。 1投目で70cmほどの鱒がヒットした。私はできるだけそっと合わせたつもりだったが、それでも合わせが強すぎて、あっけなくティペットが切れてしまった。気がつくと、群れていた鱒の姿は消えていた。 アランが、淵に流れ込む浅瀬の上流で、ライズしている鱒を見つけた。私はフライを#12のクイル・ゴードンに取り替えてその鱒の1mほど上流にキャストした。フライがゆっくりと流れてその鱒の頭上に差しかかると、鱒がスーッと浮上してフライを吸い込んだ。私は少し間を置いて、軽く合わせた。重い手応えがあって、初めはじっと動かなかった鱒が、いきなり下流の淵に向かって走り出した。鱒は広い淵の中を縦横に走り回り、ロッドは満月のよう曲がってなかなか寄せられなかった。淵の中には別に障害になるような物も見当たらなかったので、私は余裕を持って遣り取りができた。体長を計ると62cmあった。横腹に浮かび上がる色鮮やかな赤の、幅の広い帯が見事なニジマスだった。 この淵から100mほど上流にある小さな淵で、大きな鱒がライズを繰り返していた。アランは小型のイエロー・ハンピー(これは#12のニンフ・フックを使っていた)を私に手渡してこれを使えと言う。3回目のキャストで鱒の1mほど上流の、50cmほど右側にプレースできた。「ナイス・キャスト!」という彼の声と殆んど同時に、魚は頭を右に擡げてフライを咥え、ゆっくりと沈んでいった。私は1、2、3と数えて軽く聞き合わせしてみた。魚の重みを確認して、2度目はやや強く合わせると、がっちりとフッキングできた。鱒は上流右手のブッシュの陰に猛然と突っ込んでいく。私は思い切りロッドを立て、岸から後退しながら必死に耐えた。鱒が反転したので、私は鱒を淵の下流にある中洲に導いた。鱒は激しい水飛沫を立てたが中洲に横たわって、一瞬動きが止まった。アランが素早く走って行って、ハンド・ランディングしてくれた。巨大な美しいブラウン・トラウトだった。計ると72cmあった。
私は、アランにこの魚を剥製にしたいと言った。アランは、明日はもっとでかいのが釣れるかもしれないが、これでいいかと私に尋ねた。私は、明日の80cmより、今日の72cmを選んだ。 剥製が出来上がって日本に届くまでに半年かかった。この剥製は、文字通りトロフィーとなって、現在我が家の玄関を飾っている。 (2001/9/10) |
|
5.高津川水系 匹見川支流・広見川(島根県) |
||
西中国の島根県、広島県、山口県の三県が接する中国山地の冠山山地辺りは、現在も多数の熊が生息するなど、豊かな自然が残っており、ヤマメ、アマゴ、ゴギなどが生息する渓も多い。
この広見川は、島根県の高津川の支流・匹見川のそのまた支流である。匹見川は、匹見の町で、匹見川(表匹見)、広見川(裏匹見)紙祖川と、同じような規模の三本の渓に枝分かれする。広見川沿いの国道488号線は、山越えして広島県の吉和村に通じている。水源は、冠山山地の最高峰、恐羅漢山(1346m)である。
五月の渓は、夏のように葦や、木の枝が伸びておらず、またアブや、蜘蛛の巣などに悩まされることもなく、夕方まで非常に快適な遡行が楽しめ、幸せな数時間を持つことができ、今もそのときのことを、まざまざと憶い出す事ができる。 (2003/1/15) |
|
6.佐波川支流・滑川(山口県) |
||||||
|
見ず知らずの人から、「よかったら家に泊まっていけ」と、声を掛けられるなどということは、一生にそう何度もあることとは思えないが、私はある夏、三日の間に二度、違った場所で、別々の人から泊まっていけと声を掛けられたことがある。
佐波川は島根県との県境付近の野道山(924m)、飯ヶ岳(937m)などを水源とし、防府市で瀬戸内海に注ぐ山口県内有数の河川である。上流に大原湖(佐波川ダム)があり、大原湖の上流で佐波川と滑川に枝分かれする。左股が本流で、右股が滑川である。釣りの対象になる渓魚はアマゴで、以前滑川の源流部にイワナが放流されたということであるが、釣れたという話は聞いたことがない。水源となる山々の標高が比較的低いため、夏期は渇水気味となって水温が上がり、渓魚釣りには条件が悪くなる。そのため、夏場は雨後の増水したときが狙い目となる。
釣りを終えて山道を下っていた。滑の集落付近に差し掛かると、三軒並んだ民家の、真中の家の玄関前に立っていた、六十四、五歳と思しき老人と目が合った。尤もそのとき私も五十歳を越えていたので、私と一回りしか違わない相手を老人と呼ぶのも気が引けるが、彼は私に、
山口県は渓魚の体長制限が20cmと全国で一番厳しいが、この制限が守られている限り渓魚が減ることはないだろう。 (2003/5/10) |
|
7、高津川支流・福川川 |
|||
福川川は、島根県の高津川の支流で、西中国山地の小峰山(930)、鈴ノ大谷山(1036)、莇ヶ岳(1004)など1000m級の山々を水源としている。高津川水系は、西中国地方では広島県の太田川水系と並ぶ渓魚の一大産地であり、太田川水系は源流部が険しく上級者向きの渓が多いが、これに対して高津川水系は比較的平坦な渓が多く、釣り場としてはより一般向きと言え、釣り場としての価値は高い。高津川は支流の数が多く、そのほとんどに渓魚が生息しているが、それら全ての支流を探り尽くすのは至難のわざである。
途中、大きな砂防堰堤があった。堰堤の上は湛水しておらず、広い河原に一筋の流れが見えた。流れを眺めているうちに、何だか釣れそうな気がして車を止め、釣り支度をして高い崖を下って行った。それほど大物は出なかったがアマゴとヤマメが5〜6尾釣れた。この福川川は日本海側の河川で、本来はヤマメの生息地だが、ずっと以前に山一つ越えた錦川か、佐波川からアマゴが移植されたのか、或いは最近、漁協が生態系に関係なくアマゴを放流したものと思われる。2時間ほど釣っていると陽が暮れたので竿を収めた。私は、それまで、福川川にはそれほど渓魚はいないと見くびっていたのだが、このとき私はその認識を改めさせられた。
椛谷集落辺りから上流が本格的な釣り場で、左岸に古江堂谷川が合流するまでの区間は川幅が広く、フライ・フィッシング向きでロング・キャストが楽しめる。このあたりは水量もあるので釣れるヤマメの型は良い。1994年の5月初め、再び私はこの川を訪ねたが、このときは絶好調で、椛谷集落辺りから上流の黒渕、中条集落辺りまでを一日かけて釣って、二十数尾の釣果を得ることが出来た。新緑に囲まれ、澄み切った無人の流れの中で終日爽快な釣りができ、至福のときと言うのは、まさにこのようなことを言うのだろうと、しみじみと思ったものである。この日は珍しく、黒渕で小型のゴギが釣れた。源流部にはゴギが多数生息しているようだが、ブッシュが酷く、あまり釣りにはならない。また、この辺りのゴギはほとんど天然記念物と言ってもよいほど貴重な魚であり、もし釣れても、丁寧に扱って傷めないで放流して貰いたい。 この川の最盛期は4月から5月にかけてだが、真夏でも上流では十分釣りになる。支流の古江堂谷川は、どういう訳か釣れたのはアマゴばかりである。右岸に鈴ノ大谷川が合流するが、これを過ぎるとすぐに先ほど述べた大堰堤にぶつかる。福川川は中条集落で小峰谷川と大峰谷川に枝分かれするが、かなり細流となり、ブッシュも酷そうなので私は釣ったことがない。
1995年の8月の午後、三度私はこの川を訪ね黒滝辺りを釣ったが、この時期としてはまずまずの釣果を得ている。福川川は、いつ訪ねても釣り人を温かく迎えてくれる優しい渓である。 (2005/1/8) |
|
8.耳川支流・柳原川 |
|||||||
私が耳川支流・柳原川を訪ねたのは、’90年の8月15日だった。前年(‘89年)の暮れに九州自動車道の八代・人吉間が開通したことを知って、夏休みが来るのを待って出かけたのである。私はかねてから、この区間が開通したら是非宮崎の渓に行ってみたいと思っていた。
そんな訳で、宮崎の渓流で釣ることは私の7年越しの念願だった。当時私は、山口の女房の実家を、西日本で釣る際の基地にしていたのだが、このときも8月13日の朝山口を出発し、その日は熊本県・多良木町近くの槻木川(大淀川水系綾北川源流)を釣り、翌14日球磨川水系の川辺川支流・梶原川や、久連子川、小川など五家荘の渓を釣ったり覗いたりして、その夜遅く、耳川沿いの諸塚村に着いた。どの宿も閉まっていたので、私は柳原川に架かる橋の上に車を留めて夜を明かすことにした。橋の下からかすかに水音が聞こえていた。 前回、宮崎行きを計画したとき、宮崎の釣り場を地図で調べていて、耳川の支流に「柳原川」という名前の渓があるのを見つけた。私は自分と同じ名前の渓があるのに驚くと同時に、是非一度この渓を訪ねてみたいと思っていた。耳川は九州山地の中央に位置する国見岳(1739m)を水源とし、秘境で名高い椎葉村を流れる水量豊かな大河で、柳原川はこの耳川の支流で、諸塚山(1342m)を水源としている。
翌朝早く目が覚めて、橋の上から川を覗くと、昨夜は真っ暗で気がつかなかったがぞっとするほど谷が深く、指先が痛くなった(少々高所恐怖症らしい)。諸塚を出発して、柳原川上流に向かった。木々に覆われて底が見通せない、谷沿いの山道を延々と登っていくと、途中大きなダムに遭遇した。ダムを越すと谷が浅くなり渓の様子が見えてきた。谷への降り口を探しながら、なおも車を走らせると、点々と人家が現われた。そういえば、諸塚を出発してここまで一軒の人家も無かったことに気がついた。 立岩と言う集落の手前で車を停め、前夜、耳川沿いの国道のコンビニで買っておいた弁当で朝食を済ませ、手早く釣り支度をして入渓した。ロッドを振るには十分の川幅があり、河原もあるので遡行は楽だった。最初、小型のニジマスが頻繁にヒットし、何だニジマスかとがっかりしたが、立岩を過ぎた頃からヤマメだけになった。それほど大型は出なかったが、15〜20cmのヤマメが立て続けにヒットした。
その後、大平、葛の集落から最上流の内の口まで釣り上がった。途中何箇所かブッシュに行く手を阻まれたが、すぐそばに道路が通っているので、難なく通過できた。水深は、流心でもせいぜい膝くらいまでで、滝や、岩場などの悪場もなく、前日釣った五家荘の渓に比べ、嘘のように穏やかな渓相だった。何より、魚影の濃さは特筆ものである。遡行の途中、川岸に芭蕉の木が生えていたりして、関東などではとても見られない、いかにも南国らしい渓流の風情が楽しめた。
内の口から上流は細流となって釣りには不適になるが、ここまで遡ってくる間に、十分な釣果が得られた。内の口に架かる橋のプレートを見ると、「やなばるがわ」と平仮名で書かれていた。私はこのとき初めて、この川の呼び名が「やなぎはらがわ」ではなく「やなばるがわ」であることを知った。 (2005/3/5) |
|
9.錦川源流 |
|||
錦帯橋で有名な山口県岩国の錦川は、広島県境近くで瀬戸内海に注いでいる。その流域面積は広く、東は広島県との県境、中国山地の寂地山(1337m)を水源とする宇佐川や、その支流の深谷川が流れ、西には中国山地西端の莇ヶ岳(あざみがだけ、1004m)を源流とする錦川本流が流れている。私は、初め宇佐川が錦川の本流と思っていたが、意外にも莇ヶ岳から流出する方が錦川の本流であった。
大潮の集落を過ぎなおも進むと周囲の田圃が消え、漸く渓流らしい錦川が姿を現した。錦川もここまで来るとごく小規模な渓流になってしまい大河の面影は無い。片山という集落を過ぎると、渓は大きく左にカーブした。車を降りて渓を見ると、流量はさほど多くないが、澄み切った流れが見え、瀬と渕が連続する絶好のポイントが目に入った。朝から快晴で、周囲の山々の新緑が眩しく感じられた。私は早速釣り支度をして入渓した。
渕中央の水深のある流心にフライをキャストすると、待っていたように早速アマゴがライズした。20cmに少し足りないアマゴで、この辺りのアマゴは朱点が小さく色も薄いようだ。その後も、ここぞというポイントからアマゴがヒットしたが、山口県の体長制限である20cmを上回るアマゴは少なかった。暫く釣り上ったが葉ノ内という集落の前後で魚影が薄くなった。集落から200mほど上がった地点からまた魚影が濃くなり、本日最大の25cmのアマゴが出た。この辺りの景色は素晴らしく、岸辺のあちこちにサイコクミツバツツジがピンク色も鮮やかに咲いていた。最源流は屋敷川と名前が変る。相変わらず魚影は濃いが、川幅が狭まり、ボサが多く釣り難くなったので納竿した。錦川の源流の釣り場は流程が短く、その気になれば数の出る釣り場であるが、20cm以下放流という山口県の漁業規則を是非守って貰いたいものである。
鹿野IC周辺は渓流釣り場に恵まれており、国道315号線を直進し峠を越えれば佐波川の源流に出られ、蝮鹿野(はみかの)で分岐する県道を右に取り小峰峠を越えれば高津川支流・福川川に出ることもできる。また、鹿野IC近くで錦川と分かれる渋川にもよい釣り場があり、その先の米山峠を越すと、高津川支流・蓼野川の釣り場があるなど、福川川を除けばいずれも半日コースであるが、先行者のあるときの逃げ場には事欠かない。 |
|
10.周布川支流・波佐川 |
||||||||||
私は今まで数多くの渓流を釣り歩いてきたが、この周布川は私の好きな渓のベストテンに入る。私はこの渓を過去に5回訪ねている。周布川は、中国山地の大佐山(1069m)や鷹ノ巣山(943m)、掛山(843m)などの水を集め、浜田港の西の周布で日本海に注いでいる独立河川で、鍋割峠付近が水源である。最初に訪ねたのは1982年8月の夏休みである。8月3日の早朝、私は山口の女房の実家を出て中国自動車道を岡山方面へ車を走らせ、戸河内ICで降りて国道186号線で浜田へ向かった。波佐の集落で入漁券売り場を見つけて購入したが、店番をしていたのがお婆さんだったので釣り場のことは訊ねなかった。この辺りは初めて来たのだが、地図で見ると国道沿いの周布川支流の長田川より、波佐で分かれる波佐川の方が水線が長いのでこちらの方が釣れるだろうと思い波佐川の上流に向かった。
道端に小さな沢を見つけ、藪の中を沢に沿って下って行くと波佐川の河原に出た。渓相が素晴らしかった。澄み切った流れは水量もたっぷりで、渕と瀬が連続し、水面下に大小の岩が点在しているのが見えた。一目で、もう何年も出水の被害にあっていない安定した渓であることが見て取れた。その証拠に、水辺のすぐ近くに背の高い樹木が生えており、河原の岩は苔に覆われていた。
対岸に生えている樹木から伸びた枝が淵の上影を落とし、淵の中に反時計回りに緩い渦が巻いているのが見えた。私は淵の上流から、淵の窪みの前を流れるようにフライ(クイル・ゴードン#14)を投げた。すぐにライズがあり、私はすかさず合わせた。20cmほどの魚が釣れた。見ると、イワナに似ているが、頭の上にも白い大きな斑点があり、紛れもなくゴギであることが分かった。初めての釣り場で、第1投目に釣りたいと願っていたゴギが釣れるとは、何と幸運なことだろう。 ゴギをつくづくと眺めた。目玉がくりくりと大きく、どこか愛嬌があり、何だかいたずら小僧のような感じがした。私はゴギを傷つけないように気をつけてリリースした。 その後もゴギが連続して釣れたが、ヤマメも幾つか混じった。釣り上がっていくと小さな堰堤に突き当たった。私は堰堤の上の様子を見たいと思い、堰堤脇の斜面を登った。堰堤の上は半ば土砂に埋まっていた。流れ込みの泡の中から型の良いヤマメが釣れ、流れ込みの上の瀬では連続してヤマメが2尾釣れた。ゴギはいないのかなと思っていると、小型のゴギが釣れた。その先は傾斜がきつくなり、流れが左右に分かれた。右の渓は、すぐ奥に高い堰堤が行く手を遮り、左の渓は岩石がごろごろ転がり酷く荒れた感じだった。念願のゴギが釣れたことだし、ひとまず納竿して下流に移ってヤマメを狙ってみることにした。 2kmほど山道を下り、適当なところで車を止め、とりあえず遅い朝食を摂った。時計を見るともう2時を回っていた。道路は波佐の集落から源流までずっと波佐川の左岸に沿っていた。踏み跡を見つけて河原に降りた。川幅は源流部の3倍ほどに拡がっていたが、渓相は相変わらず素晴らしかった。ところどころに落ち込みと淵があり、瀬には適度の水深もあってポイントが多かった。落差はあまりなく、河原があり、歩いていて楽しい渓流である。ゴギは出なかったが、釣れるヤマメは型が良く、数も釣れたのですっかり満足して、日はまだ高かったが納竿した。その日は、事前に連絡してあった浜田の旧友宅を訪ねて泊めて貰った。
翌年の1983年の7月下旬、浜田や三角地方が豪雨(昭和58年山陰豪雨)に襲われたことを報道で知った。浜田測候所の観測では、1時間当りの最大雨量91mm、連続雨量521.5mmで、この地方では未曾有の大水害であった。私は浜田の友人のことが心配になり電話を掛けた。友人は意外に元気だったが、浜田川の水が溢れて店内に浸入したと話してくれた。私は、周布川の渓魚たちが心配になった。波佐川の被害は如何なのか、ゴギは果たして生き残れたのか。私は、あの美しい渓や魚たちの無事を願わずにはいられなかった。 翌年(1984年)の夏、私は再度周布川を訪ねた。国道186号線が周布川に接する辺りから上流の波佐川までを見て回った。国道を砂塵を巻き上げながらダンプカーが走り回っていた。長田川が合流する付近から上流の波佐川は土石流で川床が上がり、道路と河原の区別がつかない誠に悲惨な状態だった。車の轍の跡を辿って上流まで行ってみたが、川岸の樹々は根こそぎ流され、河原のあちこちに身の丈の倍ほどもある巨岩が累々と横たわっていた。あの美しかった渓流の姿は何処にもなかった。 1989年の夏、私は久しぶりに周布川を訪ねてみた。その時は波佐川と、支流の小国川で釣ってみた。小国川は渓相は今一だが、魚影は濃かった。波佐川の様子もだいぶ旧に復していたが、以前の美しかった渓相は望むべくもなかった。漁協の努力の甲斐あって、ヤマメの魚影は濃かったが、ゴギは姿を見せなかった。もしかしたら絶滅したのかも知れないと思うと悲しかった。
1994年の5月、山陰釣行の途次私は周布川に立ち寄った。今回掲載した写真はこのとき撮ったものである。このときは支流の深笹川出合い付近から周布川の本流を釣りあがってみた。この辺りは夏場には鮎釣りの人が多くてヤマメが狙えないからである。本流筋は思っていた通り数は出なかったが大型のヤマメが釣れた。それから上流の波佐川に入った。渓流の姿もかなり復旧していて、ところどころに、以前の好渓の面影を偲ばせる場所があった。相変わらず魚影が濃く満足の行く釣りができた。私は源流を目指して車を走らせた。暫く走ると、行く手を遮るように巨大な堰堤が屹立していた。私は一瞬ぎょっとしたが、新しくできた砂防ダムであることを理解した。ダムの横に新たに取り付けられた急坂を登ると堰堤の上に出た。堰堤から下を見下ろすと、下流の渓がミニチュアのように小さく見え、指先が痺れてきた。私は気を取り直してインレットから釣り始めた。すぐにライズがあり、釣れたのは紛れもなくゴギであった。12年振りに出会ったゴギである。私は、ゴギが生き残っていたことが嬉しかった。それにしてもなんという生命力の強さであろうか。この生命力があればこそ、氷河時代から延々と種族を保存してきたのであろう。私は、ゴギに<生命の意志>を見たような気がした。
その後、1996年にも周布川を訪ねて釣りをしたが、その時は大堰堤の下流でもゴギが釣れた。この文章を読んで、周布川に釣行される方は、ゴギが如何に貴重な魚であるかを理解して、魚体を痛めないように注意して、すべてリリースするようにお願いしたい。 (2009/1/5) |
|
11. 高津川水系 匹見川支流・紙祖川(島根県) |
||||
紙祖川は、周布川と並んで中国地方の渓流の中で私の最も好きな渓である。渓相が良く、水がきれいで、魚影が濃く、その上シーズンを通して釣れるからである。私はこれまで、春休みと夏休みを合わせると、多分10回ほどこの渓を訪ねているが、何時訪ねても期待を裏切られたことが無い。
私が初めて紙祖川を訪ねたのは1983年の夏であった。そのころは地理がよく分からず、山口から国道9号線で益田市の横田まで行き、国道488号線を匹見川沿いに匹見の町まで引き返し、そこで匹見川と枝分かれする紙祖川沿いの道を延々と上流に上って行ったのである。途中、水量豊かな渓相があまりに素晴らしいので、度々車を停めて竿を出してみたが、夏の盛りで水温が上がり、カワムツが流れを支配していて釣りにならない。恐らく、3月か4月の水温の低い時期ならきっと大型のヤマメにお目にかかれるに違いない。
笹山という集落を過ぎて小学校が見える辺りで車を停めた。ゴギの保護のため、支流での釣りを禁じる旨の看板が立っていた。そこから河原に降り、やや水量の減じた本流で釣りを始めた。川幅4〜5m、左右の岸から伸びた木の枝が頭上を覆っていたが釣りの邪魔になるほどではなく、水面近くの葉陰からヤマメがヒットした。20cm前後の良型が揃った。
三葛の集落で渓は二本に枝分かれした。私は左股の本流を遡った。すっかり細くなった渓を上っていくと、途中物凄いブッシュに行く手を遮られた。悪戦苦闘しながらブッシュを通り抜けると、やや川幅が広がり嘘のように穏やかな渓相になった。ところどころに点在する淵から、大型のヤマメが連続して釣れた。この辺りは下流のブッシュの為か長いこと釣り人が入っていなかったようである。
暫く遡ると、小さな木製の橋が頭上を渡り、そこを潜ると山岳の源流のようにまた渓相が変化した。少し遡ると、ブラウン・カラーのクイル・ゴードン・タイプ#14に、少し変った色の魚がヒットした。ランディングすると20cmほどのゴギだった。頭頂部から口の上近くまで白い大きな斑点があり、イワナとは明らかに違っている。とても元気が良く、私は何枚も写真を撮った。それから先はゴギばかりだったが、左岸に細い林道が通っているとはいえ、集落を遠く離れると人影は皆無で、何処となく熊の気配が感じられたので引き返した。 その後、中国自動車道の六日市インターからが近道であることが分かり、それからは専らその道を利用した。その道は、六日市インターを降りて国道187号線を益田方面へ走り、途中の七日市で高尻川沿いの県道六日市匹見線に入り、山越えして三葛に出るのである。このルートだと、国道9号線から益田を経由するルートより1時間近く時間を短縮できる。 この渓を5月に訪ねたのは1度しかない。そのときは最高のコンディションで、夢のような釣りができた。中流部の樫田から上流は何処に竿を出してもライズがあり、これが本来の紙祖川の姿だと感じた。樫田と笹山の間にはところどころ大きな淵があり、夕刻尺近いゴギが釣れたことが今も忘れられない。 ある年の夏、釣りを終えて三葛から六日市方面に向けて車を走らせていると、集落から程近いところの路上で、薄暗くなってはっきりとは識別できないが遠くで小さな動物がぴょんぴょんと跳びはねていた。ゆっくり近づいてみたると、ヘッドライトにまだ幼さの残る濃淡鼠色の縦縞模様の猫が、しきりに天に向かって跳び上がっている姿が浮かび上がった。どうやら路上を翔び回る蛾のような夜行性の昆虫を捕えようとしているらしい。私はそんな御伽噺のような光景に暫く見惚れていた。せいぜい1日に数台しか車の通らない田舎道なら交通事故の心配も無いのだろう。できれば、安心して猫を放し飼いにできるこんな処に、私も住みたいものだと思ったものである。 (2010/2/5) |
|
12.佐波川水系 島地川源流・清涼寺川 |
|||
釣り人は列車の車窓や、車のフロント・ガラス越しに川が見えると、つい眼が行ってしまう。またテレビのドラマやドキュメンタリー番組を見ていて、川や、渓流が見えると、今度行ってみたいなどと思ってしまう。これは海釣り師でも磯や砂浜を見ると同じような気持になるに違いない。私はこれまで、中央自動車道を走っていて眼下に見える笹子川や、桂川で何箇所も新しい釣り場を見つけたものである。
下清涼寺の集落を過ぎ、漸く入渓できそうな場所を見つけ車を止めた。車を降りようとしたとき、ラジオのニュースが、折から世間を騒がせていたオウム真理教事件の関係者、青山弁護士に逮捕状が出たことを報じていた。私は、弁護士ともあろう者が、オウム教団を弁護するなどとても許せないと思っていたので、心の中で喝采した。
清涼寺川は両岸が護岸され、お世辞にも渓相が良いとはいえないが、流れは数日前の大雨の影響で、岸辺の枯れ葦などの様子から幾らか増水しているように思われた。この増水が幸いしたのか、中小型のアマゴが頻繁にヒットした。釣り上げると朱色の斑点も鮮やかな美しいアマゴだった。釣り上って行くと護岸が切れて、清涼寺川本来の渓相が姿を見せる個所があった。3〜4時間の間に十数尾のアマゴが釣れ、期待通りの良い釣りが出来た。
帰り道、長いスリリングな道中を心配していたら、思いがけず左手に真新しい道を見つけた。坂を登ると、最近出来たばかりらしい広い舗装道路に出た。道路を下って行くと、30分もしないで鹿野の町中に出た。 去る2009年7月21日、防府市を中心とした地域が集中豪雨に襲われ、死者22名に上る未曾有の被害があった。私は以前、同じ佐波川支流の三谷川でアマゴを釣ったことがあるが、テレビのニュースで、土砂で川床が1mも上がったということを知った。これでは恐らくアマゴは全滅したことだろう。同じ佐波川支流のこの清涼寺川も、無傷ではおられなかっただろうと心配している。この地域の一日も早い復興を祈ると共に、渓魚たちの復活を願わなくてはいられないのである。 (2011/2/19) |
|
13.大分川支流・阿蘇野川 |
||||
阿蘇野川は大分県の大分川の支流であり、九重連山の大船山(1787m)、平治岳(1642m)、黒岳(1587m)などを水源としている。九州に棲息する渓魚は主としてヤマメであるが、瀬戸内海に面する大分川や大野川にはアマゴが生息している。なお、九州にイワナは棲息しない。
私が九州で初めてフライ・フィッシングをしたのは、1983年8月3日であった。その前日の早朝、私は滞在していた山口県の萩を発って九州の耳川を目指した。JR日豊本線沿いの国道10号線を車で走っていたのだが、一般国道は車で渋滞し午後2時を過ぎてもまだ別府の遥か手前までしか進めず、私は耳川のある延岡を諦め、目的地をJR九大線沿線の玖珠川方面に変更し、その夜は由布院で泊まることにした。 現在でも西日本方面の釣り場に付いての情報は多くないが、この当時、九州方面の渓流釣り場に付いての情報は皆無に近かった。地元では有名でも全国的には無名の阿蘇野川の名前を何故私が知っていたのかというと、以前、山口市内の古書店で、1969年(昭和44年)に毎日新聞社から刊行された「九州・西中国の最新総合釣りガイド〜ここがポイントだ」というガイドブックを見つけて読んでいたからである。
8月3日、私は午前中に筑後川上流の玖珠川支流・平家川と田野上川で幾つかヤマメを釣ったが、期待したほどの釣果が得られず、午後から阿蘇野川に移動した。玖珠川の情報も、勿論前記の本で知ったのである。 ガイドブックに載っていた阿蘇野川の永畑集落の辺りから釣り上がっていった。暫く当たりがなかったが、栢ノ木の辺りからアマゴの魚影が濃くなった。高津原辺りからまた暫く当たりが途絶えた。途中、白水鉱泉という看板が出ていたので立ち寄ってみた。ここは珍しい炭酸の冷泉で、私は天然の炭酸水があることを初めて知った。飲んでみると、冷たいが無味無臭であまり美味しいとは感じなかったが、ウイスキーを入れれば良いハイボールができるなと思った。
一服して、また釣り始めた。渓を遡るに釣れ、両岸には杉を初め高い樹々が鬱蒼と生い茂り、辺りは薄暗く私は禁断の深山幽谷に足を踏み入れたような心細い気分になった。それでも時折型の良いアマゴが釣れた。午後入渓してから10尾以上のアマゴが釣れていたので、もういいかと言う気になり、この森から一刻も早く脱出したいと思い杉木立の急斜面を喘ぎ喘ぎ這うように登った。暫く登ると、あたりが急に明るくなり、道路に出ると傾きかけた太陽が輝いていた。道路の向こうには畑も見える。私は狐に抓まれたような気がした。どうやら、川の両岸に数十メートルだけ帯のように杉が植林されているらしい。私は、自分の臆病さが可笑しくて笑いたくなった。
道路を暫く下っていると、折から夏休みとあって、子供たちの集団と出会った。「小父さん、釣れた?」と訊かれたので「ああ、釣れたよ」と答えると「見せて」というので、「みんな逃がしたよ」と答えると、「どうして?」、「勿体無い」と、子供たちは口々にひどく不思議そうに言った。どうやらこの辺りでは、魚を放流するという習慣がないらしい。阿蘇野川は夏でも美しい佇(たたず)まいを見せていた。私は、このときカメラを持ってこなかったことを後悔した。 9年後の1992年8月10日、再び私は阿蘇野川に写真を撮りに行った。このときは数日前の台風10号の影響で増水していて、写真は撮れたが釣りの方はさっぱりで、小型のアマゴの型を見ただけだった。 (2011/6/5) |