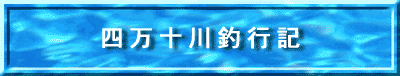
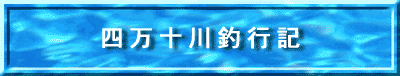
�@
|
�l���\��ލs�L |
||||||
|
�����@�ޓ� ���t��i4��26���j ���m��ʉ����̓y�n�֒ނ�ɍs�����A���͂����A�g�k������悤�ȁA���҂ƕs���̓��荬�������C�����̍V�Ԃ���o����B 1992�N��4��26���A�y�j�̖锪�����A���͓����E�����q�̎�����Ԃŏo�����A��H�l���̎l���\���ڎw�����B ���������ԓ��̔����q�C���^�[�`�F���W���獂���ɏ��A���ꂩ���A��l���̓����̒������v���ď��Ȃ��炸�S�ׂ����o�����B ���q�W�����N�V�����Ŗ��_�������H�ɍ��������B���̍����́A���_���̉������҃X�s�[�h�Ńg���b�N�������Ă���̂ŁA�����C���g���Ƃ��낾�B���E���c�Œ��������ԓ��ɓ���A�����r�`�œԂقlj��������B �ڂ��o�߂�ƁA�ӂ�͖��邭�Ȃ��Ă����B�Ăё��肾���A�ÎR�C���^�[�`�F���W�Œ��������ԓ����~��A����429�����ʼn��R���ʂւƌ��������B�����͂܂��A���������ԓ��Ɛ��˒��������ԓ��Ƃ����ԉ��R�����ԓ��͊������Ă��Ȃ������B���R���ЃC���^�[�`�F���W�ŎR�z�����ԓ��ɓ���A���ˑ勴��n�����B ���m�����ԓ��́A���݂̎b��I�ȏI�_�A�썑�C���^�[�`�F���W���o�Ă����ڂ̑O�ɂ��郌�X�g�����Œx�����H���Ƃ����B���m�s���߂��Đ{��s�Ɍ������A�{��s���獑��197�����ɓ����āA�l���\��㗬�E���t��̗���鍂�m�����Ö쑺�D�˂ɂ����̂́A4��26���̒��̏\��������Ă����B�������o�����āA���x�\�Z���ԖڂƂ������ƂɂȂ�B �D�˂Ƃ������O�͒ނ�̎�����ǂ�Œm���Ă����̂ŁA�Ƃ肠�����A��������O��A���t��ɉ��������ɓ���A�����Ƃ����Ƃ���ŎԂ𒓂߂��B���t��͎l���\��̖{���ƌ�����n��̌����ŁA�s���R�i���炸��܁E1336���j���[�Ƃ��Ă���B���t��͒ʏ̂ŁA�����ɂ͓n��i�l���\��j�ł���B �ނ�x�x�����Đ�������낷�ƁA�i�X���̊Ԃ��Ȃ��肭�˂��ĒJ������A���n�鋴�֑����Ă��鏬�����������B���̋�������k���悤�ƍ⓹������Ȃ���A�r���̔��Ŗ�ǎd�������Ă��邨�S���ɐq�˂��B �u���̕ӂŃA���S�͒ނ�܂����v �u�������̂��肾�ˁv ���V�̂��S���́A���d���̎���x�߁A���Ă�������ɔ������������āA�e�w�Ɛl���w�ŋ��̑傫�����������B �Ƃ������l�q�����邱�Ƃɂ��āA����n��A��݂̐ꂽ�Ƃ��납����k�����B�앝��3�`4���̏��k�ŁA���ꂢ�Ȑ��������ʂ͖R�����B ��݂ɂ́A�͗t�̊Ԃ���A�N�₩�ȗ̈��̗t�������L�тĂ����B���グ��ƁAꡂ������R�̋}�ȎΖʂ̂��������ɓ_�݂���A�_�Ƃ̍����ΐς̊_���̏���A��̂ڂ肪���Ă̕��ɏ���āA�g�����˂点�j���ł���̂��������B�����̂��������ŁA���ނ悤�ȗz�C�������B �ނ�n�߂Ă����A�J�[�u���Ă��镣�́A�Ί݂̍ۂ���A20�������̃A�}�S�i�l���ł̓A���S�ƌĂ�ł���j���A�N�C���E�S�[�h���Ƀ��C�Y�������A���킹���Ȃ����B�_�o���ȁA�d���Ή̃��C�Y�������B���Ȃ�ނ�l�����������Ă���l�q���B �b���ނ�オ��ƁA��݂������A�앝���g����A���R�̌k�����p�����킷�ƂƂ��ɁA���ʂ������Ă����B���݂���̎}���A�召�̊₪�_�݂���k�̏�ɒ���o���A����̒��������o������ɁA�����݂��悤�ɐ����Ă���q�������Q���A�т�����Ɖ��F�������ȉԂ��炩���Ă����B�T���Ɩ���X���z�����Ղ�A�k�͈Â������B�k���̗ǂ����ɂ͋��e�������A�����ȃA�}�S�̃��C�Y����A�O�x�����������Ȃ̂ŁA�ԂقǂŔ[�Ƃ����B �r���̍��������̃R���r�j�G���X�E�X�g�A�Ŕ�����������ƃy�b�g�E�{�g���̃E�[�������Œ��H���ς܂����B ����̒ލs�̑_���́A���t��A�k��A������A�l����A�L����A������ł���B�����Ɉ�{���ނ��Ă��A�Œ�O���͂����銨��ɂȂ�B �l���� �Ăэ���197�����ɖ߂��āA���Q���̑�F���ʂɌ������đ���o�����B���ꂩ���̒ނ�́A�[���̒ނ�ɂȂ�̂ŁA�댯������邽�߁A�Ȃ�ׂ����R�Ȓނ��Ƃ��Ďl�����I�B�l����͓�����̎x���ŁA�l���J���X�g��n�̐��[�̎R�X�𐅌��Ƃ���A�������������A�X�̊ɂ₩�Ȍk���ł���B �l����֍s���O�ɁA�����̒��ɗ������A���x�ڂɕt�����Ŕňɓ����قƂ����Ƃ���ɂ��̖�̏h�𗊂B ���������̍���197�����́A�����쉈�����̉����Ɍ������đ����Ă���B����g���l���ƌ����g���l������ƁA�����͂��̊Ԃɂ�������ƕʂ�āA�l���쉈�����A�l����̏㗬�Ɍ������đ����Ă����B����g���l������Ԃɓ�����͎l����Ǝ}�����ꂵ�ė���Ă��܂��̂ł���B�����͎l���쉈�����b�������āA������Ƃ����Ƃ���ŁA�l����ƕʂ��B��������l���쉈���̒����ɓ���A�㗬�����֓�\���قǎԂ𑖂点���B �l����́A�앝�̍L���A�ω��̖R�����ɂ₩�Ȑ����܂ł����������ŁA�A�}�S�ނ�̃C���[�W�Ƃ͒����������������B�{��X�ƌ����Ƃ���ŎԂ��߁A���������w�����Ȃ���A�ދ���u�˂��B�A�}�S�͂��邱�Ƃ͂��邪�A���܂�ނ�Ȃ��Ƃ̂��Ƃ������B ���ƁA�ǂ̂��炢�㗬�ɍs���A���̐삪�����̂���{�i�I�Ȍk���ɕς��̂��A���������Ȃ������B���v�������Ă���̂ŁA�ł��Ă��d�����Ȃ��ƍl���A����r���A��J���A�앝�����܂�A����ɕω��̂���|�C���g���������̂��v���o���Ĉ����Ԃ����Ƃɂ����B �|�C���g�ɒ������B���H�����̗��ꂪ��]�ł����B�㗬�̍L���ɂ₩�Ȑ��A����i���Đ[���ƂȂ�A�r���ƂȂ��đΊ݂ɂԂ����ċȗ����A�傫�ȕ����`����Ă����B�̏I��肩�畣�܂ł́A�����悻70�����炢���낤���B �������݁A���낻��ӂ�͈Â��Ȃ�n�߂��B�삵�������堂��A�����A���Ȃ�̑����ŏ㉺���Ȃ��畑���Ă����B ���̏㗬�ɂ���r���̗��S�ŁA�������˂�̂����ڂɂ��͂�����ƌ������B���Ȃ₩�ȁA�X�����ƐL�т����̂��A�T�C�����g�f��̈��ʂ̂悤�ɁA���ʂɂ����Ɣ�яo���A�����Ȃ��������B�������̂��A��u�A�ɐÎ~�����悤�Ɋ�ɏĂ��t�����B���͂��ꂪ�A�}�S�A���������Ȃ��^�̃A�}�S���Ɗm�M�����B ���́A��قǃ��C�Y���������Ƃ����肸���Ɖ����́A���̗��ꍞ�݂���ނ�n�߂��B��قǂ̃A�}�S�͂����ƈÂ��Ȃ��Ă���_�����������̂ŁA���ԉ҂��ɉ���������k�����B���̎����A����_���Ă��m���͒Ⴂ�̂ŕ��̓p�X�����B�t���C�̓N�C���E�S�[�h���^�C�v�Ńn�b�N���ƃe�C���̓��C�g�E�W���W���[�́�16�B ���炭�ނ���ƁA�����ԈÂ��Ȃ��Ă����̂ŁA��قǃ��C�Y���������Ǝv����r���̗��S��_���ĐT�d�ɃL���X�g�����B���x���L���X�g���Ă݂����A���C�Y�͂Ȃ������B���̃|�C���g�����܂�r�炳�Ȃ��悤�ɐÂ��ɒʂ肷�����B�㗬�̊ɂ��܂ők���Ă݂����A���C�Y�͂Ȃ������B�ӂ�͂܂��܂��Â��Ȃ�A�t���C��������Ȃ��Ă����̂ŁA���C�Y�̂������|�C���g�Ɉ����Ԃ��A�Ō�̏�����q���邱�Ƃɂ����B �|�C���g�ɖ߂��āA�t���C���^�̃z���C�g�E�~���[��12�Ɏ��ւ����B���X�g�E�`�����X���B ��ځA�t���C�̎��͂ɂ͉��̕ω����N���Ȃ������B�ڂ́A��ڂ��30�����قǎ�O�Ƀt���C���v���[�X�����B�s�ӂɁA�Â����ʂɔg�䂪�N���A�������オ��A�r�X���������p�����킵���B �ڂ������̂ŁA���ɂ͂��ł����킹����S�\�����o���Ă������ƂƁA���̂ق����A�����Ȃ�ł��a��H�����Ƃ��鋭���ӎu�������Ă����̂ŁA�����������|���肵���B ���҂����قǂ̑�^�ł͂Ȃ��������A��\�O�W�قǂ́A���L�̔������A�}�S�������B�l���\��Ŏ�ɂ����n�߂ẴA�}�S���B���͂��̃A�}�S���A�b�����߂Ă������A�u���肪�Ƃ��v�ƐS�̒��řꂫ�Ȃ��烊���[�X�����B�L���Ɏc��A�}�S�������B ������{���A��c�ː�i4��27���j �����A�����ڂ��o�߂��B���ق̐l�����́A�܂��N���Ă��Ȃ��炵���A�ٓ��͐Â܂�Ԃ��Ă����B�͌��ł��U�����悤���ƁA�N���o���ĕ\�ɏo���B�\�̒ʂ�͍���440�����ŁA��������l���J���X�g��n�̒n�F���ɒʂ��Ă���B�����Ƃ͖�����́A���^�Ԃ��Q������Ⴆ����x�̋ɂ������H�n�ł���B���̗����ɂ́A�G�݉��A�������A�H���A���قȂǂ̌Âт��������A�����̋�����ɕ��ׂ��悤�Ɍ���ڂ��ė����Ă����B �l��Ԃ̉����̖����A�����̒ʂ���A�n�F��������50���قǕ����āA�M���̂���l�p�����ɋȂ���ƁA�����ɓ�����ɏo���B �ӂ�͂������薾�邭�Ȃ��Ă������A���z�́A���͂̎R�X�ɎՂ��Č����Ȃ������B���̏�ɗ��ƁA�Ђ���Ƃ����앗���j�ɐS�n�悩�����B��̗��݂́A�R���N���[�g�Ō�݂���Ă���A�㗬�Ɍ������āA�E�֑傫���J�[�u���Ă����B�앝�́A�͌����܂߂āA5�`60�����炢���낤���A���̉��́A�[������ł������A���͓����ŁA���ŏ��������܂Ђ��ł��ăL�����ƌ���̂��������B����́A�L�������苷�܂�����A�Ȃ�����[���Ȃ�����A�܂��A�����Ȃ�����x���Ȃ����肵�Ȃ���A�I�X�Ǝ֍s���J��Ԃ��Ă���B���Ԋw�ҁE�����g�̉͐�^�̕��ނŌ����A�T�^�I�Ȓ����͐�^�������Ă���B�i�u�����̓������Ԋw�I�����T�v�����g�j ����͉����Ɍ������č��փJ�[�u���A200���قlj����ɂ��鋴�̉��ŁA��h�ɂԂ����Ă����B���̉��ɁA��`�O�l�A�ނ�l�炵���l�e���������B���͋}���ŋ���n��A�Ί݂̒�h��̓���ʂ��āA�����̋����������B���ɒ����āA���̒��قǂ��牺������ƁA����͋���20���قǏ��ŁA�����ƂȂ��č��݂̌�݂ɂԂ���A����100���قlj���́A����ɎՂ��ďo�����傫�ȃv�[���ɗ��ꍞ��ł����B ���̉���̉͌��ɂ́A�O�l�̒ނ�l�����Ԋu�ɕ���ŁA���ꂼ�꒷�Ƃ���ɂ��āA���Y�~�J���ɊƂ�ł��Ԃ��Ă����B ��ԉ���̒ނ�l���^�̗ǂ������|���ĊƂ𗧂Ă��B�^�����̊ہX�Ɣ삦���A20�����قǂ̋����A�̂����˂点�ďオ���Ă����B���͈�ڌ��Ă��ꂪ�A�}�S���ƕ��������B�����Ĉ�ԏ��̒ނ�l�ɂ��A�}�S���|�������B�N�₩�ȊƎJ���ŃA�}�S����荞�B�n���Ȓނ�p�ŋC�����Ȃ��������A���̒ނ�l�͏����������B���R�̖�ǒ��𒅂āA�����S�����𗚂��A���F�̓��{��@����X�q�����ɔ�������N�̏����������B ����Ȓ����Ō^�̗ǂ��A�}�S�����X�ƒނ�Ă���B�Ȃ�ƌ����삾�낤�B�ނ�l�̓V���A�������A�y���A�鋫�A�ʓV�n�A���X�ƌ��t��������ł����B���͂����ɏh�Ɏ���ĕԂ��A���A�[�E�t�B�b�V���O�̎x�x�������B���́A�t���C�E�t�B�b�V���O�łȂ��A���A�[�E�t�B�b�V���O�Ȃ̂��ƌ����A�a�ނ�����Ă���T�ŁA�܂����t���C�Œނ�锤�͂Ȃ��Ǝv�������ƂƁA�t���C�̖ڗ��������C���ŁA�a�ނ�̒ނ����r�炵�����Ȃ��Ǝv�����̂ŁA���A�[��I�̂��B�^�b�N���́A�E���g���E���C�g�̃L���X�e�B���O�E���b�h�A���[���̓A�u��1500�b�A���A�[�̓n�X���A�[��1/4�I���X�̃S�[���h�ł���B �ނ��ɖ߂�A�a�ނ�̐l�����̎ז��ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�ނ�l�̂��Ȃ����̏��̗��ꍞ�݂�_�����B����Ɍ������Ē��p�ɗ����A�����́A���ꂪ�݂ɂԂ���ӂ�́A�݂̍ۂ��肬��ɃL���X�g���A����ɏ悹�ă��A�[�܂��Ȃ���A��`�ɉ����Ɉ����Ă݂��B50�������݂Ƀ|�C���g�������ɕς��Ȃ���A���������������Ɉړ������B �O�x�ڂ̃L���X�g�ŁA����ɏ�������A�[�����C���Ɉ�����Ă�����Ɍ�����ς��悤�Ƃ����Ƃ��A�K�c���ƃA�}�S���q�b�g�����B�ہX�Ɣ삦���A���̐F��������22�`23�W�̂��ꂢ�ȃA�}�S�������B���h�̗��[���C��Ċۂ��Ȃ��Ă����̂ŁA�����������ꂽ���̂��Ƃ������Ƃ������ɕ��������B�l�C�e�B�u�ł͂Ȃ������̂ŁA���X�������肵���B���̌���A�����|�C���g�œ�A�O�x�����肪����������|���肵�Ȃ������B �����̉����̃v�[���̗��ꍞ�݂ɂ͒ނ�l����l�����̂ŁA����̉����Œނ邱�Ƃɂ����B ����̍����͎v���Ă��������Ⴍ�A2���قǂ����Ȃ������̂ŁA�ȒP�ɉ��ɍ~��邱�Ƃ��ł����B����̉����́A�㗬����͂悭�����Ȃ��������A������̐[���a�����܂ꂽ��Ղ��I�o���A�͌��ɂ͑傫�Ȋ₪���낲��Ɠ]����A�r�X�����l���������Ă����B�r���ƕ����A�������D�̃|�C���g���������A���x���A�[�𓊂��Ă��A������͂Ȃ������B ��������Ȃ艺���āA�O�\�������A�[�𓊂������낤���A���A�[��ǂ����e�͑S���Ȃ������B�J�Ԃ̒��ɒ������������B���͉��牺�̃|�C���g����߁A���̏ꏊ�ɖ߂����B����A�����̃v�[���̗��ꍞ�݂ɂ����ނ�l�̎p�͂Ȃ������B �������A�[���v�[���̒��قǁA�݂���10������̂Ƃ���ɓ����A���A�[���\�����܂��Ă��烊�[�����O����ƁA�y�������肪����������|���肵�Ȃ��̂ł��̂܂܈����Ă݂��B�܁`�Z���̃A�}�S�����A�[��ǂ��Ă��āA�߂��ł��̒��̈�����̓����肷��悤�ɃA�^�b�N���A���x����|���肵���B����ނꂽ�̂Ɠ����T�C�Y�́A�����������ꂽ�A�}�S�������B���̌�A���W�c�Ń��A�[��ǂ��Ă������A���̒��Ƀ��A�[��ǂ�Ȃ��Ȃ����B �ēx�A���̏��̗��ꍞ�݂Ń��A�[�𓊂��Ă݂��B���x�͂����Ƀq�b�g�����B�ނꂽ�A�}�S�𑫂��Ƃ̐�����Ɋ������Ă����āA���x��5���قlj����ă��A�[�𓊂����B�����Ă����ɒނꂽ�B �z���˂��āA���ʂ����炫��ƌ����Ă����B�a�ނ�̐l�����ɁA������͂Ȃ��Ȃ��Ă����B����̏������ނ���~�߂āA�A�肪���Ɏ��̖T��ʂ肩�������B���͐�����Ɋ������Ă���������̃A�}�S���A��낵��������ǂ����ƍ����o�����B�ޏ��͈�u���߂�������A���J�ɗ�������ăA�}�S�����A���Ăɔ[�߂ė����������B �h�ɖ߂�Ǝ������ɂȂ��Ă����B���H�̎��A�h�̏�������A����A����ނ�������̏�̃v�[���ŁA�e�q�A�}�S�ނ���Â��ꂽ���ƁA�����̒ނ�l�B�́A���̎c��A�}�S��_���Ă����̂��Ƃ������Ƃ�����āA�ނ�l�̐��̑����Ƌ��e�̔Z�����[���ł����B�����̒ނ�t�ɂ��Đu���Ă݂����A�悭�ނ�����Ă���Ƃ������Ƃ����ŁA���܂�ڂ������Ƃ͘b���Ă���Ȃ������B ��c�ː� ���H���ς܂��A�h���o�č���440������k�サ�A������̏㗬��ڎw�����B������́A�n��i���t��j�ƌ�����ׂ��͂ŁA����ʐςł́A���n��ɗ�邩���m��Ȃ����A�k��A�l����Ƃ�����x���������A���ʁA���i�ł͓n���ꡂɗ��킵�Ă���Ǝ��ɂ͎v����B�_���̂Ȃ���Ƃ����C���[�W���l���\��̃C���[�W�ł���Ȃ�A�m���ɁA������ɂ̓_������������āA�l���\����\�����Ƃ��đ��������Ȃ���������Ȃ��B�������A�x�����܂ޓ�����̗���S�̂̕W�����A�n��̗���̕W����荂���ʒu���Ă���A���ꂾ�����w�ȃC���[�W�������A�k���ނ�t�@���̈�l�Ƃ��āA�����삱���l���\����\����͐삾�Ǝ��͍l���Ă���B �h���o��O�ɁA�����ɕ������b�ł́A�z�m�ʁi�����߂�j�̕ӂ肪�悭�ނ��炵���Ƃ������Ƃ������B�I�`�����ƍŏ��������Ƃ��A�ǂ�Ȏ��������̂��S�����������Ȃ������B��������̂��肻���Ȓn�������A�\�ʂɂł��W������̂��낤���B�i������́u�\�y�k�`�v�ɉz�q�q�����r�Ƃ����\�ʂ̍�҂̖����o�Ă���j ������́A�c��X�ő�c�ː�i������{���j�A�i���A�c��X��̎O�{�Ɏ}�����ꂷ��B�E������c�ː�A�������i���A�������c��X��ŁA�O�{�Ƃ����K�͂̌k�ŁA��������l���J���X�g��n�́A�ܒi��i1455���j�A�����z�i1310���j�A������i1143���j�A����i1342���j�Ȃ�1300���`1400�����̎R�X�𐅌��Ƃ��Ă���B �O�{�̎x���ɕ������܂ł̓�����́A�����I�Ȕ��k�ŁA�ǂ����璭�߂Ă��G�ɂȂ����B���K�͂ł͂��邪�A�l���\��Ɠ��̒����������������Ɍ����A��݂ɂ͍g���F�̉Ԃ������L�V�c�c�W�������鏈�Ɏ������A���͂̐V�ƁA���̐��ɂ悭���a���Ă����B���͕p�ɂɎԂ��߂Ďʐ^���B��܂������B
�����삪�c��X��ƕ���@�ʓ��Ƃ����W�������̃J�[�u���߂́A�L�V�c�c�W�̌Q������̂ق��������A�݊��̎��n�ɂ́A�R�������\�E�������Ԃ��炩���A�T�J�n�`�`���E��x�j�V�W�~�ȂǃI�����W�F�����������Q�����ċz��������i�͈�ۓI�������B �O�{�̎x���̒��A���������̉i���͌h�������B�c��X��͌�ɂ��āA��n�߂ɑ�c�ː��ނ邱�Ƃɂ����B�z�m�ʂƂ����̂́A�ǂ���炱�̕ӂ��т��w���炵���B ��c�ˌ��Ƃ������ŎԂ��߂��B���v������ƒ��x�㎞���w���Ă����B���̉E��̊ɂ��X�������̒����A�k�ɍ~��鏬��������A���̐�ɏ����Ȗؐ��̋����������B���̏�𐔕C�̃����V���`���E���ɂ₩�ɕ����Ă����B�t�̐���̒��ՂȎR���̂������܂��������B �����Ԃ���k�ɍ~�肽�B�앝��4�`5���قǂŁA��݂ɂ͍̉Ԃ��������A���������ɉ��F���Ԃ��炩���Ă����B���ʂ͉����ɔ�ׂĂ����ƌ����Ă����B���̏㗬�͏����ȕ��ɂȂ��Ă��āA���̗��ꍞ�݂́A�̎}������o���Ă��鉺��_���ăt���C�𓊂����B ���́A�n�߂Ă̒ނ��Ŏg�p����t���C���A�S���̐M���������Ă���N�C���E�S�[�h����14�ƌ��߂Ă��邪�A���̎����N�C���E�S�[�h����14���g�p�����B����ɏ�����t���C���}�̉��ɍ���������Ƃ����Ƀ��C�Y�������āA12�`13�����̏����ȃA�}�S���q�b�g�����B�Ȃ������͒ނꂻ���ȗ\���������B �͌��̂Ȃ����k���A����̒����ʂ��Œނ�オ�����B�ނ���ɂ�ċ��e���Z���Ȃ�A�^��20�������������悤�ɂȂ����B �ݕӂɂ��Ԃ���悤�ɐL�т����X�̗t���A���̎Ό������ĉ��ΐF�ɋP���A���ʂ𗬂��t���C�̃n�b�N�����A�z���𗁂тăK���X�@�ۂ̂悤�Ɍ����Ă����B ���L�삪���������O�Ōk�͑傫�����ɋȂ����Ă��āA�Ȃ�p�̊R�̏�ɏ������K���������B���L��͗��ꂪ�ׂ��A�J��̑������ł��Ȃ���A�ƂĂ��ނ�ɂȂ肻���ɂ��Ȃ������B�����_���߂͐[���ؗ����ɕ�܂�A�k�͈Â��A�������傫�������B �ȗ��_���߂���ƁA�����ȋ����������B���̉����͑�₪�_�݂��A����D�|�C���g������A���̃|�C���g�̈����A�}�S����ނꂽ�B����������ƋJ���Ė��邭�Ȃ����B���̏㗬�́A������Ƃ����v�[���ɂȂ��Ă���A�nj^�̃A�}�S�������I�R�Ɖj������Ă������A�t���C�𓊂���Ƌ����Ċ�̉��ɓ�������ł��܂����B �앝�͂��悢�拷�܂�A���݂̌͂ꂽ���̊Ԃ���A�Z���ΐF�̎Ⴂ�t���L�сA���̖݂̂Ƃ���ǂ���ɁA�̉Ԃ����F���Ԃ��炩���Ă����B �����̂Ȃ����₩�ȗ���̒��ɁA�召�̊₪�_�X�Ɠ����o���A���グ��ƁA����̍s����Ɋ┧��I�o�����l���J���X�g��n�̂Ȃ��炩�ȗŐ����������B ��ڂ̋����������đ�c�˂̏W���̎�O�܂Œނ�オ��ƁA�k�̐^���ɐg�̏�ȏ�������₪�s������Ղ�悤�ɉ�������Ă����B����́A���̑��������悤�ɍ��E�ɕ�����ė���A��̊�́A��[�����e������ɍ���A�E��ł���B���́A���1���قǏ㗬�Ƀt���C�𗎂Ƃ��A��̂����e�����R�ɗ������B�堂����ʂɕ����~��ė��ꉺ��V�[�������o���Ă݂��B �t���C������ɏ���ĉ���A��������悤�ɂ����Ǝ�O�ɋȂ���A��̉���10�����قǗ��ꂽ���A�ˑR�A�\�z��ꡂɒ�������^�̋��̂��A�t���C��ǂ��Đ��ʋ߂��ɂ���Ǝp�������A�����ɏ������B �ڕ����H�v�킸�����������B�S�܂Ő��𐔂��Ă������ԍ��������A�ēx�t���C�𓊂��������ɓ����͂Ȃ������B�t���C�̎�ނ�ς��A�T�C�Y��ς��A�����̒m���ƌo���������ĉ�����g���C�������A���̑啨�͂����ƒ��ق����܂܁A��x�Ǝp�����킳�Ȃ������B �O�\���قǔS���Ă悤�₭���߁A���x���ɂȂ����̂ŏh�ō���Ă�������ٓ���H�ׁA��c�ː�̒ނ�ɏI�~����ł��Ƃɂ����B�����琔���āA���A�[�Œނ������������āA�����Ə\�܁A�Z�����炢���ނꂽ���낤���B�l���\��ɗ��Ă悤�₭�����̂����ނ�����邱�Ƃ��ł����B �k�� �ߌ�́A����197������{����ʂɑ����āA���Ö쑺�̖k���ނ邱�Ƃɂ����B�k��͓�����̑�x���ŁA�l���J���X�g��n�̍ō���A�V�獂���i1485���j��A����R�i1365���j���A�J���X�Ƒ�n�̓��[�̎R�X��A�s���R�i���炸���1336���j�𐅌��Ƃ��Ă���B �V�c�Ƃ����Ƃ���ō���439�����ɓ������B���݉Ɓi���������j�Ƃ����W�����߂��A�k��ɉ����ď㗬�ڎw���ĎԂ𑖂点���B�����Ƃ͖�����́A�ܑ����Ă��邾���̂����̎R���������B �Ԃ��猩��k��̌k���͑f���炵���A�ǂ��ł��ނꂻ���Ɏv��ꂽ�B�����ɋ߂�����Ƃ����W���ŎԂ𒓂߂��B�V�c���߂���������܂肾���A�ߑO������قǗǂ������V�C���R�̂悤�ŁA����ɂ����Ƃ��ɂ͎��͈͂Â��Ȃ��Ă����B �k�ɂ͂����ɍ~��邱�Ƃ��ł����B���͐���ł���A�k�����ǂ������B�ߑO���ɒނ�����c�ː������傫�Ȍk�Ő��ʂ����������B��߂��܂ŗ���������A��͑ۂނ��āA�k���ƌĂԂɑ����������k�������B �������A�ނ�Ȃ��B�t���C�̎��ӂɂ͐��͂��납�A�Q���A�g����N���Ȃ������B�����ɋ����ē����鋛�e����Ȃ��B �Ƃ��Ƃ��J���~�肾�����B��������Ƀ��C�������[���ɔ[�߂��B���H�ɏo�ĎԂɖ߂�r���ɏ����Ȗ��l�̔̔����������āA��R�̖쑐�̔��A�����A�����l�̂悤�ɍs�V�悭�A�O�i�ɂȂ����I�̏�ɕ���ł����B150�~�Ƃ��A200�~�Ƃ��̒l�D���A���ꂼ��̔��ɍ����Ă������B�G�r�l�ƃi���R�����A�V�����A���L�U�T���čd�݂������ɓ��ꂽ�B���ɃX�~����V���������Ȃǂ��������B �Ԃɖ߂��ĉJ�̎~�ނ̂�҂��Ă�����A���̂܂ɂ������Ă��܂����B�ڂ��o�܂��ƉJ�͏オ���Ă���A���v������ƌߌ�l��������Ă����B�ꏊ�ւ������悤�ƎԂ𑖂点�R���������B���݉ƂɎx������{���ꍞ��ł������A�n�}�Ō���ƌ��\���������ŁA���Ԃ��x���Ȃ������Ƃł�����A�x���ɓ���͎̂~�߂āA���݉Ƃ��班���������{���Œނ邱�Ƃɂ����B �{���͐��ʂ������A�J�̂����ŏ������肪�����Ă����B���[������A�C�̂����傫�Ȓ�����������ɓ]�����Ă���A�n�ɂĂ��������B ���ǁA10�����O��̃A�}�S���܁`�Z���ނꂽ�����œ�����ꂽ�B���݉ƂŔ��܂낤�Ǝv���Ă������A���̕ӂ�ł͑債�Ēނꂻ���ȋC�����Ȃ������̂ŁA�ēx�����ɖ߂��āA�O���Ɠ����ɓ����قɔ��܂����B �O�̔ӂ͓��h�҂����炸�Â����������A���̖�͌\�j�Ə\��̎Ⴂ�j�̓�l�A�ꂪ���܂��Ă���A���N�j����x���܂ŎႢ�j�Ɍ������āA����炭�ǂ��ǐ������݂����Ƃ������Ă����̂����ɂ��ĂȂ��Ȃ��Q���Ȃ������B �c��X��A�l����i4��28���j
���H�ƒ��H��ٓ��ɂ��Ė���āA�ߑO�����ɏh���o���B�����̑_���͓�����̎x���̓c��X��ł���B����440������c��X�܂ōs���A�����ō��܂��ēc��X��Ɍ�������������Ă������B�c��X��̗����ɂ͓c�ނ��L����A���݂͐ΐς݂̌�݂ƂȂ��Ă����B�₪�ēc�ނ��i�X���ɕς��A���ܑ͕�����Č��z�𑝂��A�}�ȍ⓹�ƂȂ����B�l�Ƃ������Ȃ��Ȃ�A���������āA�ѓ�����{�ɕ���Ƃ���ɃR���N���[�g�̋�������A�����ԂɎԂ𒓂߂āA����100���قǕ����ĉ����ē��k�����B �앝�͋��܂��Ă������A�����������ɑ�₪�_�݂��A���₩�Ȑ��Ə����ȗ������݂��A�������D�k�������B���k�����Ƃ���̂�����̗������݂ő�������ނꂽ�B18�������́A�ܘ_�l�C�e�B�u�̃A�}�S�ł���B��_�����I�����W�������āA�����E�C����̃A�}�S�́A���̐F���v�킹��Z����F�ɔ�ׂĂ����Ԃa�ȐF�ł���B ���̍��͔����A���͗₽�����ݐ�A���̐V���N�₩�ŁA���܂Ō��Ă����ǂ̌k�����������Ɗ������B������w���ɎĂ����̂ŁA���͉e�𗬂�ɗ��Ƃ��Ȃ��悤�ɋC�����Ȃ���ړ������B�g�̏�ȏ��������̌������ɁA�w�̍������L�̖��A���F���Ԃ̂ڂ݂̉�����ė����Ă���A�������썑�̌k�ł��邱�Ƃ����������B �����ȗ������݂̌��A����̂Ԃ����̊�A�A���[�̂��闬�S�ȂǁA�������Ǝv����|�C���g�ŕK���q�b�g�����B�����̃A�}�S�͖���Œނ�ꂽ���Ƃ��Ȃ��悤�Ɏv����قǁA���ԂŖ��x���������B������Ԃ������܂ők��120���قǂ̊ԂɁA�����̃A�}�S����ɂ��Ă����B ���͂��̂Ƃ���N���[�����������A���̑���J�����������A�ނꂽ���̒��Ō^�̗ǂ��̂�A���̂̓��ɔ������̂��ʐ^�ɂƂ��āA���ׂĕ�������̂��K���ɂȂ��Ă��܂��Ă���B���͂��̓��A�ǂ̃|�C���g�ŁA�ǂ�Ȃӂ��Ƀq�b�g�����������Ɏv���o�����Ƃ��ł���̂ŁA�ނꂽ���̐����ԈႦ�邱�Ƃ͖w�ǂȂ��B �Ԃ𒓂߂����̏㗬�ɏ����ȉ������������A���̉����z���Ēނ�オ���čs�����B�k��ɘA��Đ앝���g����A�͌��͕��R�ɂȂ�����Ղ��Ȃ����B �c��X��Œނ�l�́A���̉�������k����炵���A�������͎�藧�Ăċ��e���Z���ƌ������Ƃ��Ȃ��A�^�����܂��^�͏o�Ȃ������B�|�c�|�c�ƒނ�Ă͂������A�㗬�ɍs���ɘA��ċ��e�������Ȃ��Ă����̂ŁA�K���Ȓn�_�Ő�グ���B �Ԃɖ߂�A���H���ς܂��A�R�����������B�r���Ōk�͓��𗣂�Č����Ȃ��Ȃ������A500���قlj����ꡂ������ɐΐς݂̌�݂��������B���̂������͒ނꂻ�����ƂЂ�߂��ĎԂ��߂��B�ӂ�ɂ͔_�Ƃ��_�݂��A��������_�Ƃ̑O��ʂ��Đ�̂ق��֒ʂ���Ȃ��肭�˂����������������B���͓͂c�ނ������A���ł��̂�т�ނ�̂ɑ�����������ŁA�k�Ƃ͂ƂĂ��Ăׂ�㕨�ł͂Ȃ������B���͂��̕ӂ肪�A����A�}�S���ނꂽ�n�_���炳�قǗ���Ă��Ȃ����ƁA�k���ނ�t�͂���Ȍk����n���ɂ��āA�Ƃ���ꂽ�肵�Ȃ����낤�Ǝv���邱�ƂȂǂ���A�t�ɁA�����������狛���c���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����̂��B �����Ԃ����ɉ��肽�B���̉��͐��[�͂��������A�����̗��܂萅�̂悤�ɗ���ł����B���܂Ő��ɒЂ����ď㗬�ɏ���Ă����ƁA���[���Ȃ�A�Q����炵�����ɓ������o�Ă����B���݂̗��ꍞ�݂̏㗬�́A���݂̐Ί_�̍����ɂт�����ƈ��������Ă����B�͂ꂽ���͖w�ǔ����قǂɐ܂�Ă���A�V�������̉肪�܂ꂽ���ƌ�����ׂ�قǂɐL�тĂ��� �㗬�Ŏ搅���Ă���炵���A����ׂ͍��앝��1���قǂ����Ȃ������B����̏��Ƀt���C�𓊂���ƁA�t���C�͐��̉��ʂ��Ȃ���悤�ɐ��ʂ��㉺���Ȃ��痬�ꉺ��Ă����B�݊��́A���̍������P��Ă���Ƃ���Ń��C�Y������A�^�̗ǂ��A�}�S���q�b�g�����B��ʂ��ŗ���ɗ�������Œނ��Ă���̂ŁA��荞�݂͊ȒP�ł͂Ȃ��B�\����A�}�S������ƃl�b�g�Ɏ��߂��B �����24�����قǂ̃I�����W�F�̔��_���N�₩�Ȕ������A�}�S�B�J�����͎Ԃ̒��ɒu���Ă��Ă��܂����B����ȂƂ��Ɍ����Č^�̗ǂ��̂��ނ����̂��B�d�����Ȃ�����A�A�}�S����ꂽ�l�b�g��������Ɗ����Đ��ɐZ���A�l�b�g��������Ȃ��悤�ɐʼn������ăJ���������ɎԂ֖߂����B ����ȓc�ނ̒��ŃA�}�S��ނ�l�ȂǒN�����Ȃ��̂��낤�B�^�̗ǂ��̂��ʔ����悤�Ɏ��X�ƃq�b�g�����B�ނ����Ă����Ɠc�ނ̎搅���炪�������B����̏�͑傫�Ȓ����v�[���ƂȂ��Ă���A�v�[���̒������܂ŒЂ����ď㗬�i��ōs�����B�����v�[���̒���30���قǕ����Ă����Ə����ȃR���N���[�Ɛ��̋����˂����Ă���A����������Ɨ��ꍞ�݂������Ă����B���ꍞ�݂ɂ͂����Ƃł����̂�����Ɗm�M�����B �����𗧂ĂȂ��悤�A�����Ƌ߂Â��A�N�C���E�S�[�h����14��T�d�ɃL���X�g�����B�o�V���b�I�t���C����������Ɠ����ɁA�h��Ȑ����オ�����B�\�z������葁�����C�Y������A��������ĕs�o�ɂ����킹���Ȃ����B���͗��ꍞ�݂́A������x���[�̂��闬�S�Ń��C�Y���邱�Ƃ�z�肵�Ă������A�A�}�S�͗��ꍞ�݂̋ɂ����ʼna��҂��Ă����炵���B ����ɂ��Ă��ł��������B�����炭�ڋ��ł��낤�B��|���肵�Ă͂��Ȃ������̂ŁA����������ƁA�܂������m��Ȃ��Ǝv���A�S�܂Ő��𐔂��đ��肪���������̂�҂����B�S���̌ۓ����͂�����ƕ������Ă����B���ꂩ�牽�x���L���X�g�����݂����A��������̋��҂ƌ����A���ꂫ�蒾�ق��Ă��܂����B ���ꍞ�݂��߂��A�㗬�ɑk��ɏ]���Čk�����D�]���A��قǂ܂ł̓c�ނ̒��̏��삪�R�̂悤�ɁA�����Ȍk�J�ɕϐg�����B���H����͗���Ă���̂ŁA����Ȍ��i��z������͓̂���B���₪�_�݂��A�����������A���݂͋��܂�A���k���ꂽ�����͔��ɋ��������B���Ɨ������݂ƕ����A�����A�nj^�̃A�}�S���q�b�g�����B50���قǂŊj�S�����I���A�ŏ��̓��k�n�_�ɒ����Ĕ[�Ƃ����B�����炩�ꂱ���\�����̃A�}�S���ނ�Ă����B �l���� ���H���ς܂��Ǝl����̏㗬�ֈړ������B �����A�l���\��ɒ��������̗[���ɒނ����A�l����̋{��X����㗬��ڎw�����B���琣�����̌k���͑��ς�炸�ŁA�r���ō��������č�{��ƌ������ŊƂ��o���Ă݂����A�S�������肪�Ȃ������B�Ăя㗬��ڎw���A�Ԃ𑖂点�Ă���ƁA�앝�����܂�A�k�����ǂ��Ȃ��Ă����B�ؖ�c�Ƃ����Ƃ���ŎԂ�����Ēނ�n�߂��B���炭�ނ�オ��ƁA�������o�Ă��āA��₪����A�������݂��_�݂���f���炵���k���ɂȂ������A����ɓ����肪�Ȃ��B�r���ŁA�݂̏�̔��Ŗ�ǎd�������Ă���V�l�ɐ��������Đu���Ă݂�ƁA���̕ӂ�͖����̂悤�ɒނ�l������������̂ŁA�������苛�������Ă��܂����Ƃ̂��Ƃ������B ���߂āA�܂��㗬��ڎw�������A����K�ƌ����Ƃ���Ōk�͓ɕ�����A�����̉���K����̗���́A�������肪�����Ă���A�E���Œނ��Ă݂��B�b���ނ��Ă݂����A�ɂ����^�̃A�}�S����A�O���ނꂽ�����������̂ŁA�l����Ɍ�������āA�܂����邩�������[�Ƃ����B ���̖�̏h�͂܂����߂Ă��Ȃ��������A�����͍L����Œނ���肾�����̂ŁA�h�͍L���쉈���ŒT�����Ǝv���Ă����B �L����͈��Q�����𗬂�Ă���A���́A�I�퓖���a�J���Ă������Q���̋g�c���̒ߊԂ��A�L���삩�炻��Ȃɗ���Ă��Ȃ����ƂɋC�������B�}�ɁA���������Ȃ��āA�ӂ��ƁA�g�c���ɍs���Ă݂����Ȃ����B�ߊԂɂ͕���̐e�ʂ��Z��ł��āA��ƌZ�A�o�A���̎l�l�͂��̐e�ʂ𗊂��đ�ォ�炩��a�J���A���a19�N�̓~����22�N�̉Ă܂ł̓�N���قǂ�ߊԂʼn߂������B���́A�����̒ߊԏ��w�Z�ɓ��w���Ă܂Œʂ����̂����A���̓����̂��܂��܂ȋL�����A�C�t�����ɓ��݂����n�����s�ӂɔ��������悤�ɁA�ꎞ�ɑh���Ă����B �������獑��197�����𐼉����A�r������320�����ɓ���A�F�a���s�Ɍ��������B�F�a���s�ɒ������̂ɂ͖�̔����߂������B�F�a���w�O�̓y�Y�����Ŕ����������A�H�����ς܂��ċg�c�����������B�g�c������ߊԂ̏W���ւ̓�����������炸�A�s���߂��Ĉ����Ԃ����肵�Ȃ���Ȃ�Ƃ��ߊԂւ��ǂ蒅�����Ƃ��ł����B ���w��N�̉Ă��̒n�𗣂�āA���Z����Ɉ�x�K�˂�����ŁA�O�\�N�ȏ�̋�����ƁA�������b�ɂȂ����e�ʂ̉Ƃ��ǂ̉ƂȂ̂��A�钆�ƌ������Ƃ������đS�����������Ȃ������B�@���ɁA�Ⴍ�A�Ȃ鍕���R�̉e���C�ɔ���A�R�ƊC�̊Ԃ̋����y�n�ɁA�C�ݐ��ɉ����ė��������Ƃ͈Èł̒��ɂЂ�����ƐÂ܂�Ԃ��Ă����B����̒ލs�ɒߊԂ�K�˂�\��͂Ȃ��������A�e�ނ̏��������ׂĂ��Ȃ������̂ŁA���̗ǂ����������̓������̖��O�����v���o���Ȃ������B�O�\�N�ȏ�̔N�����^�C���E�X���b�v���ė����悤�ȋC�����������B�g�c�`�̑Ί݂Ɍ�����R���̃V���G�b�g�͐̂ƕς�炸�A�\�]�{���𑖂��Ԃ͂r�k�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă������A�ȑO�Ɠ����悤�ɑ����Ă����B �钆�ɎԂ����邱�ƂȂǖő��ɂȂ������̂ƈ���āA�Ί݂̌N���Y��ʂ鍑��56�������s�������Ԃ̐��͑����A�w�b�h���C�g�̗��鐔��̂悤�ɒ����q�����Ă����B ���͊C�݉����̓����A�������Ă��Ȃ��Ԃōs�����藈���肵�Ȃ���A�Ȃ��̂̋L�����@��N�������Ƃ��Ă����B �Y��Ă����L�������X�Ƒh���Ă����B����ӁA�Ί݂̏W������P���Ė���Ԃ����߁A�ĈΒe�̖����C��ʼn����グ�ĕY���Ă������Ƃ��������B����͋��낵�����ٗl�ɔ��������i�������B���̎��A��͊�h���Ă����Ƃ����l�ŏd���~�V���i�V���K�[�А��ŕꂪ��ɂ��Ă����j�Ƃ��A�I���K���Ȃǂ�����ĕ\�̓��H�Ɏ����o�����B��ŕ�͎������ǂ�����ĉ^�яo�����������Ŋo���Ă��Ȃ��ƌ����Ă������A���ꂪ������Ύ���̔n���͂Ƃ������̂ł��낤�B�܂��A�Z��ł����Ƃ���߂����̋����ŁA�ČR�̐퓬�@�̋@�e�|�˂��āA�Βi�̘e�̍a�ɐg���B���낤����ꂽ���ƁA���̉Ԃ̉��ł̏��w�Z�̓��w���̂��ƁA��̊C�Ŗ����̖�����������Ă������ƂȂǁA�l�X�Ȃ��Ƃ������Ȃ��]���ɕ�����ł͏������B ���鎞�A��ƌZ�Ǝ��̎O�l�ŁA�����b�N��w�����ėׂ̏W���܂Ŕ����o���ɍs�������Ƃ��������B�������̂��A���邢�͕�̒����ƕ��X�����ŎF�����ł���ɓ��ꂽ�̂��A���V���d���ו���S���ŁA�����т�����肩���āA���������ƂڂƂڕ������Ƃ��̐h�����v���o�����B �̂ƈ���āA�������L���̂́A�C�݂ߗ��Ă�����ɈႢ�Ȃ��B1���ȏ�̖h���ǂ����菄�炳��Ă����B���̋L���ł́A���̊C�݂͓��H�̉��������C�ŁA�����̎����l���͂��Ɍ���邾���ŁA�咪�̖������ɂ͓��H��G�炷�قǒ��ʂ��オ���Ă������̂��B���̕ӂ�̓��A�X���̊C�݂̂悤�ɓ���]�����n�̉��[�����荞�݁A�Ôg�̊댯�ɎN����Ă��邽�ߖh���ǂ��K�v�Ȃ̂��낤�B�i�ނ��A���̒��x�̖h���ǂő�Ôg�ɑς����邩�͋^��ł��邪�j ���������A�q�����������H�����Ăقlj��̍��l�ɔ�э~��ėV��ł��āA�V����̎��ɂ���э~���ƌ��������Ƃ��������B�s��炿�̎����A���ꂱ���ڂ�ῂލ����ɋ���ł���ƁA���̈����B���皒�����Ă��A���ʎv���Ŕ�э~�肽���̂��B���̎��̑�����S�g�֎��V���b�N�͍��ł��͂�����Ǝv���o�����Ƃ��ł���B ���̈����������炯�̍��l�ŕꂪ�C�l���E������A��Őe�ʒ�����A��H�݂����Ȑ^���͎~�߂Ă���Ƌ������������ꂽ���Ƃ��������炵���B�����������A�C��ő��ɒǂ�ꂽ�K�U�~���K���ɉ~��`���ē�������Ă���̂�ڌ������̂����̊ݕǂ������B �ݕǂ̊O�ɂ́A���������ɋ��t�̑D���W������Ă���̂������A���H�e�ɂ͖�ނ������l�̎Ԃ���������܂��Ă���A�h���ǂ̏�ɂ͒ނ������l�B�̃V���G�b�g�������߂��Ɍ������B���ɂ͎Ⴂ�j���̃y�A�[�̒ނ�l�������B ���͖�ނ�ɗ����ނ�l�̂悤�ɓ��H�e�ɎԂ��߂��B�Â��������A�|���|���E�E�E�ƃG���W�������������ċ��D���ʂ�߂����B�c�����̂��Ƃ����ꂱ��Ǝv���o���Ă������A���̊Ԃɂ������Ă��܂��Ă����B �L����A������i4��29���j
���͂��܂����Â����ɊႪ�o�߂��B��ނ�̐l�B�̎Ԃ͏����A�ӂ�͐Â܂�Ԃ��Ă����B�ݕǂ̂Ƃ���ǂ���ɓ˂��o���V��������A���ꂼ��̎V���ɂ͋��D���q����āA�����ɏ㉺�ɗh��Ă����B���܁A�Î��j���ďo������D���A�傫�ȕz�������ň����悤�ɁA�C�ʂ������đ����Ă����̂��������B �O�ȋL�������ǂ��āA�e�ނ̉Ƃ�T���Ă݂��B��A�O���̂���Ƃ��ڂ����Ƃ̑O�ɗ����ĕ\�D�����Ă݂����A���͋L���Ɠ��������A���O�͐S������̖������̂��肾�����B�e�ނ̓������́A�m�����j�������������A���O�������͉̂��̂��낤�B �e�ނ̉Ƃ�T���͎̂~�߂��B�K�˂鑊��̖��O����Ɋo���Ă��Ȃ��҂��A�܂Ƃ��ɑ���ɂ���锤�͂Ȃ��A�ӎU�������z�Ǝv����̂��������낤�B �ߊԂ���g�c���̕��ֈ����Ԃ����B�傫�ȋ�������]�ɉ˂���A���̌������ɏ��w�Z���������B�ȑO�ɂ͂��̋��͂Ȃ��A���w�Z�֒ʂ��̂ɓ���]��傫���I�Ă������ł���B���͓���]�̉��֎Ԃ𑖂点�A�̉j�����蕩��ނ����肵�ėV�A�����ȗ��r��T���Ă݂���������Ȃ������B ����ȏ㎸�����������߂�͎̂~�߂ɂ����B���Ƃ��A�m�荇���̐l�Ԃɏo�������A���������v���ł̏ꏊ�ɏ��荇�����Ƃ��Ă��A����炪�̂̂܂܂̎p�ł��锤���Ȃ��A����A�Ăт��̓y�n��K��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�ƍl����ƁA���ɂƂ��āA���݂̂��̓y�n�����A���̓y�n�̎v���o�̕����A�����Ƒ�Ȃ��̂Ɏv��ꂽ����ł���B�ɗ\�g�c�w�߂��̐H���Œ��H���ς܂��A�����̖ړI�n�A�L��������ďo�������B �L����́A�l���\��̒����]���ŁA�l���\��Ǝ}�����ꂷ��g���̖{���ŁA�S�삪���Q�����ɂ����āA���m���Ƃ̌����́A�����R�i1055���j�A�����R�i1096���j�A�n���R�i1128���j���̎R�X�𐅌��Ƃ��Ă���B ����56�����ʼnF�a���ɖ߂�A�F�a������́A����320�����œ������ʂ��������B�o�ځi�����߁j�Ƃ��������߂���ƁA�L���삪�����ɉ����ė���Ă����B����Ƃ����W���ōL����͍����𗣂�A�E�֑傫���Ȃ������B ���͍L���쉈���̓����㗬�Ɍ������Ďb���Ԃ𑖂点���B���������V�ŁA�E��Ɍ�����L����͗z���˂��ăL���L���ƋP���Ă����B�L����́A�͕��̍L���A�ɂ��ɂ₩�ȗ��ꂪ���X�Ƒ����A�l����ɍ��������k�������Ă����B �r���A�Ί݂ɗ��ꍞ��ł��铡��ƌ����荠�Ȏx���������A����n���Čk�̗l�q�����Ă���ƁA���̂����T�Ɉ��̎Ԃ�����Ă��Ē�܂�A�ނ�x�x��������l�̒ނ�l������āA���̕��ɂ͊�����ꂸ�A�������Ɖ͌��֍~��Ă������B���͕��C�ɂƂ��Ē��߂Ă������A�l���܂ŗ��Ēނ��̐�w���������邱�Ƃ��Ȃ��낤�Ǝv���A�������߂čL����̏㗬���������B ���~�Ƃ����W���œ��������w���������A�W�����߂����ӂ肩��A�k�͋}�ɐ[���Ȃ�A���H�̌��z�������Ȃ����B�㗬�Ɍ������ɘA��āA�v�X�k�͐[���Ȃ�A���H���r��Ă��āA���ɁA���H�H���̉ӏ��ňꎞ��~������ꂽ�B�Ԃ��~��Čk�̏㗬������ƁA���H����J��܂�3�`40���͂��낤���Ƃ����[���k��ꡂ��㗬�ւƑ����Ă���A���̕��ł͌k�ւ̍~������A�ȒP�ɂ͌����肻�����Ȃ��A���܂��ɂЂǂ����H���A�����Ɛ�܂ő����Ă���̂������A�Ȃɂ₩��ł�������ӋC�j�r���Ă��܂��A�����Ԃ����Ƃɂ����B �쉈���̓����A��̗l�q�����Ȃ��牺���ċ{���Ƃ������܂ŗ���ƁA�ׂ���������A���̉����̑Ί݂ɑ傫�Ȗ��}���ɒ���o���āA���ʂɉe�𗎂Ƃ��Ă���̂��������B�앝��30�������邾�낤���B���C�Ȃ����߂Ă���ƁA���̎��A�ŁA���ڂɂ��͂�����Ɣ��������オ��̂��������B ���͎Ԃ��߂Ă����Ƃ��̎��A�𒍎������B�܂������オ�����B�ԈႢ�Ȃ�����͋��̃��C�Y�������B���͂����ɂ��Ȃ�̑啨�̃A�}�S�����邱�Ƃ��m�M�����B ���͂����߂��ɂ��邨�{�̑O�ɎԂ𒓂߁A���̎��A�̃|�C���g�����S�Ăقlj����ɁA��ɍ~��铥�Ղ������ĉ͌��ɉ��肽�B�����͑傫�ȕ��̕��K�������B�E�݂͐��ۂ܂łт�����ƒ|�M���������Ă���A�d���Ȃ��ڂ܂Ő��ɐZ����Ȃ���A30���قǏ㗬�̗��ꍞ�݂̂ق��ɕ����Ă������B ���ꍞ�݂���5���قlj����ŁA�����Ȕ��オ�����B�S�g�̐_�o���A��u���k����̂��������B���̉��ɗ����ĕ��̒������̐���������ƁA���邢��A�\�����̗nj^�̃A�}�S�����ǂ������㗬�Ɍ����ĉj���ł���B���܁A�Q�ꂩ�痣��ĕ����яオ�����A�}�S���A���ʂ𗬂�鍩����ߐH����̂��������B�������ꂽ�A�}�S�����ɏW�܂��Ă���̂��낤���B���͗��ꍞ�݂ɂ����ƃt���C���L���X�g�����B�����ɐ_�o���ȑf�������C�Y�����������A������|���肵�Ȃ������B�ēx�L���X�g�������A��x�ƃ��C�Y���Ȃ������B�C�����ƃA�}�S�̌Q��������Ă����B ��قǁA�����オ�������A�̃|�C���g�ɋ߂Â����B�J�������ŁA�g���B�����͉����Ȃ��̂ŁA���́A�㗬�ɓ��������A�a�����ꉺ���Ă���̂�҂��Ă���A�}�S�̎��p�ɂȂ�悤�A�����ɉ�荞��Ŏ��A�̃|�C���g��_�����B���A�̃|�C���g�͎v���Ă����قǐ��ɕω��͂Ȃ��A���[������قǖ��������B���������Ղ�̎}���A���̌x���S�𔖂ꂳ���A��_�Ƀ��C�Y���J��Ԃ����Ă����̂��낤�B �����ɋ�������Ƃ킩���Ă����̂ŁA���݂͊���2���قǗ��ꂽ���ɐT�d�ɃL���X�g�����B�܁A�Z��L���X�g���J��Ԃ������A����͒��ق����܂܂������B����Ȃɔh��Ƀ��C�Y���Ă������͂ǂ��֍s���Ă��܂����̂��낤�B�����堂�H�ׂĖ������Ă��܂����̂��H ���߂����āA���C�Ȃ��݊��ɃL���X�g���Ă݂��B�h��Ȑ����オ�����B�ْ����ɂ�ł������ׂō��킹����u�x��A���b�h�͋������B���ꂫ�藬��͒��ق����B ���v�������B�ߑO�\���������B���������₽���ῂ����M�������B�S�g����͂������A�����Đ��ŃL���X�g���Ă���悤�ȏ�Ԃ������B300���قǑk���Ă����ƁA�傫�Ȑ��͌��◬��̒��ɓ_�݂���悤�ɂȂ��Ă����B�W���͂���������Ԃ��������A��◬���̂���ӏ��Ń��C�Y���������B���ӎ��ɔ��˓I�ɘr�������ăA�}�S���|���Ă����B ���̓����߂ẴA�}�S�������B�ɂ��������F����тт��������ɁA��F�̔��_���N�₩�ɕ����яオ���Ă����B�̒���20�����Ƃ���قǑ傫���͂Ȃ��������A����Ȃ����������̂������B���ꂩ���̓|�c�|�c�ƒނꂽ�B�삪�傫���J�[�u���Ă��鏬�w�Z�̍Z��̉��ŁA���̓��ő��25�����̂��ꂢ�ȃA�}�S���ނ�A������@�ɊƂ����߂��B �Ԃɖ߂�A���H���ς܂��A���̖ړI�n�A������Ɍ����ďo�������B
������ �����������������Ԃ��A�o�ڂō���361�����ɓ���A�y�]�{���̏��ۉw���߂��Ă����ɁA�����k�J���ʂƌ����W�����������B�����k�J�ƌ����͖̂ڍ���̏㗬�ɂ���ƌ������Ƃ�n�}�Ō��Ēm���Ă����̂ŁA���łɖڍ����`���Ă݂悤���ƁA�W���̎w���e���ɓ������B �ڍ��Ƃ����W���ɏo�āA�ڍ��쉈���̋Ȃ��肭�˂�����������Ȃ���A���܌������̗l�q�������B�k���ƌĂԂ̂��͂�����قǁA�k���Ƃ͒������k���ŁA���͗��݁A�ݕӂ܂ŎG�����������Ă��āA���������J�����c���������ނꂻ�����Ȃ������������B�A�}�S���ނ��̂́A�����A�����k�J����㗬�ł��낤�B ���͓����}�����B�v��ʉ����ŁA���Ԃ�啪���X���Ă��܂����B�Ö��Ƃ����W�����߂���ƁA�}�Ɏ��E���J����O�Ɏl���\��̖{�����������B�v�킸����ۂB���X�����͂������B�앝�̍L����͑��ɂ���R���邪�A����قǐ��ʖL���Ȑ�͖ő��ɂȂ��B�������A����قǂ̑�͂ɂ��āA����قǐ��w����ۂ��Ă����͑��ɂ͂Ȃ����낤�B���܂ŁA�l���\��̎x�����茩�Ă����̂ŁA��X�Ɋ�O�ɏo�������{�����A����������Ɍ�����̂��낤���B �Ñ勴�Ƃ������̒��قǂŎԂ��߂Ď��͂������B���ʂ�ꡂ������Ɍ������B����������ƁA�l���\��͍��֑傫���Ȃ���A����i���݁j�ɂ͍��l�̂悤�ɔ��B�����͌����g����A�����t���̒��^�̗V���D����ǁA�D����݂Ɍ����Đ�݂Ɍq����Ă����B�V���D�̎�O�̉͌��ɂ͋�������M���������ɖ��܂�Aꡂ������ɁA�싙�t�̏�������D���������B�L���͌��ɂ́A���̑����̎l�쓮�Ԃƃe���g��������Ă���̂������邾���������B �E�݂͐藧�����}�s�ȊR�ɂȂ��Ă���A���̊R�������オ���č���200���قǂ̎R�ƂȂ��ĉ����̕��ւƘA�Ȃ��Ă����B ������㗬������ƁA�E��i���݁j�ɑ傫�ȉ͌�������B����i�E�݁j�̎R�́A����ނ��āA�����̂悤�ɐ�����͂�ł���B�R�̐��ƁA��Ƃ̊Ԃ̋�����ԂɁA�������Ă����X��������A�X���ɉ����ē�d�A�O�d�ɐl�Ƃ���������ł����B �ӂƎR��������ƁA�����Z���̐��ؗ��̊ԂɁA�̓��������F���ϐF���Ă�������������B��������{���{�ł͂Ȃ��B�����������ɁA���ɂ���Ă͐��\�{���A�Ȃ�悤�Ɏ��������F���ϐF���Ă����B������i�E�݉����j�̎R�������悤�ȏ�Ԃł��������A�����߂��āA���ꂪ���̖ŁA�ǂ̂悤�ȏ�Ԃł���̂��悭������Ȃ������B ����n��A������������āA�l���\�쉈���̌�����쉺�����B�r���A�����i�Ȃ��j�ƌ����Ƃ���́A��ɖʂ����R�̏�ɋx�e��������A�W�]�䂩��l���\�삪�悭���n�����B�W�]��̑Ί݂́A�R�̎��X�����������F���Ȃ��Ă���B�ӂƋC�����ƁA�W�]��̗����́A���L���Γ͂��قǂ̋߂��ɂ��A�}�̐悪���F���Ȃ��Ă��������ł͂Ȃ����B�悭����ƁA����͌I�̉Ԃ�Z�������悤�ȉ��F���ԂŁA���̚삵���Ԃ̉��������F�����߂Ă���̂��B�n���̐l�ɐu���Ƃ��̖͒Ńm�Ƃ̂��Ƃ������B �ȑO�A�a�̎R���́A�Í���̑�̔q�Ƃ������ł��A����Ɠ������i�ɏo��������Ƃ��������B���̎��͂Ȃ��悭�����炸�A�|�̎�t���������낤�ƕЂÂ������A����Ɠ����Ńm�������ɈႢ�Ȃ��B�����ɐ����C�݂ɋ߂��A���g�Ȑ�Ɏ������邱�Ƃ������X�_�W�C���낤�B�����ۂ����̗t�ƁA�ΏƓI�ɖ��邭�h��ȉ��F���Ԃ͂悭�ڗ��B�����O����E���ƁA���ɒ�����ł������F���Z�[�^�[���ς��ƌ��ꂽ�悤�Ȋ����������B ������́A�������Ƃ������Ŏl���\��ɍ������Ă���B���͌������勴��Ί݂ɓn�荕���쉈���̓���k�����B�l���\�쐅�n�̌k���ނ��Ƃ��āA�����炭�œ�[�Ɉʒu���Ă���Ǝv����̂��A���̍�����ł���B�����k���s���ė���Ă���ڍ��삪�A������˂������Ĉ��Q���̉F�a���s�ɒB���Ă���̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA������͍Ō����ɂ�����܂ō��m�����ɗ��܂��Ă���B�l���\��̎x���̒��ł��ł���翂ȁA�鋫�I���݂̌k�ł���B ������̗��݂ɂ��Ńm���悭�������Ă���A���������ɉ��F���Ԃ�����ꂽ�B���͂Ђ�����㗬��ڎw�����B�r���A�R����̕����H�������Ă���ӏ�������A���̓����t�����Ă����B�Ŕ��o�Ă��āA�ߌ㔪���ɂ͒ʍs�~�߂ɂȂ�Ə�����Ă����B���v������Ƃ����ߌ�l��������Ă����B �����̏W���ɒ������̂͌ߌ���߂������B�W������1�����قǏ�����Ƃ���ɁA�c�я��̍�Ə��������������Ă���A���̏����̑O����ނ�n�߂��B�ŋ߁A�㗬�œ��H�H���ł������炵���A�k�͓y���Ŗ��܂��Ă����B���܂���ނ���ς���̂��ʓ|�ŁA���̂܂ܒނ������B�傫�ȓ|���k�s��W�����肵�āA�k�͍����r��Ă����B���^�̃A�}�S���l�`�ܕC���ނꂽ�Ƃ���Ŏ��Ԑ�ɂȂ����B�㗬�ɍs���A�����Ɨǂ��ނ�ꂪ����ɈႢ�Ȃ��������A�㗬�ɒނ�ɍs���ƁA�A�蓹�A�ʍs�~�߂Ɉ����|�����Ă��܂��B�[�H�̗p�ӂ��Ȃ��ŁA��h�͂����ɂ��h�������B���͉������c���ĎR���������B �������ŁA�E�܂��ׂ��Ƃ���i���Ă��܂��A�{���Ƃ������ɏo�Ă����ŏ��߂Ē��������Ԃœn�����B���v��̔���̒��A�����̖����̂���ڂ��̋���n��̂́A���ɐS�ׂ������B���͋����l���\�쉈���̓��𒆑��s�ڎw���ĎԂ𑖂点���B�ӂ�͂�������Â��Ȃ��Ă��܂����B�X���͂��납�A�l�Ƃ̖�������������A����Ⴄ�Ԃ��ő��ɗ��Ȃ������B ���͐�قǂ��疧���ɐS�z���Ă������Ƃ��������B����̓K�\�������c�菭�Ȃ��Ȃ��Ă���A�o���邾�������������������ĕ⋋����K�v������Ƃ������Ƃ������B�������A�s���ǂ��s���ǂ��A�X�^���h�͖����A�Ƃ��Ƃ������s�ɒ����Ă��܂����B�������`�����s�܂ł̖��\�L���̊ԁA�ꌬ�̃X�^���h�������������ƂɂȂ�B �����s�ɓ��������ɂ́A���v�͌ߌ㔪���������ɉ���Ă����B���͍���56�������h�ѕ��ʂ֎Ԃ𑖂点�����A�ǂ̃X�^���h���ߌ㔪���ʼnc�Ƃ��I���Ă����B�����s�����������������������A�J���Ă���X�^���h�͈ꌬ���Ȃ������B �����͒��߁A�y�������w�O�̐H���Œx���[�H���ς܂����B��̋㎞�ł́A���ق�������͓̂�����A����ƂāA�ǂ��ֈړ�����ɂ��A�K�X���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���͑��~�߂�]�V�Ȃ�����A�w�O�̍L��ɒ�߂��Ԃ̒��łڂ��肵�Ă����B�w�O�̍L����\�����̖쌢�̌Q�ꂪ�������Ă����B���́A�Â����m�N���[���̉f������Ă���悤�ȋC�������B ���͂ǂ����A�C�݂̋߂��Ŗ閾�����������Ǝv�����B���܂艓���ւ��s���Ȃ��̂ŁA�y�����낵���S���������̓y������w�ɋ߂��`�ɎԂ𒓂߂��B�J���������~��n�߂��B4��25���ɓ������Ĉȗ��A���߂Ă̖{�i�I�ȉJ�������B�J�̉�����ꂽ�̂ɐS�n�悢�h���ƂȂ��āA���̂܂ܐQ�����Ă��܂����B
�k��x���E����X��i4��30���j ���Ⴊ�o�߂�ƉJ�͏オ���Ă������A�������������B�����ɃX�^���h���J���̂�҂��āA�������Ă�������B�w�߂��̃R���r�j�ŁA���ƒ��ٓ̕������B���͖�x���Ďl���\������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA�����s���̎l���\�싴��n���āA�Y��Ȏl���\��߂Ă݂��B �k��x���̉���X��i���X��ł��ǂ������̂����j��ڎw���āA����439������k�サ���B�����͎l���\��̎x���Œ����s�ō���������ƕ��s���đ����Ă���A��p�i�����䂤�j�Ƃ����W���܂ł͓������L�����K���������A���𗣂ꂽ�ӂ肩�瓹�͈����Ȃ����B�Ȍ�A����Ƃ������Őm��c��i�n��j�ɏo��܂ŁA���X��\�L���قǖ��ܑ��̎R�x���H���������B���̓��́A����̗��̒��ōň��̓��������B���肩��A����439�����͍���381�����ƍ������Đm��c�쉈����k�サ�A�c��X�ōĂѓ�{�ɕ������B�l���\����c��X�Őm��c��Ɠ�����ɕ�����A����439�����͓�����ɉ����Ėk�シ��B �����쉈���̍���439�����������Ċy�ȓ��ł͂Ȃ��B���炭�k�シ��ƁA�l���\�쐅�n�ő�̒Éꔭ�d���̃_���ɏo��B�l���\��̓_���̖�����Ƃ��Ēm���Ă��邪�A�n���L����ɂ̓_���͂Ȃ����A���̓�����ɂ̓_������R����Ă���B�Éꔭ�d���̃_���̑��ɁA�k��Ƃ̏o������̎搅���A���n�_���A�R�q�_���ƁA�O�̃_�����W�����č���Ă���B �����Ƃ����Ƃ���ō����͓�����ƕ�����A�x���̖k��ɉ����Ėk�シ��B�V�C�͉������A���͉v�X���������r��A�C���͋}�ቺ�����B ��Ì��Ƃ����W���ŁA����X��ւ̗ѓ��ɓ������B�k��ɉ˂����Ì����̎�O�ŎԂ𒓂߂��B���v������ƁA�ߌ�ꎞ������Ă����B�����s���ߑO�����ɏo�����āA���Ɍ��Ԃ��߂������ƂɂȂ�B���H���ς܂��A��������Ėk��̍��݂ɓn��A����X��̍����_������k�����B�@����X��́A�郖�X�i1053���j�𐅌��Ƃ���A�K�͂͏����������e�̔Z���D�k�ł���B�܂���̋����ŁA�̗t�A�͂�}�A�ԕГ��A�l�X�ȗ�����������Ă��āA�t���C�E�t�B�b�V���O�̎ז��ɂȂ����B���b�h�͕��ɐ����A���T���C���̃��C���E�R���g���[�������Ȃ�Ȃ���Ԃ��������A���e�̔Z���͔��Q�ŁA�nj^�����X�ƃq�b�g�����B �ӂƉ͌�������ƁA��̉��݂̗��܂萅�̐��ʂŁA�����߂��Ă��鏬���Ȓ�������B���͂��̒��������ƝS��Ō��Ă݂��B�J�G�f�̉ԂɏW�܂�N���g���J�~�L���������B���̕��ł́A�����̓e���X�g���A���i���������j�����̂��߂ɑ����������A�A�}�S�͂�����ߐH���Ă���ɈႢ�Ȃ��B ���݂ɑ傫�Ȓ�����̊₪�����ė�������߁A��̊Ԃ��i��ꂽ��������オ��悤�ɗ���Ă���Ƃ��낪�������B���́A�t���C����̊Ԃ𗬂��悤�ɏ㗬�ɃL���X�g�����B��̊Ԃ���t���C������o�悤�Ƃ����u�ԁA�t���C��ǂ��ĕ��シ�鋛�e���`���b�ƌ��������A���]���Ă����ɒ���ł��܂����B���Ȃ��^�̉e�������B���͍ēx�g���C�����B��x�ڂ̃��C�Y�͍ŏ��̂��̂�肩�Ȃ葬���������A���x�͐��ʂɊ���o�����B���킹��Ƃ����������|���肵���B���͋��ɒ�R����ɂ�^�����A�����ɊݕӂɈ�������グ���B��^�̌����ȃA�}�S�������B�ځi30�����j��ꡂɒ����Ă����B�l���\��ł̏��߂Ă̎ڃA�}�S�������B���͂��̃A�}�S���ݕӂ̐ɒu���A�ʐ^���B���ă����[�X�����B�ߌ�O�����������A��͓܂��ĕӂ�͗[���̂悤�ɈÂ������B
���̌������H���̂悤�ɒނꑱ�������A���k�n�_����7�`800���قǑk�s����ƁA�k�͓�{�Ɏ}�����ꂵ�A���ʂ������ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�ނ���グ���B���̒Z����ԂŁA�ڋ����܂߂ď\�l�A�ܔ��̃A�}�S���ނꂽ���ƂɂȂ�B ����X��̏o��������A�k���600���قǑk��ƁA�x���̏��X�삪���������݂ɗ��ꍞ��ł���B���́A���X���`���Ă݂���肾�����B���X��͓��H�Ƃ͔��Α��Ȃ̂ŁA�k���k���đΊ݂ɓn��K�v�����邪�A�[���ĂƂĂ��n�ꂻ���ɂȂ��B�d���Ȃ��A�����_���炩�Ȃ�㗬�ɉ˂���ꂽ����n���āA���X��ɓ��k���悤�Ƃ������A�Ί݂̓��͌k����ꡂ��������ɂ����āA���~�ł��������Ȃ��B�[�����߂��Ƃ������Ƃ�����A�c�O�������X��̒ނ�͒f�O�����B ����ɂ��Ă��A�l���\�여��ɂ́u��X�v�ƕt���n�������Ƒ������Ƃ��B����X��A���X��A��X��i�\�a���j�A�c��X�A�Ö���X�i�吳���j�A�c��X��i�������j�Aꠖ�X�i��쌩���j�A�{��X�i�������A��쌩���j���X�A���ɂ��܂����邩���m��Ȃ��B�u��X�v�Ƃ����̂́A��́A���̈Ӗ����낤�B �[���ɂȂ����̂ŁA���낻��h�����߂悤�Ǝv���A���X��o��������A�k�쉈���������k�サ���Ƃ���ɖ��h�������āA���̖�̏h�𗊂��A�\�����Ƃ������ƂŒf���Ă��܂����B�d���Ȃ��A�����ŏh��T�����Ƃɂ��č���197�����ɓ���A�����Ɍ��������B �r���A���Y������Ƃ������ɐH�����������B���̋G�߂ɂ͒������₦����ł����̂ŁA�g�����H�ו����~�����Ȃ�A�����𗊂B �H���̏����́A���̓y�n�ɂ͏�Ⴂ�Ɏv����قǁA�����̏�i�ȕw�l�ŁA�h�̏Љ�𗊂ނƁA�����ɐ����ɓd�b���Ă���A�߂��́u�F�T�v�Ƃ������h���Љ�Ă��ꂽ�B �H���̑O����A�������ɑ���������ʂ��čs���ƁA���h�E�F�T�͂����Ɍ��������B�F�T�̌����́A�Â��_�Ƃ��قƂ�ǎ���������ɁA���̂܂ܖ��h�Ƃ��Ă���炵���A�Ŕ�������������茩�߂����Ă��܂��Ƃ��낾�B �H���̏���l����A�����s�����炵���A�F�T�̏���l�������o�}���Ă��ꂽ�B���͂��̖�̏h���𗊂݁A�[�H�܂łɖ߂�ƌ����āA�Ăы߂��̌k�̗l�q�����ɍs�����B�Ԃ𑖂点�đ��Y����ӂ̌k��`���Ă݂����A��������M��Œނꂻ���ɂȂ������̂ł����Ɉ����Ԃ����B�J�����~��Ȃ��������A�t�̗��������r��A�C�����ቺ���A�ň��̏������B �F�T�̏���l�́A���\�O��́A�m�I�Ȋ����̏����ȏ����ŁA���ɍb�������̎����傾�����B���C�ɓ���̂͂��������҂��Ă���ƌ���ꂽ�B��ԉ��̕����ɒʂ��ꂽ���A�L���͂Ȃ��A���ւ��炻�̕����܂ł̓r���̓�Ԃ́A���Ŏd��ꂽ�����Ȃ̂ŁA���C�֍s���̂��A�g�C���ɗ��̂��A���̓���ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �F�T�̏]�ƈ��́A���̏���l��l�����������B�q�͎���l�����B���C�ƐH����҂ԁA���͕����Œn�}���g���ė����̒ނ�̗\��𗧂ĂĂ����B�����̖�ɂ́A�l���𗧂��A��������肾�����B �\���قǂ̍L�������������B�Â��u���Ȃǂ��u����A�̂̐����̖��c�肪���̂܂c���Ă������A�����́A�ǂ��̖��h�ł��悭��ɂ�����̂������B�ӂƁA�����̏�Ɋ|�����Ă��鐔�_�̑傫�Ȋz�ɓ������؏����ڂɗ��܂����B�߂Â��ēǂ�ł݂��B����́A����n���̑�w�ƁA�����̑�w�̑�w�@�́A���Ȃ�̂̑��Ə؏��������B��w�@�́A�C�m�A���m���ے��̏C���؏����������B ��ŏ���l�����̊z�ɕt���Ęb�����Ă��ꂽ�B���̐����ʂ�A����͔ޏ��̈�l���q�̑��Ə؏��������B�����̑��q�炵���A�����ɂ��ւ炵�����������A���ꂪ�������}���ɂ͕������Ȃ������B�ނ͍��A�n���̑�w�Ő��w�̋��������Ă��āA���X���Ƃɂ��A���Ă���Ƃ̂��Ƃ������B ���C���Q���������B�ޏ��́A�J��̐��������Ă���̂ŁA�������܂�̂Ɏ��Ԃ����������ƁA�\����Ȃ������ɘl���������B�y�Ԃ̉��ɕ��C�ꂪ����A���C�͒������܉E�q�啗�C�������B�₦���̂ɔM�����͗L�������B ���C����オ��ƐH�����҂��Ă����B�h�g���Ԃɍ��킸�����Ȃ��ĂƁA�܂��l�т�ꂽ�B���̑���A�R�̓V�Ղ炪�R�̂悤�ɐ����Ă����B �H�����I����āA�܂��l���R�b�������B�Ⴂ���ɁA���S���������v��S�����A��l���q����Ă���J�b�����Ă��ꂽ�B�����̑�w�ɒʂ����q�Ɏd��������邽�ߖ��h���n�߁A�_���H���⍑���H���̎������ƌ_�A��ƈ��h�ɂƂ��Ē����肵�Ȃ���A�������グ�����Ɠ���b���Ă��ꂽ�B���̋�J�͕����̂��̂ł͖��������������A���̌����͏�������J�����������Ȃ������B�ޏ��̊z�ɂ�������ƍ��܂ꂽ�[���cᰂ������A�����̐h�_���ؖ����Ă����B�S�J�́A���܂ł��c��Ώ��̍��̂悤�ɁA�[��ᰂƂȂ��Ċ�Ɏc���Ă��܂��悤���B �b�̒��ŁA�����̘Z�V�V�ƌ������t���o�Ă����B�ŏ��������Ƃ��ɂ͉��̂��Ƃ������炸�A���y�|�\�̎��q���������Ǝv�������A��ŁA�������i�ׂ̒Ö쑺���܂ށj�o�g�́A�Ή��̘Z�u�m�̂��Ƃ��ƕ��������B�����A�ޗǂ̓V�n�g�̋g���Ց��Y�A���s�̒��E���̓ߐ{�r�����l���́A�n�����������ւ�̐l�B�Ȃ̂ł���B �b�����Ȃ���A��q�̌��Ԃ��琁�����ށA�₽�����ԕ����C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ������B�Q�Ă���Ԃɕ��ׂ������Ă��܂��������������炾�B����l�����c�������Ă��ꂽ�B�������ԕ����C�ɂ��Ă���̂��@���āA�����Ɉ�Ԃقǂ̛����𗧂ĂĂ��ꂽ�B���͂҂����ƎՂ�ꂽ�B���̎����߂āA���͛����̎��p�I���l�̍�����m�����B �����A���h���o������Ƃ��A����l�͎��𒓎ԏ�܂Ō�����ɗ��Ă��ꂽ�B�ޏ��́A���̃��S���̉ב�ɎR�Ɛς܂ꂽ�ނ蓹��◷�s�p�i�̈ꎮ�߂āA �u�C�܂܂�̂��A�C�܂܂�̂��v �Ɗ��Ɋ����ʂ悤�əꂢ���B ��c�ː�A�c��X��A���m���i5��1���j �������͗₦�����A�V�C�͂�����������B ���͓������ɏo�āA����440�����ɓ���A������̏㗬�Ɍ��������B�啨�������|�C���g�ɍēx���킷�邽�߂��B��c�ˌ��̓�{�ڂ̋�������k�����B�l���O��4��27���ɁA�啨�̋��e������������T�d�ɑ_�������A�啨�͎p�������Ȃ������B�b���ނ���A�����ނ����Ƃ���œ��ɖ߂����B ���̑_���́A�c��X��̎ڕ����B���͎O���O��4��28���ɁA�啨�����킹���Ȃ������̑傫�ȃv�[���̗��ꍞ�݂ɓI���i�����B���͗ѓ��ɎԂ𒓂߁A���ڃR���N���[�g�̋��܂ō~��Ă������B���̎�O�Ŕ��d����V�l�Ɂu�ނ�邩���v�ƁA�����ꂽ�B ���͑O��̃~�X�ŁA�A�}�S�������ɂ��邩�������Ă����̂ŁA�T�d�ɃL���X�g�����B����L���X�g�������A�z�͒��ق����܂܂������B ����̑�c�ː�Ɠ����ŁA�������C�Y���Ȃ��̂��ƒ��߂��B����Ɨ��ꍞ�݂́A�A���������ӂ�Ń��C�Y�������B�܂����Ă�����������A���킹���x�ꓦ�����Ă��܂����B ���͑��߂̐H�����ς܂��A�܂��^�����Ă��Ȃ����t��i�n��j�֏o�������B ����197�����őD�˂܂ōs���A�D�˂��珼�t�쉈���̌�����쉺�����B���͊뜜���Ă����قLj����͂Ȃ������B�v���H�Ƃ����W���ŁA���t��ɉ˂��鋴��Ί݁i�E�݁j�ɓn��A�����ɍ������Ă���x���̓��m���̏㗬��ڎw�����B����n��O����A�������̎�舵�����̊��Ƃ��Ŕ�{���Ă������A������Ȃ������B���m��̏W���ɒ�������u���Ă݂邱�Ƃɂ��Ă��̂܂Ԃ𑖂点���B ����̒ލs�̎��s�́A����ɋ��ƌ��̈قȂ����A��{���ނ������Ƃł���B�����l���\��ł��A���t��A�l����A������A�k��A�L����A������̊e�x���́A���ׂċ��ƌ����قȂ�A�]���āA����ɓ����������̔̔�����T�����A�w�����Ȃ���Ȃ炸�A�s�o�ςł�����肩�A���Ԃ�Q��Ă��܂������Ƃ��B ���m���̐����́A�郖�X�i1054���j�ŁA����ڃA�}�S��ނ�������X��Ƃ́A�R������Ŕ��Α��ɓ�����B���m��̏W���ɒʂ��铹�́A�ܑ��������Ă��Ȃ����A���ꂢ�ɋς��ꂽ�ǂ����������B�k���̗ǂ��ɂ��āA�r���ʼn��x���Ԃ��~��ĊƂ��o���Ă݂����A�ނ��̂̓J�����c���肾�����B���ʂ͑����A���ݐ��Ă����B��͔�����悤�ɐ��A�C���͂���㏸���Ċ��ނقǂɂȂ����B ���m��ɒ��������́A�ߌ������Ă����B�W���Ƃ͖�����ŁA�l�A�܌��̔_�Ƃ��_�݂��邾���������B�W���͐�̑Ί݁i���݁j�ɂ���A�E��ɑΊ݂ɓn�鋴���������̂ŎԂ��߁A���̂ق��֍~��čs���A��̗l�q�����悤�Ƌ��̉���`�����B����Ƌ��̉����Œނ�����Ă���V�l���������B�V�l�͎��X�A��ɂ����q�����g���ߒ��Ԃ�U��Ă͉�����߂܂��A�܂��ނ�n�߂�B���������s�v�c�ȓ�����J��Ԃ��Ă����̂ŁA���͘V�l�ɁA�������Ă���̂��q�˂��B����ƁA�g���{���a�ɂ��ăJ�����c��ނ��Ă���Ƃ����������Ԃ��Ă����B�����ꏊ�ʼn������ނ�Ă����B���͘V�ނ�t�ɁA�����œ��������Ă���Ƃ͂Ȃ����Ɛq�˂��B�����Ƃ������Ƃ������̂ŁA�d���Ȃ��������̍w���͒��߂��B ���m��ŁA�k�͎O���Ɏ}�����ꂵ�Ă���B���͗ѓ��̂��鍶����ނ낤�ƁA�Ԃ𒓂߂Ēނ�̎x�x�����Ă����B���̌y�g���b�N���ѓ��������Ă��āA�����T�ɒ�܂����B�^�]�䂩��Aᰂ��炯�̓��Ă������V�l������o���āA�������������Ă��邩�Ǝ��ɐq�˂��B���͂����֗���r���������̎�舵�������ꌬ���Ȃ��A�w���ł��Ȃ������Ɛ����ɓ����A�����O�A�D�˂Ŕ��������t��̓������������A�V�l���������������Ă���̂Ȃ甄���Ăق����Ɛ\���o���B�V�l�͏����������悤�Ȋ�����Ă������A�܂������ł��傤�ƌ����A�A�}�S�ނ��͂��̂����肩��㗬�����A���֓����ɒނ�������āA�吨�̐l�����������Ă�������A�ނ���Ă����w�ǃA�}�S�͎c���Ă��Ȃ����낤�ƌ����c���āA�܂��Ԃ��^�]���čs���Ă��܂����B ���́A�Ԃ𒓂߂����̂����߂��Ɍk�ւ̍~����������Ēނ�n�߂��B�k�́A�M��ƌĂԂقǂł͂Ȃ������������B�b���ω��̖������������������A�k�����ǂ��Ȃ�ɘA��Ēނ�n�߂��B�r���A���������g���l���̂悤�Ɍk���ĈÂ��Ȃ��Ă���Ƃ���ɁA���x���ꂪ�J�[�u���Đ[���Ȃ��Ă���D�|�C���g���������B���ꍞ�݂̏㗬����A�t���C�𗬂����B�ڋ߂��啨������o�������A��|���肵�Ȃ������B2�����قǒނ�オ���āA�ɂȂ��Ă��鏈�ŊƂ�[�߂��B�nj^������ŁA�}����\���قǂ̃A�}�S���ނꂽ�B�l���\��̒ނ�̍Ō������ɑ��������ǂ��ނ�����邱�Ƃ��ł����B �k����オ���ėѓ��������Ă���ƁA���[�̋n�Ɉ��̃I�[�g�o�C����܂��Ă��āA��l�̎Ⴂ���C�_�[���A�����ȃe���g���Ă���̂ɏo������B����ȎR���ŎR�d���ȊO�̐l�ɏo��Ƃ͗\�z�����Ă��Ȃ������̂ŁA���������������B�u�����́v�ƁA�o�R�ғ��m�̂悤�ɒZ�����A�����킵�ĕʂꂽ�B ���m���Ɠn�삪���������v���H����A1�����قǓ쉺�����Ƃ���ɂ��鉹�H�Ƃ����W���̃R���r�j�ŕٓ����ė[�H���ς܂����B��쌩�Ƃ����g���l�����č���560�����̎��q���ɏo�āA�l���\��ɕʂ���������m�s�Ɍ��������B���̉��蓹���玞�܌�����A�v��C�݂̚삵�����̓����V�N�ŁA�Ђǂ�������������ꂽ�B�i2001/11/15�j �@ ©2001�@(���f�œ]�ڂ��邱�Ƃ��ւ��܂�) |