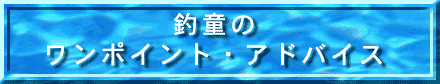
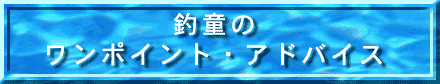
|
釣童のF.F.ワン・ポイント・アドバイス(1) |
|
|
F.F.を始めた後輩たちが、1尾でも多く渓魚を手にすることが出来るように、今後いろいろと思いつくままに、アドバイスをしていきたいと考えている。 複数の魚種が混棲する釣り場で、アマゴ(ヤマメ)だけを釣るにはどうすれば良いか? 伊豆の渓流のように水温の高い渓では、アマゴの他にカワムツ、ウグイ、オイカワなどの外道(釣り人は対象外の魚を外道と呼ぶ)が混棲しているが、これらの外道を避けてアマゴだけを釣るにはどうすれば良いのだろう。 数年前の3月末、F.F.歴2年の若い釣友と伊豆の渓で釣ったことがある。私が釣ったのはほとんどアマゴだったが、彼が釣ったのは90%が外道のカワムツだった。彼がどういうポイントで釣っているのか見ていると、彼は流れの緩い瀞場とか、緩い巻き込みばかりを狙っていた。私は彼に瀬の流心とか、流れの速いポイントを狙うようにアドバイスした。その後、彼はカワムツをあまり釣らなくなった。 アマゴとカワムツの釣り分け方 アマゴとカワムツを釣り分けるには、瀬の流心とか、とにかく流れの早いポイントを狙うことで、アマゴだけを釣ることが出来 る。尤も、速い流れといっても、波打って流れ下るような落差のある激しい流れには、アマゴはいない。 アマゴとウグイの釣り分け方 大場所(水深のある、流れの緩い瀞場)を避け、小場所(落ち込みの肩、落ち込みの脇、沈み石の周囲など)や、分流を狙うこと でアマゴを釣ることが出来る。 アマゴとオイカワの釣り分け方 アマゴとオイカワは、一時期同じ流心のポイントで釣れるので、釣り分けるのは難しいが、落ち込みの肩や、落ち込みの脇、岩陰 などの小場所や、堰堤や落ち込みの下の緩い巻き込みでアマゴを釣ることが出来る。普通 、オイカワは複雑な流れや、淵のような緩い流れにはいないものだ。 アマゴとアブラハヤの釣り分け方 アブラハヤは、好冷水性の魚でシーズンを通してアマゴやヤマメと混棲している。アブラハヤはどちらかといえば流れの緩いところを好むので、瀞場や、緩い流れを避ければ、アブラハヤを避けることが出来る。 釣り場によっては、3種類以上の魚が混棲している場合があるが、そんな場合でも、流れの速い流心や、小場所、分流などを狙えば アマゴやヤマメが釣れるだろう。
|
|
釣童のF.F.ワン・ポイント・アドバイス(2) |
||
|
先行者のある釣り場で、釣果を上げるにはどうすれば良いか? 都市近郊の渓流で、土、日はおろか平日でさえ、先行者がいない釣り場など、まず皆無といって良いだろう。私は30数年の長いサラリーマン生活を通 じて、条件の良い日を選んで、平日に休暇を取って釣りに行けたのは、それこそ数えるほどしか無い。これは別 に私に限ったことではなく、平均的なサラリーマンにとっては、ごく当たり前のことである。 敏感で警戒心の強い渓魚を釣るのに、先行者がいるということは致命的ともいえる悪条件である。かといって餌釣り師のように、朝一番に入渓しても、渓魚の餌であるカゲロウなどの水棲昆虫はまだ飛び回ってはいないから、殊にドライ・フライで釣りたいフライ・フィッシャーにとっては、あまり意味の無いことである。 我々釣り人にとっては、先行者がいる場合の釣り方(対策)は、釣果を左右する一大問題である。釣り人は、餌釣り師、フライ・フィッシャーを問わず、それぞれ経験を積み重ね、先行者対策を立てる。その対策は一人ひとりの、いわば企業秘密であり、決して他人に漏らしたりしない。私は、今まで多くの釣りの本を読んだが、「先行者のある釣り場における釣り方」が詳しく書かれた本にお目にかかったことは無い。
先行者が、どのくらい前に通過したかを知ること 河原の石に、点々と生々しい濡れた足跡が付いているようなら、先行者は100m以内にいると思ってよく、この場合は、少なくともその足跡が完全に乾くまで待つか、釣り場を替えるようにする。 先行者の釣りの種類、釣りの癖を見分けること 先行者が餌釣り師か、フライ・フィッシャーか(テンカラ師を含む)を見分けることが大切である。餌釣り師はあまり浅い瀬を狙わないので、浅い瀬でライズがあれば先行者は餌釣り師だと考え、水深のある淵や深瀬の流心は狙いから外すようにする。 先行者が、フライ・フィッシャーか、複数だと思われる場合の釣り方 (a)まず自分で思いつく限りの、ポイントと思われるポイントにフライをキャストして、先行者が見落としたポイントが無いか探ってみる。ライズするポイントがあれば、先行者がそのポイントを見逃したものとみなして、その後はライズのあった同じポイントに的を絞って攻めるようにする。 (b)先行者が見送ったと思われるポイントは、労を厭わず攻めること。決して危険を冒すことを推奨する訳ではないので、危険を感じたら止めて欲しいが、荒瀬の対岸にある落ち込みの肩とか、流心を越したところに突き出している大岩の、釣り人にはその岩が死角になって見えない、岩の向こう側のポイントなどに、苦労して渡渉し近づいて狙うことで、釣果 を上げることが出来る。 (c)5月を過ぎると、雪代が続いている渓を別にすれば、渓魚は、羽化した昆虫を狙って瀬に出ていることが多い。この時期に、落ち込みや淵にいる魚は、大半が先行者によって追い込まれたものと見て良いだろう。 落ち込み脇にある緩い巻き込みの、落ち込みに近い個所は、ヤマメ(アマゴ)やイワナの好ポイントで、多少時間をかけてもトライしてみる価値がある。このポイントでのライズは、非常に神経質で素早いことが多いので、合わせ遅れないように気をつけたい。 (d)落ち込みの裏側が抉れていて、奥の方に水面が見えるようなら、その水面 をピンポイントで狙い、エルクヘアー・カディスを投げ入れてみるのも面白い。用心深く身を潜めているヤマメやイワナがヒットすることがある。 (e)大きな巻き込みで、ごく細かい泡が集まって厚い絨毯のように水面を覆っているのを見かけることがある。そんな時は、エルクヘアー・カディスを泡の絨毯の中にキャストして、泡の下を引いてやれば、大物のイワナや、ブルック・トラウトがヒットすることがある。 (f)流れがカーブする地点では、淵が形成され、大きな巻き込みが出来ていることが多い。速い流れと巻き込みが接する緩流点でもライズすることがあるが、釣り人に追い込まれたナーバスな魚が多い。 (g)ごく浅い普通の瀬でも、流れの中に岩が頭を出して、岩の向こう側が釣り人には死角になって見えないことがある。そんな時、億劫がらずにその岩の下流に回り込んで岩の反対側にフライをキャストしてみると、思いがけず渓魚がヒットすることがある。 (h)分流があれば、たとえそれが小さな流れであっても、渓魚が潜んでいる可能性があるので狙ってみると良い。葦や、ブッシュに覆われていれば、ヒットする確率は高くなる。 (i)流れの中から突き出ている岩の裏(水流の当たる反対側)は、殊に陽が落ちてから渓魚がエルクヘアー・カディスにヒットすることが多い。日中でも白泡の中からアントに大イワナがライズすることがある。 |
||
|
|
||
|
(k)何度もフライを追って魚が姿を見せるが、フライを取り替えてもフライに食いつかない場合は、最後の手段としてフライを沈ませてみよう。時には一発でヒットすることがある。 (l)落差があり、流速のある山岳渓流では、#4以上のロッドと、7.5フィート、5X以上の短めの、太いリーダーの使用をお奨めする。今流行りの、#3以下の細いロッドや、極細の、ロング・リーダーでは、山岳渓流の荒々しい流れに乗った大型魚の逸走や、岸のブッシュや障害物に駆け込もうとする魚の引きに耐えるのは難しい。たとえ幸運にも、魚をランディング出来ても、ただそれは魚を弱らせただけの自己満足に過ぎず、自然保護の立場からみればあまり感心できることではない。欧米や、ニュージーランドなどの例を引き合いに出すまでも無く、魚を掛けたら、出来るだけ早くランディングし、リリースしてやることが望ましい。 まだこの他にも書きたいことはあるが、今回はこの辺りで終わりとしたい。
|
||
|
釣童のF.F.ワン・ポイント・アドバイス(3) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
釣期によって釣り方を変える 渓流の釣期は、大まかに言って初期、盛期、終期の3つに分けることができる。東京近郊の渓流を例にとれば、3〜4月が初期、5〜7月が盛期、8〜9月が終期になるだろう。 季節によって魚の釣り方は大きく変わる。フライを使って渓魚を狙うフライ・フィッシングも、当然季節によって、狙う河川や、ポイント、使用するフライなどが異なってくる。 同じ渓流でも、季節によって釣れたり釣れなかったりすることは、我々が日頃よく経験するところだが、このような経験を数多く積み重ねることによって、釣りに対する知識と理解が深まってくる。 釣行記録をつけよう 釣行記録を詳細につけ、それを何年も続けることによって、経験がより確かな事実として残り、信頼できるデーターとなる。 記録の内容は、年月日、時刻、河川名、フライ名、フライをどのように使ったか、渓魚名、尾数、天候、気温、水量、水温、濁りの有無、どんなポイントだったか、などである。 このような記録を10年20年と積み重ねることによって、いつ、どの川で、どんなフライを使えば、何が、何尾釣れるか、おおよそ見当がつくようになる。パソコンを使ってデーターベースを作れば、その記録は一層役立つものとなるだろう。 また、新聞、雑誌、テレビ番組などで、自分の釣りに役に立ちそうな記事や番組があれば、できるだけ保存するようにしておくと、将来、何かの折りに重宝するに違いない。
初期のフライ・フィッシング 東京近郊では3〜4月、全国共通の季節の指標として花の開花を例にとると、解禁から山吹の花が咲く直前辺りまでが初期に入るだろう。初期は渓流の水温が低く、したがって渓魚の活性は高くない。渓流でも中流や下流の、流れの緩やかなところで釣れるので、比較的釣り易い。天気は、晴れた暖かい日の方が水温が上がるので、この時期の釣りには適している。カゲロウのハッチも、日中が多く夕方は少ないので、ヤマメのイブニング・ライズはあまり期待できない。 3月のメソッド
桜の花が咲く4月に入ると、水温も上昇し、渓魚の動きも活発になってくる。ヤマメは淵から瀬に出て就餌するようになる。暖かい好天の日中にカゲロウが盛んにハッチし、小型のガガンボが、日陰の湿った岩裏などに密集しているのがよく見かけられる。解禁になってまだ日も浅く、警戒心の薄いヤマメが、日中のんびりとライズを繰り返すのを見ることがある。ヤマメのフライへのライズの仕方は割合スローで、合わせ易い。 4月のメソッド
盛期のフライ・フィッシング 東京近郊では、5月の連休に入り、山吹が咲き始める頃から7月下旬の梅雨明け頃までが盛期に当たるだろう。 渓流の水温が上昇すると共に、カゲロウその他の水棲昆虫の活動が活発化し、それらの昆虫を追って渓魚が盛んにライズするのがこの時期である。時として、大粒の雹が水面を叩くような、激しいライズに遭遇することがある。渓魚は流速のある瀬に散り、フライ・フィッシングはまさに最高の釣期を迎える。 季節が進み、釣り人に攻め続けられた渓魚たちは、日を追う毎に用心深くなってくる。初期にはあれほど容易に釣れた渓魚も、簡単には釣れなくなり、高度な技術が必要となってくる。管理釣り場で十分に実績のあるフライ・フィッシャーが、自然の渓流フィールドでは自分の釣技が全く通用しないことを思い知らされるのが、この頃である。 渓魚のライズは、渓魚が受けているプレッシャーの高さに比例して速くなり、釣り人の反射神経が試されることになる。この時期、晴天の日中はほとんどライズが無く、曇天の方が断然喰いが良い。 盛期のメソッド
終期のフライ・フィッシング 梅雨明けから禁漁までが終期である。 梅雨が開け、真夏に入ると、日中の水温は渓魚の生存限界近くまで上昇するところが多く、渓魚は朝夕しか餌付かなくなる。お盆を中心に多くの企業が夏休みを設定するので、渓流は涼を求め、釣りをする帰省客や行楽客で殷賑を極める。 お盆を過ぎると渓流はすっかり荒廃し、渓魚は激減してしまう。この渓魚の減り方は尋常ではなく、釣り以外の手段で違法に乱獲されるのではないかと疑われる。昔から、「夏ヤマメは1里1尾」と言われるように、夏場のヤマメ釣りは難しく、渓流の釣りは高山のイワナ釣りが主流となる。 日中にカゲロウのライズが見られることは滅多に無く、フライはテレストリアルが主体になる。 終期のメソッド
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
釣童のF.F.ワン・ポイント・アドバイス(4) デジカメ写真で見るポイント集<1> |
||||
| 最近では、渓流釣りの経験が全く無いまま、フライ・フィッシングを始める人が圧倒的に多いようである。彼らの主要なフィールドは管理釣り場や、
C&R区間である。 近頃、管理釣り場、C&R区間そのままの感覚で、渓流に進出してくるフライ・フィッシャーが増え、各地の渓流で、地元の渓流釣り師やフライ・フィッシャー達の顰蹙を買い、トラブルを起こしている話をよく耳にする。 渓流釣りのルールを守ろう
渓流釣りの経験の無いフライ・フィッシャーは、ライズのあるところ、魚が群れているところがポイントだと思い勝ちである。まだ日の高いうちから、岸辺に腰掛けてイブニング・ライズを待っているフライ・フィッシャーを見かけることがあるが、彼らは、日中でもフライがポイントに入れば、魚がライズすると云うことを知らないのである。 ポイントを知ろう ポイントを知ることが、渓魚のヒットの機会を増やし、キャスティング、フッキング、ランディングなどフライ・フィッシング全般の技術の向上へと繋がるのである。 最近、私はデジカメを持ち歩くことが多く、釣れた魚や、釣れたポイントを撮っている。デジカメは、偏光や、その他のフィルターが付けられないなど、光学式カメラと比較して不備な点があるが、薄暗くなったときでも見た目以上に良く写るなど、美点も多いのである。リヴァーサル・フィルムのASA100を使って撮ると、私のような素人は手振れすることが多いが、デジカメの場合、よほど暗い場合を除き、手振れすることはまず無いと言って良く、これが私がデジカメを愛用する最大の理由である。 瀬のポイント(1) (a)瀬の流心がポイントである。底石があり、しかも流れが複雑に縒れていて、底石の輪郭がはっきり見えないようなところに渓魚は潜んでいる。 (b)副流の流心。瀬には幾筋もの流れがあり、最大のものを主流、2番目のものを副流と呼ぶこととする。この流心にも底石があるが、はっきりとは見えない。逆にいえば、底石がはっきりと見えるようなところには魚はいないのである。
瀬のポイント(2) (c)手前の流れが主流で、瀬の流心から、瀬尻の駆け上がりにかけて好ポイントになっている。 (d)少し頭を出している岩の、向こう側の副流もポイントである。
荒瀬のポイント (a)落差の小さな落ち込みの肩で、ヤマメがよく付いているポイントである。 (b)流れの境目と、岩裏がポイント。 (c)小さな巻き込みに岩魚が隠れていることがある。不用意に足音を立てないように気をつけよう。 (d)ごく小さな落ち込みの肩。 (e)これも落ち込みの肩。 一口に荒瀬と言っても、細かく見れば、小さな落ち込み、落ち込みの肩、小さな巻き込み、岩裏などの集合であることが分かる。
|
||||
|
釣童のF.F.ワン・ポイント・アドバイス(5) デジカメ写真で見るポイント集<2> |
||||
|
渓流を構成する二大要素は瀬と淵である。ヤマメやイワナなど渓魚たちは、瀬と淵のいずれにも生息するが、季節や、さまざまな環境の変化に応じて、その生息場所を替えるのである。 渓魚は水温の低い冬期には淵にいて、水温が上昇する時期になると瀬に出て活動する。一般にヤマメは瀬を好み、イワナは淵を好むと言われるが、これは両者の就餌行動や、習性の違いによるものである。夏期であってもヤマメが淵で釣れることがあり、瀬の多い渓ではイワナは瀬で就餌する。ヤマメとイワナが混棲する渓では、ヤマメは瀬、イワナは淵と棲み分けることがよく見られる。 淵のポイント
(a)ぶっつけの下流によく見られる大淵である。この淵はやや浅いが、これが深くても条件は同じである。白泡の消える辺りから、淵の中央部にかけてがポイントである。 (b)淵尻の緩い駆け上がりで、先行者がいない時のポイント。淵尻で渓魚がのんびりと餌を待っていたり、周回していたりすることがあるので、不用意に近づいて追い込まないように気をつけよう。
ぶっつけの淵のポイント
(a)小規模な渓流の曲流点にしばしば出現する。ぶっつけの崖の下が深く抉られていることが多い。この淵の場合は、流れ込んだ水が淵に留まることは無く、すぐに淵尻から流れ出て行ってしまう。岸壁沿いが好ポイント。
(b)流れ込みの向こうの小さな巻き込み。見逃し易いが、魚が潜んでいることがある。強い流れが、まともに壁にぶつかるところには、魚はいないと思って良い。
堰堤下の淵のポイント (a)最近、渓流には数多くの堰堤が造られ、渓魚たちの遡上を妨げて、棲息範囲を狭めている。陸封型の渓魚はともかく、殊に、北海道のヤマメなど、海と川を行き来している魚たちに致命的な打撃を与えている。好むと好まざるとに係わらず、渓魚たちは堰堤下の淵に生息し、就餌する。堰堤下の淵(滝壷も条件は同じ)の岸寄り(片側だけの場合が多い)には、流れがあり渓魚たちはこの流れに潜んで餌を待っている。時として、特大魚がヒットすることがある。
(b)沈み石の周りも良いポイントである。
|
||||